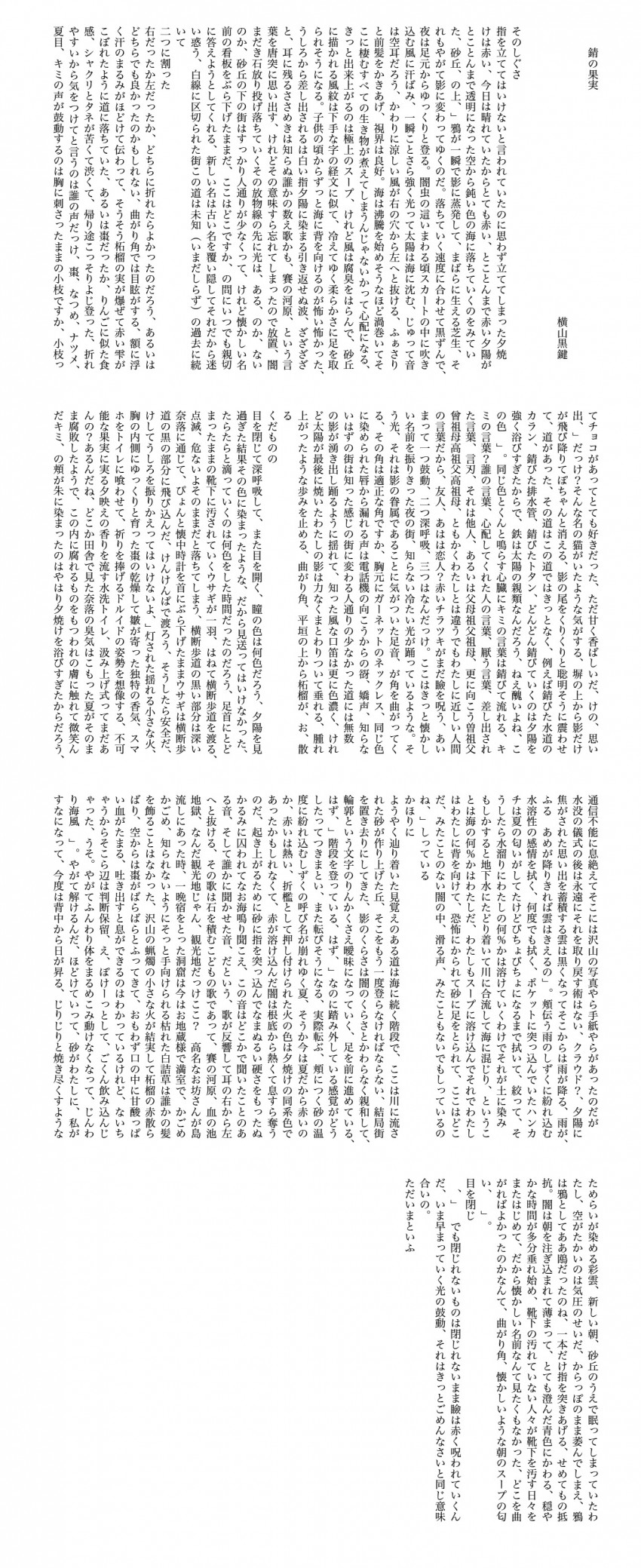錆の果実 横山黒鍵
そのしぐさ
指を立ててはいけないと言われていたのに思わず立ててしまった夕焼け
は赤い、今日は晴れていたからとても赤い、とことんまで赤い夕陽がと
ことんまで透明になった空から鈍い色の海に落ちていくのをみていた、
砂丘、の上、」鴉が一瞬で影に蒸発して、まばらに生える芝生、それも
やがて影に変わってゆくのだ。落ちていく速度に合わせて黒ずんで、夜
は足元からゆっくりと登る。闇虫の這いまわる頃スカートの中に吹き込
む風に汗ばみ、一瞬ことさら強く光って太陽は海に沈む、じゅって音は
空耳だろう、かわりに涼しい風が右の穴から左へと抜ける、ふぁさりと
前髪をかきあげ、視界は良好。海は沸騰を始めそうなほど渦巻いてそこ
に棲むすべての生き物が煮えてしまうんじゃないかって心配になる、き
っと出来上がるのは極上のスープ、けれど風は腐臭をはらんで、砂丘に
描かれる風紋は下手な字の経文に似て、冷えてゆく柔らかさに足を取ら
れそうになる。子供の頃からずっと海に背を向けるのが怖い怖かった、
うしろから差し出されるは白い指夕陽に染まる引き返せぬ波、ざざざざ
と、耳に残るささめきは知らぬ誰かの数え歌かも、賽の河原、という言
葉を唐突に思い出す、けれどその意味すら忘れてしまったので放置、闇
まだき石放り投げ落ちていくその放物線の先に光は、ある、のか、ない
のか、砂丘の下の街はすっかり人通りが少なくって、けれど懐かしい名
前の看板をぶら下げたままだ、ここはどこですか、の問にいつでも親切
に答えようとしてくれる、新しい名は古い名を覆い隠してそれだから迷
い惑う、白線に区切られた街この道は未知(いまだしらず)の過去に続
いて
二つに割った
右だったか左だったか、どちらに折れたらよかったのだろう、あるいは
どちらでも良かったのかもしれない、曲がり角では目眩がする、額に浮
く汗のまるみがほどけて伝わって、そうそう柘榴の実が爆ぜて赤い雫が
こぼれたように道に落ちていた、あるいは棗だったか、りんごに似た食
感、シャクリとタネが苦くて渋くて、帰り途こっそりよじ登った、折れ
やすいから気をつけてと言うのは誰の声だっけ、棗、なつめ、ナツメ、
夏目、キミの声が鼓動するのは胸に刺さったままの小枝ですか、小枝っ
てチョコがあってとても好きだった、ただ甘く香ばしいだ、けの、思い
出、」だっけ?そんな名の猫がいたような気がする、塀の上から影だけ
が飛び降りてぽちゃんと消える、影の尾をくりくりと聡明そうに震わせ
て、道があった、その道はこの道ではきっとなく、例えば錆びた水道の
カラン、錆びた排水管、錆びたトタン、どんどん錆びていくのは夕陽を
強く浴びすぎたからで、鉄は太陽の親類なんだろう、ねえ醜いよね、こ
の色 」。同じ色とくんと鳴らす心臓にキミの言葉は錆びて流れる、キ
ミの言葉?誰の言葉、心配してくれた人の言葉、厭う言葉、差し出され
た言葉、言刃、それは他人、あるいは父母祖父祖母、更に向こう曽祖父
曾祖母高祖父高祖母、ともかくわたしとは違うでもわたしに近しい人間
の言葉だから、友人、あはは恋人?赤いチラツキがまだ瞼を呪う、あい
まって一つ鼓動、二つ深呼吸、三つはなんだっけ。ここはきっと懐かし
い名前を振りきった夜の街、知らない冷たい光が踊っているような。そ
う光、それは影の眷属であることに気がついた足音、が角を曲がってく
る、その角は適正な角ですか、胸元にガーネットのネックレス、同じ色
に染められた唇から漏れる声は電話機の向こうからの谺、嬌声、知らな
いはずの街は知った感じの街に変わる人通りの少なかった道には無数の
影が湧き出し踊るように揺れて、知った風な口笛は更に色濃く、けれど
太陽が最後に焼いたわたしの影は力なくまとわりついて垂れる、腫れ上
がったような歩みを止める、曲がり角、平垣の上から柘榴が、お、散る
くだものの
目を閉じて深呼吸して、また目を開く、瞳の色は何色だろう、夕陽を見
過ぎた結果その色に染まったような、だから見送ってはいけなかった、
たらたらと滴っていくのは何色をした時間だったのだろう、足首にとど
まったままの靴下に汚されていくウサギが一羽、はねて横断歩道を渡る、
点滅、危ないよそのままだと落ちてしまう、横断歩道の黒い部分は深い
奈落に通じて、ぴょんと懐中時計を首にぶら下げたままウサギは横断歩
道の黒の部分に飛び込んだ、けんけんぱで渡ろう、そうしたら安全だ、
けしてうしろを振りかえってはいけないよ、」灯された揺れる小さな火、
胸の内側にゆっくりと育った棗の乾燥して皺が寄った独特の香気、スマ
ホをトイレに喰わせて、祈りを捧げるドルイドの姿勢を想像する、不可
能な果実に実る夕映えの香りを流す水洗トイレ、汲み上げ式ってまだあ
んの?あるんだね、どこか田舎で見た奈落の臭気はこもった夏がそのま
ま腐敗したようで、この内に腐れるものをもつわれの膚に触れて微笑ん
だキミ、の頬が朱に染まったのはやはり夕焼けを浴びすぎたからだろう、
通信不能に息絶えてそこには沢山の写真やら手紙やらがあったのだが水
没の儀式の後は永遠にそれを取り戻す術はない、クラウド?、夕陽に焦
がされた思い出を蓄積する雲は黒くなってそこからは雨が降る、雨が、
ふる あめが降りきれば雲はきえるの」。頬伝う雨のしずくに紛れ込む
水溶性の感情を拭く、何度でも拭く、ポケットに突っ込んでいたハンカ
チは夏の匂いがしてたけどびちょびちょになるまで拭いて、絞って、そ
うしたら水溜りにわたしの何%かは溶けていくわけでそれが土に染みも
しかすると地下水にたどり着いて川に合流して海に混じり、ということ
は海の何%かはわたしだ、わたしもスープに溶け込んでそれでわたしは
わたしに背を向けて、恐怖にかられて砂に足をとられて、ここはどこだ、
みたことのない闇の中、滑る声、みたこともないでもしっているのね、」
しっている
かほりに
ようやく辿り着いた見覚えのある道は海に続く階段で、ここは川に流さ
れた砂が作り上げた丘、そこをもう一度登らなければならない、結局街
を置き去りにしてきた、影のくらさは闇のくらさとかわらなく親和して、
輪郭という文字のりんかくさえ曖昧になっていく、足を前に進めている、
はず、」階段を登っている、はず、」なのに踏み外している感覚がどう
したってつきまとい、また転びそうになる、実際転ぶ、頬につく砂の温
度に紛れ込むしずくの呼び名が崩れゆく夏、そうか今は夏だから赤いの
か、赤いは熱い、折檻として押し付けられた火の色は夕焼けの同系色で
あったかもしれなくて、赤が溶け込んだ闇は根底から熱くて息すら奪う
のだ、起き上がるために砂に指を突っ込んでなまぬるい硬さをもったぬ
かるみに囚われてなお海鳴り聞こえ、この音はどこかで聞いたことのあ
る音、そして誰かに聞かせた音、だという、歌が反響して耳の右から左
へと抜ける、その歌は石を積むこどもの歌であって、賽の河原、血の池
地獄、なんだ観光地じゃん、観光地だっけここ? 高名なお坊さんが島
流しにあった時、一晩宿をとった洞窟は今はお地蔵様で満室で、かごめ
かごめ、知られないようにそっと手向けられる枯れた白詰草は誰かの髪
を飾ることはなかった、沢山の蝋燭の小さな火が結実して柘榴の赤散ら
ばり、空からは棗がばらばらとふってきて、おもわず口の中に甘酸っぱ
い血がたまる、吐き出すと息ができるのはわかっているけれど、ないち
ゃうからそこら辺は判断保留、え、ぽけーっとして、ごくん飲み込んじ
ゃった、うそ。やがてふんわり体をまるめこみ動けなくなって、じんわ
り海風 」。やがて解けるんだ、ほどけていって、砂がわたしに、私が
すなになって、今度は背中から日が昇る、じりじりと焼き尽くすような
ためらいが染める彩雲、新しい朝、砂丘のうえで眠ってしまっていたわ
たし、空がたかいのは気圧のせいだ、からっぽのまま萎んでしまえ、鴉
は鴉としてああ鴎だったのね、一本だけ指を突きあげる、せめてもの抵
抗。闇は朝を注ぎ込まれて薄まって、とても澄んだ青色にかわる、穏や
かな時間が多分垂れ始め、靴下の汚れていない人々が靴下を汚す日々を
またはじめて、だから懐かしい名前なんて見たくもなかった、どこを曲
がればよかったのかなんて、曲がり角、懐かしいような朝のスープの匂
い、 」。
目を閉じ
、」 でも閉じれないものは閉じれないまま瞼は赤く呪われていくん
だ、いま早まっていく光の鼓動、それはきっとごめんなさいと同じ意味
合いの。
ただいまといふ