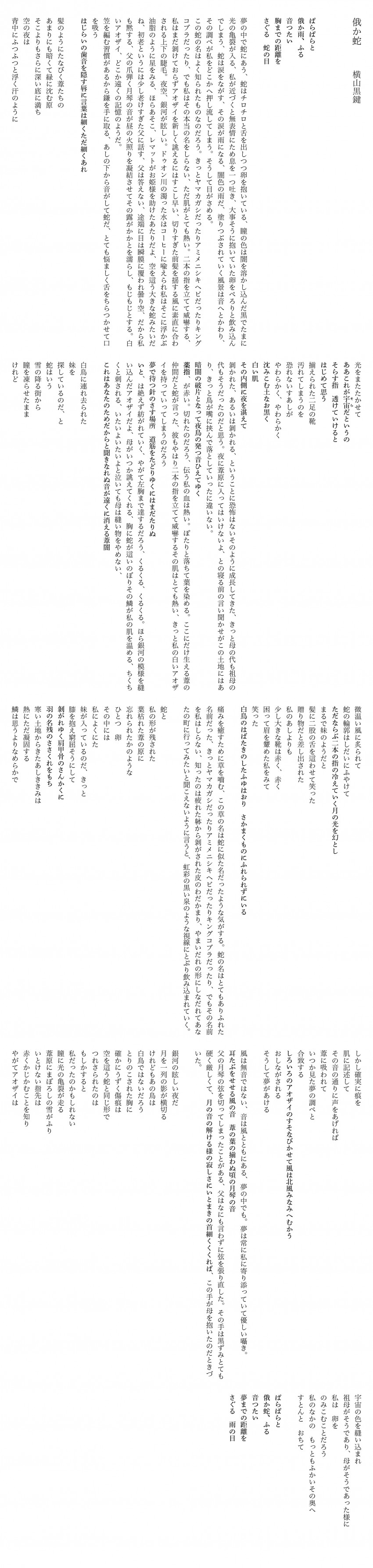俄か蛇 横山黒鍵
ぱらぱらと
俄か雨、ふる
音つたい
胸までの距離を
さぐる 蛇の目
夢の中で蛇にあう、蛇はチロチロと舌を出しつつ卵を抱いている、瞳の色は闇を溶かし込んだ黒でたまに
光の亀裂が入る、私が近づくと無表情にため息を一つ吐き、大事そうに抱いていた卵をぺろりと飲み込ん
でしまう、蛇は涙をながす、その涙が雨になる、闇色の雨だ、塗りつぶされていく風景は音へとかわり、
その調べが私をどこかへ押し流してしまう。そうして目がさめる。
この蛇の名はよく知られたものなのだろう。きっとヤマカガシだったりアミメニシキヘビだったりキング
コブラだったり、でも私はその本当の名をしらない、ただ肌がとても熱い。二本の指を立てて威嚇する、
私はまだ剥けておらずアオザイを新しく誂えるにはすこし早い、切りすぎた前髪を揺する風に素直に合わ
される上下の睫毛。夜空、銀河が眩しい。ドゥオン川の濁った水はコーヒーに喩えられ私はそこに浮かぶ
油脂のように星をみる、ほらあそこ、レマットがお姫様を助けたあたりだよ、空を這う大きな蛇みたいだ
ね、初老というには少し老けすぎた父に話す、父は答えない、途端に目は瞬膜に覆われ曇り空、だから私
も黙する、父の爪弾く月琴の音が昼の火照りを凝結させてその露がかかとを濡らし、もじもじとする。白
いアオザイ、どこか遠くの記憶のようだ。
笠を編む習慣があるから鎌を手に取る、あしの下から音がして蛇だ、とても悩ましく舌をちらつかせて口
を吸う
はじらいの歯音を隠す唇に言葉は細くただ細くあれ
髪のようにたなびく葦たちの
あまりにも暗くて緑に沈む原
そこよりもさらに深い底に満ち
空の夜は
背中にふつふつと浮く汗のように
光をまたたかせて
ああこれが
そらす指 透けていけると
はじめて思う
揃えられた二足の靴
汚れてしまうのを
恐れないすあしが
やわらかく、やわらかく
沈みこむ土なお黒く
白い肌
その内側に夜を湛えて
剥かれた、あるいは剥かれる、ということに恐怖はないそのように成長してきた、きっと母の代も祖母の
代もそうだったのだと思う。夜に葦原に入ってはいけないよ、との寝る前の言い聞かせがこの土地にはあ
り、きっと鳥が嘴に挟んで落としていったに違いない。
暗闇の破片となって夜鳥の発つ音ひえてゆく
薬指、が赤い。切れたのだろう、伝う私の血は熱い。ぽたりと落ちて葉を染める。ここにだけ生える葦の
仲間だと蛇が言った、彼もやはり二本の指を立てて威嚇するその肌はとても熱い、きっと私の白いアオザ
イを持っていってしまうのだろう
夢で待つ針のさす場所 道筋をたどりゆくにはまだたりぬ
いと、は絶えず紡がれていく、やがて左胸まで達するだろう、くるくる、くるくる。ほら銀河の模様を縫
い込んだアオザイだよ、母がいつか誂えてくれる、胸に蛇が這いのぼりその鱗が私の肌を温める、ちくち
くと刺される、いたいよいたいよと泣いても母は縫い物をやめない、
これはあなたのためだからと聞きなれぬ音が遠くに消える葦闇
白鳥に連れ去られた
妹を
探しているのだ、と
蛇はいう
雪の降る街から
瞳を凍らせたまま
けれど
微温い風に炙られて
蛇の輪郭はしだいにふやけて
ただならぶ二本の指の冷えていく月の光を幻とし
まるで妹のようだと
髪に二股の舌を這わせて笑った
贈り物だと差し出された
私のあしよりも
少し大きな靴は赤く、赤く
困って眉を顰めた私をみて
笑った
白鳥のはばたきのしたふゆはおり さかまくものにふれられずにいる
痛みを癒すために草を噛む、この草の名は蛇に似た名だったような気がする。蛇の名はとてもありふれた
名前だった、きっとヤマカガシだったりアミメニシキヘビだったりキングコブラだったり、でもその名前
を私はしらない、知ったのは疲れた躰から剥がされた皮のわだかまり、やまいだれの形にしなだれてあな
たの町に行ってみたいと聞こえないように言うと、虹彩の黒い泉のような視線にとぷり飲み込まれていく。
蛇と
私の形が残された
葉枯れた葦の原に
忘れられたかのような
ひとつ 卵
その中には
私によくにた
妹が入っているのだ、きっと
膝を抱え窮屈そうにして
剥がれゆく肩甲骨のさんかくに
羽の名残のささくれをもち
寒い土地からきたあしききみは
熱にただ凝固する
鱗は思うよりなめらかで
しかし確実に痕を
肌に記述して
その音の通りに声をあげれば
葦に吸われて
いつか見た夢の調べと
合致する
しろいろのアオザイのすそなびかせて風は北風みなみへむかう
おしながされる
そうして夢があける
風は無音ではない、音は風とともにある、夢の中でも。夢は常に私に寄り添っていて優しい囁き。
耳たぶをせせる風の音 葦の葉の揃わぬ頃の月琴の音
父の月琴の弦を切ってしまったことがある、父はなにも言わずに弦を張り直した。その手は黒ずみとても
硬く厳しくて、月の音の解ける様の寂しさにいとまきの首細くくくれば、この手が母を抱いたのだときづ
いた。
銀河の眩しい夜だ
月を一列の影が横切る
けれどもあの鳥は
白鳥ではないだろう
とりのこされた胸に
確かにうずく傷痕は
空を這う蛇と同じ形で
つれさられたのは
もしかすると
私だったのかもしれない
瞳に光の亀裂が走る
葦原にまぼろしの雪がふり
いとけない指先は
赤くかじかむことを知り
やがてアオザイは
宇宙の色を縫い込まれ
祖母がそうであり、母がそうであった様に
私は 卵を
のみこむことだろう
私のなかの もっともふかいその奥へ
すとんと おちて
ぱらぱらと
俄か蛇、ふる
音つたい
夢までの距離を
さぐる 雨の目