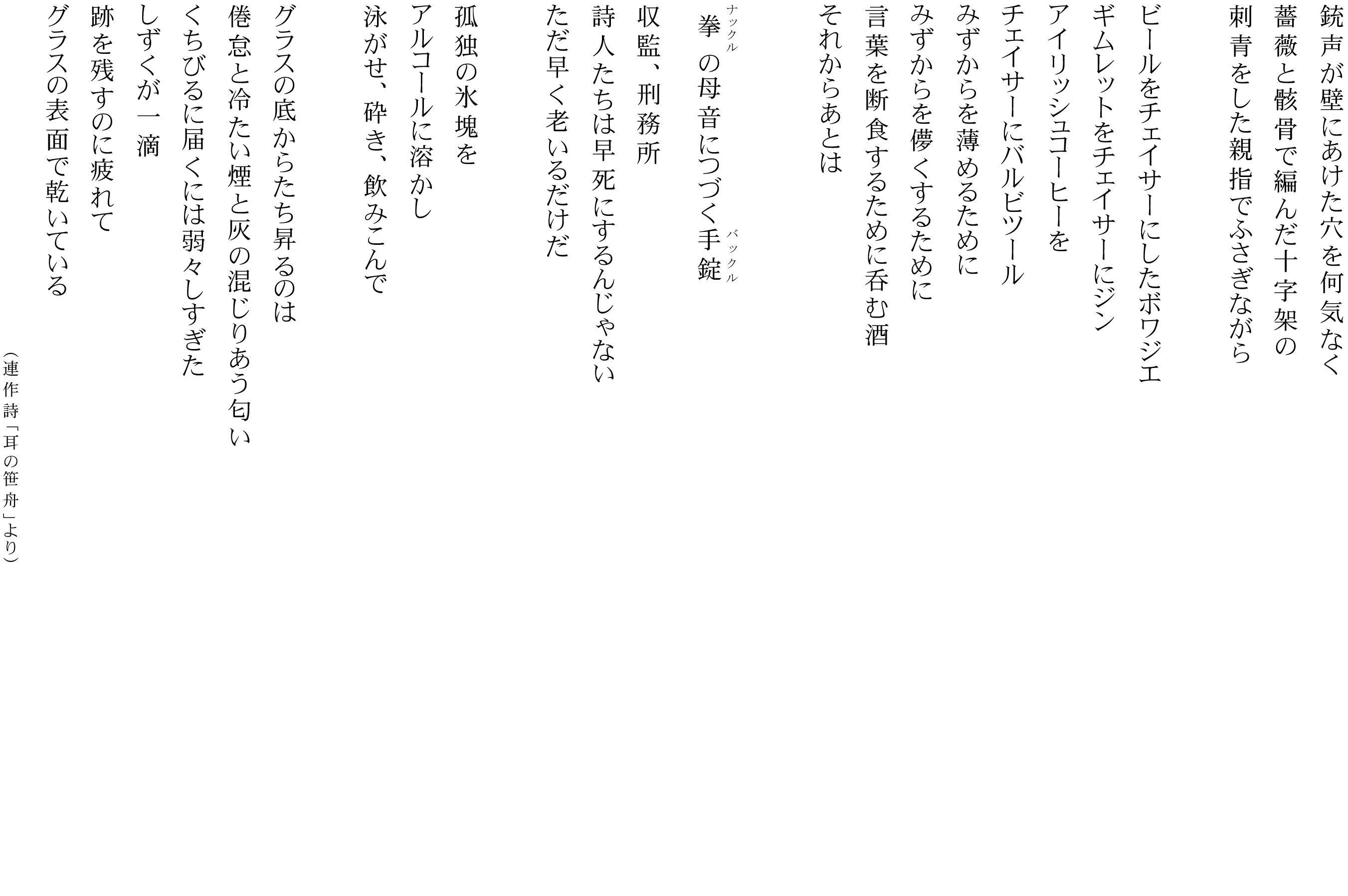セロニアス・モンクを聴きながら 石田 瑞穂
―イーストヴィレッジ、W・H・オーデンが通ったバーの後釜のバーで
もう三日も猛暑がつづいていた
夕方からの予報は雷雨
夏のニューヨークはいつもこうだ
大気のかたまりも人間も
熱いのと冷たいのがぶつかる
店のなかは
多少ひんやりしていたが
だからといってなにも変わらない
バーのひんやりした涼しさは
孤独の匂いがする
それも漠然とした孤独ではなく
ぼく自身の孤独
ぼく自身の匂い
ジュークボックスからは
チャーリー・ラウズのテナーが
魔女のように甘く
損傷を負った
アメリカの友だちであり
いまや千鳥足の若い詩人が
Ruby My Dearをわざわざ聴こうと
五十セント硬貨をトスしている
銃声が壁にあけた穴を何気なく
薔薇と骸骨で編んだ十字架の
刺青をした親指でふさぎながら
ビールをチェイサーにしたボワジエ
ギムレットをチェイサーにジン
アイリッシュコーヒーを
チェイサーにバルビツール
みずからを薄めるために
みずからを儚くするために
言葉を断食するために呑む酒
それからあとは
収監、刑務所
詩人たちは早死にするんじゃない
ただ早く老いるだけだ
孤独の氷塊を
アルコールに溶かし
泳がせ、砕き、飲みこんで
グラスの底からたち昇るのは
倦怠と冷たい煙と灰の混じりあう匂い
くちびるに届くには弱々しすぎた
しずくが一滴
跡を残すのに疲れて
グラスの表面で乾いている
(連作詩「耳の笹舟」より)