


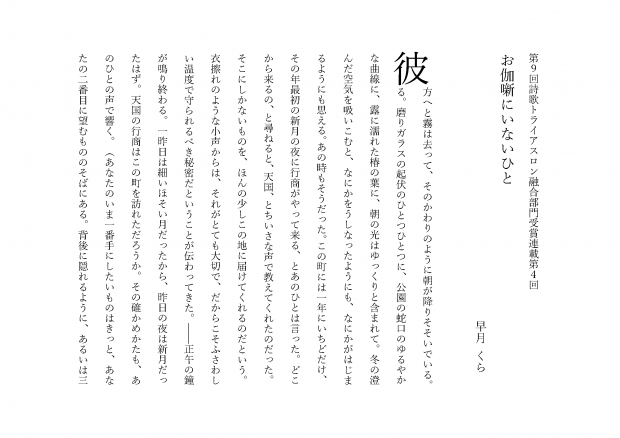
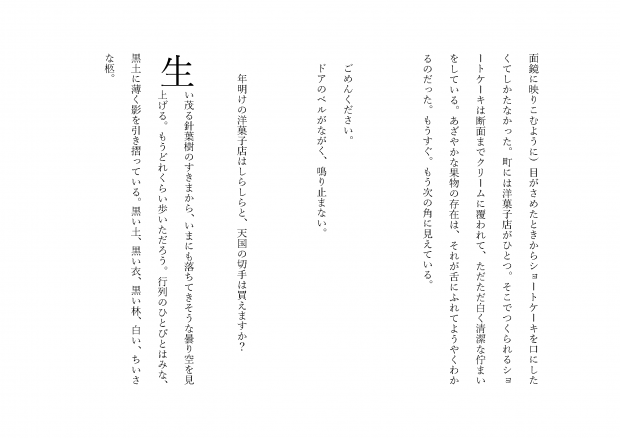
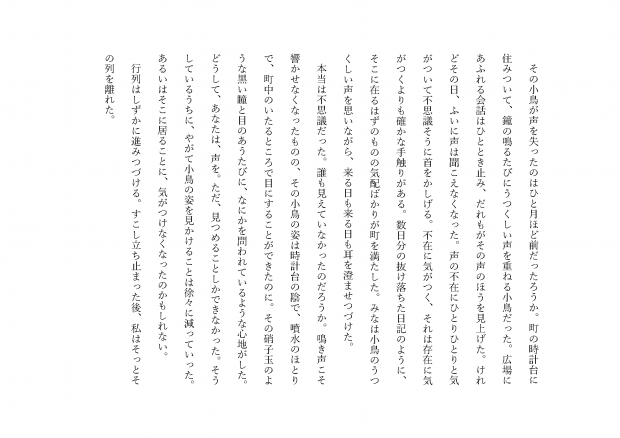
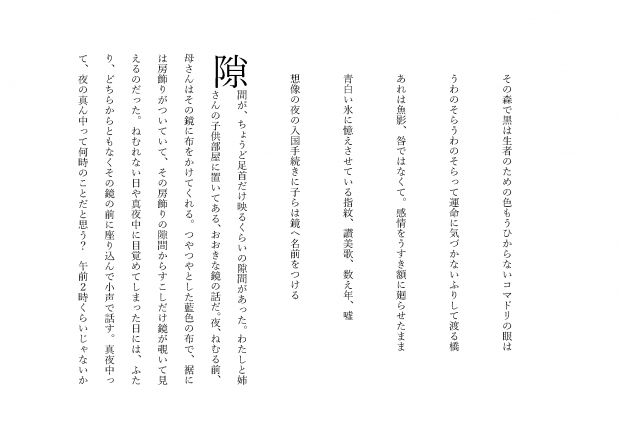
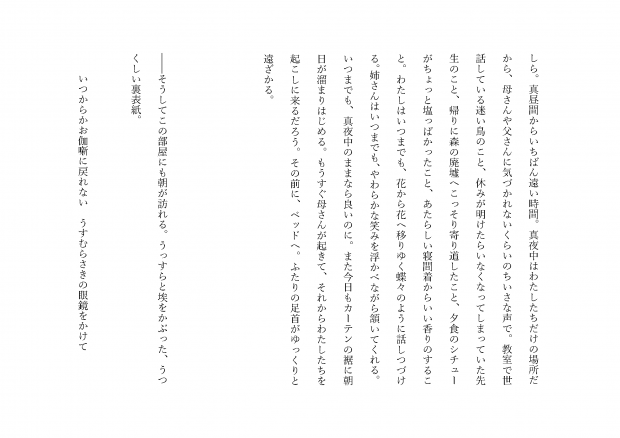
第9回詩歌トライアスロン融合部門受賞連載第4回
お伽噺にいないひと
早月くら
彼
方へと霧は去って、そのかわりのように朝が降りそそいでいる。磨りガラスの起伏のひとつひとつに、公園の蛇口のゆるやかな曲線に、露に濡れた椿の葉に、朝の光はゆっくりと含まれて。冬の澄んだ空気を吸いこむと、なにかをうしなったようにも、なにかがはじまるようにも思える。あの時もそうだった。この町には一年にいちどだけ、その年最初の新月の夜に行商がやって来る、とあのひとは言った。どこから来るの、と尋ねると、天国、とちいさな声で教えてくれたのだった。そこにしかないものを、ほんの少しこの地に届けてくれるのだという。衣擦れのような小声からは、それがとても大切で、だからこそふさわしい温度で守られるべき秘密だということが伝わってきた。——正午の鐘が鳴り終わる。一昨日は細いほそい月だったから、昨日の夜は新月だったはず。天国の行商はこの町を訪れただろうか。その確かめかたも、あのひとの声で響く。(あなたのいま一番手にしたいものはきっと、あなたの二番目に望むもののそばにある。背後に隠れるように、あるいは三面鏡に映りこむように)目がさめたときからショートケーキを口にしたくてしかたなかった。町には洋菓子店がひとつ。そこでつくられるショートケーキは断面までクリームに覆われて、ただただ白く清潔な佇まいをしている。あざやかな果物の存在は、それが舌にふれてようやくわかるのだった。もうすぐ。もう次の角に見えている。
ごめんください。
ドアのベルがながく、鳴り止まない。
年明けの洋菓子店はしらしらと、天国の切手は買えますか?
生
い茂る針葉樹のすきまから、いまにも落ちてきそうな曇り空を見上げる。もうどれくらい歩いただろう。行列のひとびとはみな、黒土に薄く影を引き摺っている。黒い土、黒い衣、黒い林、白い、ちいさな柩。
その小鳥が声を失ったのはひと月ほど前だったろうか。町の時計台に住みついて、鐘の鳴るたびにうつくしい声を重ねる小鳥だった。広場にあふれる会話はひととき止み、だれもがその声のほうを見上げた。けれどその日、ふいに声は聞こえなくなった。声の不在にひとりひとりと気がついて不思議そうに首をかしげる。不在に気がつく、それは存在に気がつくよりも確かな手触りがある。数日分の抜け落ちた日記のように、そこに在るはずのものの気配ばかりが町を満たした。みなは小鳥のうつくしい声を思いながら、来る日も来る日も耳を澄ませつづけた。
本当は不思議だった。誰も見えていなかったのだろうか。鳴き声こそ響かせなくなったものの、その小鳥の姿は時計台の陰で、噴水のほとりで、町中のいたるところで目にすることができたのに。その硝子玉のような黒い瞳と目のあうたびに、なにかを問われているような心地がした。どうして、あなたは、声を。ただ、見つめることしかできなかった。そうしているうちに、やがて小鳥の姿を見かけることは徐々に減っていった。あるいはそこに居ることに、気がつけなくなったのかもしれない。
行列はしずかに進みつづける。すこし立ち止まった後、私はそっとその列を離れた。
その森で黒は生者のための色もうひからないコマドリの眼は
うわのそらうわのそらって運命に気づかないふりして渡る橋
あれは魚影、咎ではなくて。感情をうすき額に廻らせたまま
青白い氷に憶えさせている指紋、讃美歌、数え年、嘘
想像の夜の入国手続きに子らは鏡へ名前をつける
隙
間が、ちょうど足首だけ映るくらいの隙間があった。わたしと姉さんの子供部屋に置いてある、おおきな鏡の話だ。夜、ねむる前、母さんはその鏡に布をかけてくれる。つやつやとした藍色の布で、裾には房飾りがついていて、その房飾りの隙間からすこしだけ鏡が覗いて見えるのだった。ねむれない日や真夜中に目覚めてしまった日には、ふたり、どちらからともなくその鏡の前に座り込んで小声で話す。真夜中って、夜の真ん中って何時のことだと思う? 午前2時くらいじゃないかしら。真昼間からいちばん遠い時間。真夜中はわたしたちだけの場所だから、母さんや父さんに気づかれないくらいのちいさな声で。教室で世話している迷い鳥のこと、休みが明けたらいなくなってしまっていた先生のこと、帰りに森の廃墟へこっそり寄り道したこと、夕食のシチューがちょっと塩っぱかったこと、あたらしい寝間着からいい香りのすること。わたしはいつまでも、花から花へ移りゆく蝶々のように話しつづける。姉さんはいつまでも、やわらかな笑みを浮かべながら頷いてくれる。いつまでも、真夜中のままなら良いのに。また今日もカーテンの裾に朝日が溜まりはじめる。もうすぐ母さんが起きて、それからわたしたちを起こしに来るだろう。その前に、ベッドへ。ふたりの足首がゆっくりと遠ざかる。
——そうしてこの部屋にも朝が訪れる。うっすらと埃をかぶった、うつくしい裏表紙。
いつからかお伽噺に戻れない うすむらさきの眼鏡をかけて






