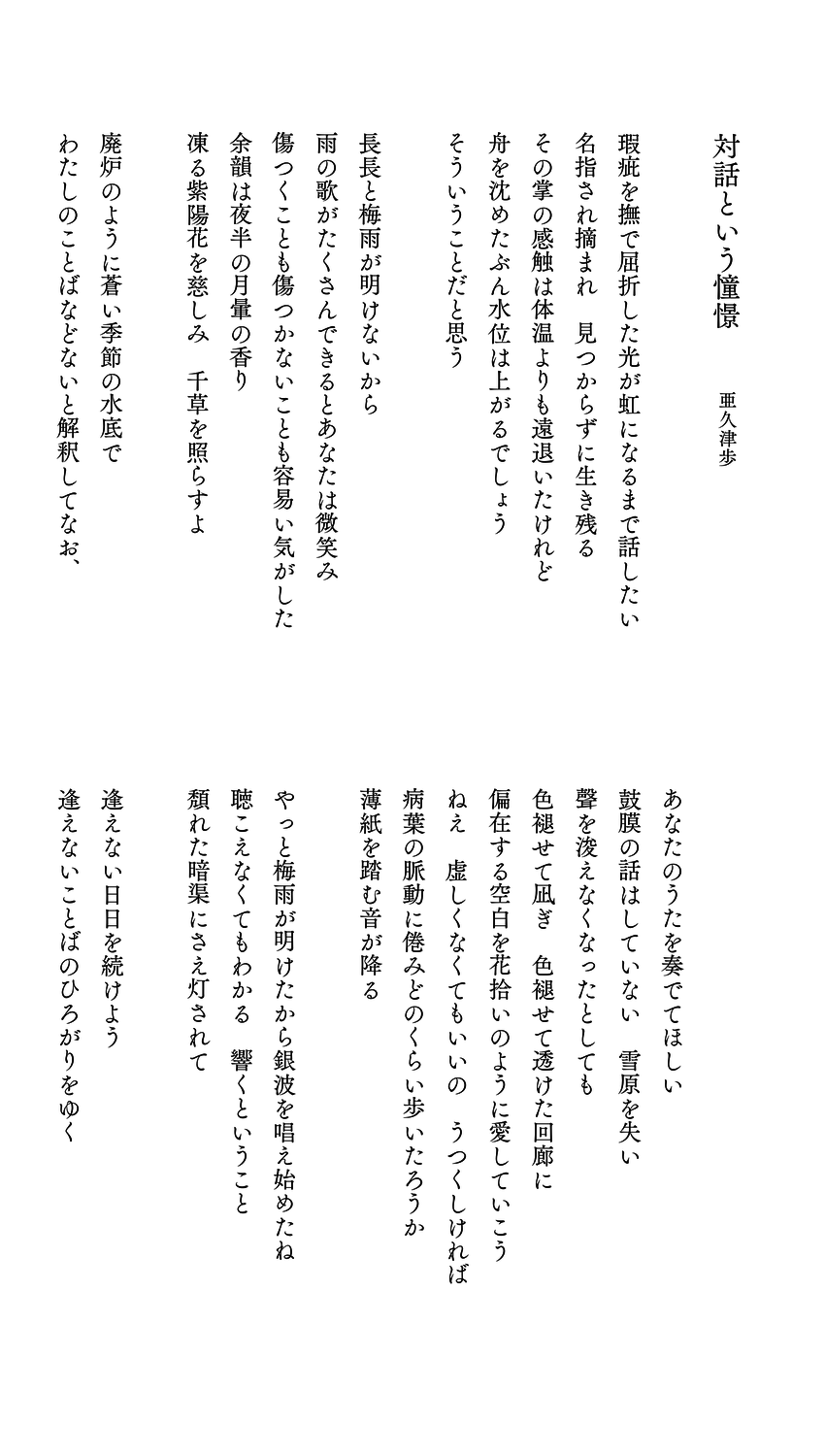対話という憧憬 亜久津歩
瑕疵を撫で屈折した光が虹になるまで話したい
名指され摘まれ 見つからずに生き残る
その掌の感触は体温よりも遠退いたけれど
舟を沈めたぶん水位は上がるでしょう
そういうことだと思う
長長と梅雨が明けないから
雨の歌がたくさんできるとあなたは微笑み
傷つくことも傷つかないことも容易い気がした
余韻は夜半の月暈の香り
凍る紫陽花を慈しみ 千草を照らすよ
廃炉のように蒼い季節の水底で
わたしのことばなどないと解釈してなお、
あなたのうたを奏でてほしい
鼓膜の話はしていない 雪原を失い
聲を浚えなくなったとしても
色褪せて凪ぎ 色褪せて透けた回廊に
偏在する空白を花拾いのように愛していこう
ねえ 虚しくなくてもいいの うつくしければ
病葉の脈動に倦みどのくらい歩いたろうか
薄紙を踏む音が降る
やっと梅雨が明けたから銀波を唱え始めたね
聴こえなくてもわかる 響くということ
頽れた暗渠にさえ灯されて
逢えない日日を続けよう
逢えないことばのひろがりをゆく