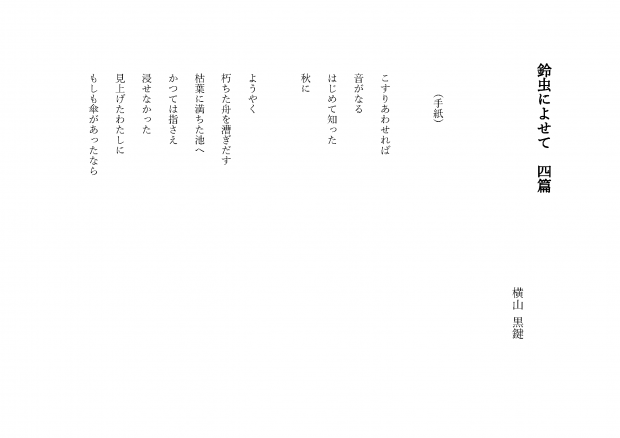
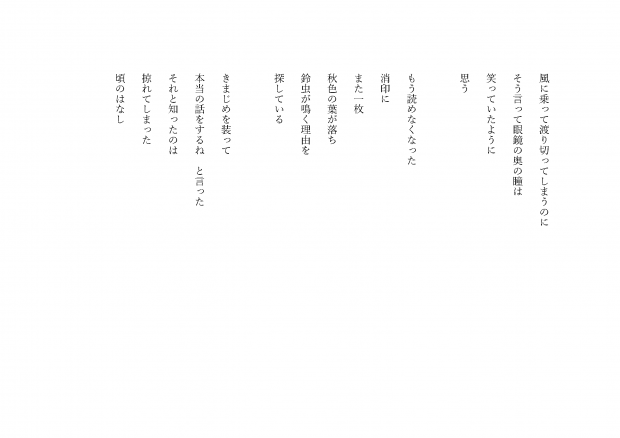
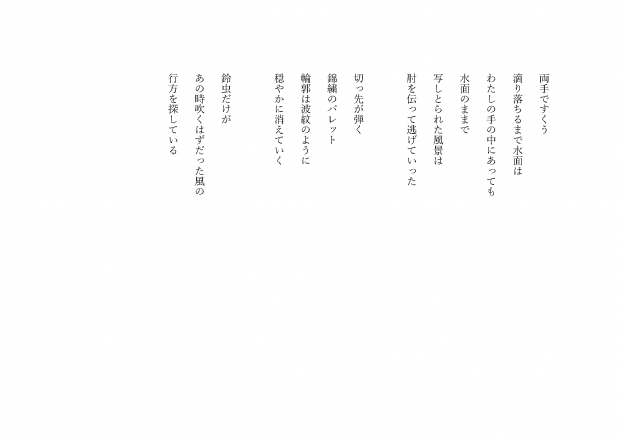
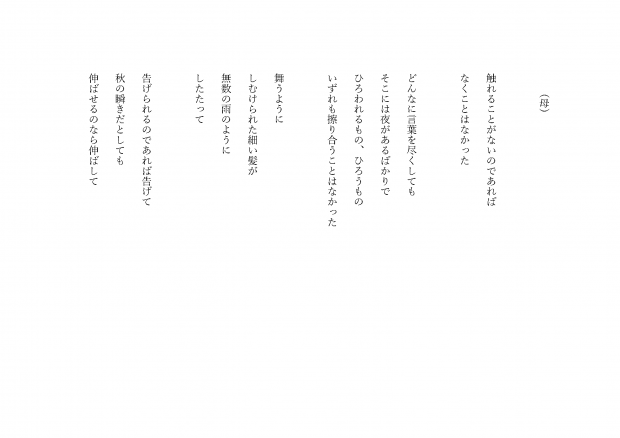
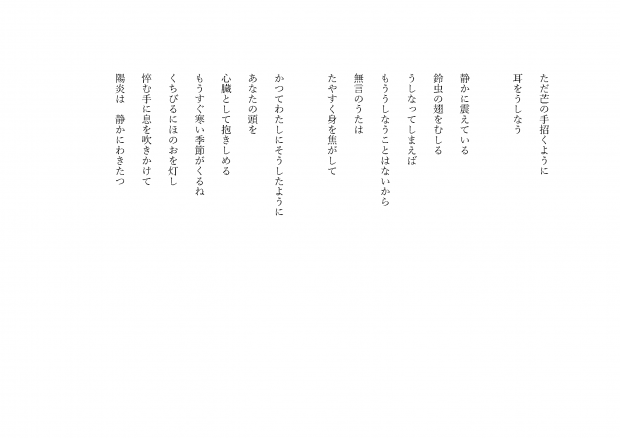
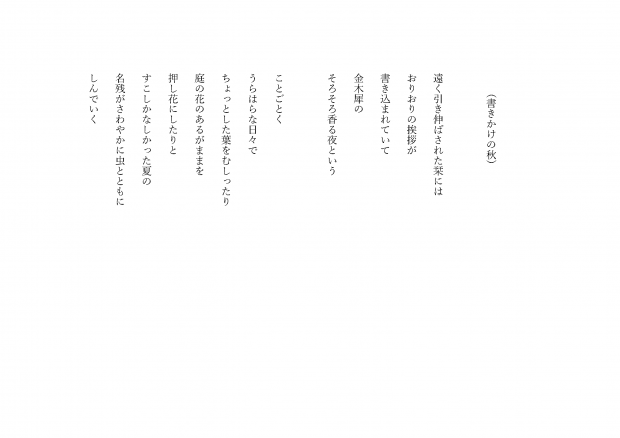
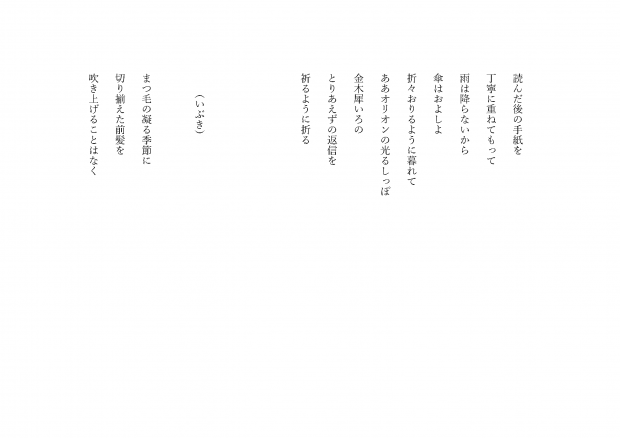
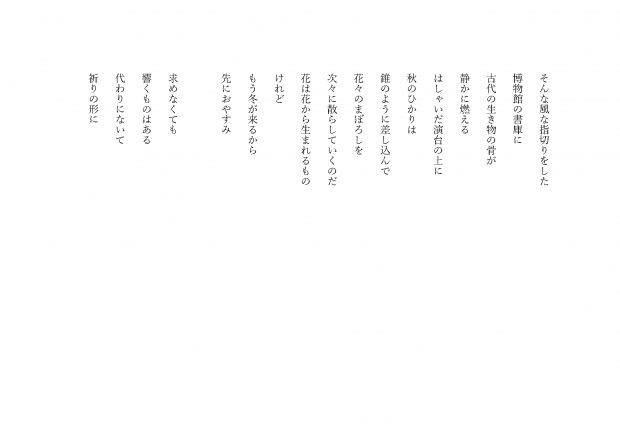

鈴虫によせて 四篇
横山 黒鍵
(手紙)
こすりあわせれば
音がなる
はじめて知った
秋に
ようやく
朽ちた舟を漕ぎだす
枯葉に満ちた池へ
かつては指さえ
浸せなかった
見上げたわたしに
もしも傘があったなら
風に乗って渡り切ってしまうのに
そう言って眼鏡の奥の瞳は
笑っていたように
思う
もう読めなくなった
消印に
また一枚
秋色の葉が落ち
鈴虫が鳴く理由を
探している
きまじめを装って
本当の話をするね と言った
それと知ったのは
掠れてしまった
頃のはなし
両手ですくう
滴り落ちるまで水面は
わたしの手の中にあっても
水面のままで
写しとられた風景は
肘を伝って逃げていった
切っ先が弾く
錦繍のパレット
輪郭は波紋のように
穏やかに消えていく
鈴虫だけが
あの時吹くはずだった風の
行方を探している
(母)
触れることがないのであれば
なくことはなかった
どんなに言葉を尽くしても
そこには夜があるばかりで
ひろわれるもの、ひろうもの
いずれも擦り合うことはなかった
舞うように
しむけられた細い髪が
無数の雨のように
したたって
告げられるのであれば告げて
秋の瞬きだとしても
伸ばせるのなら伸ばして
ただ芒の手招くように
耳をうしなう
静かに震えている
鈴虫の翅をむしる
うしなってしまえば
もううしなうことはないから
無言のうたは
たやすく身を焦がして
かつてわたしにそうしたように
あなたの頭を
心臓として抱きしめる
もうすぐ寒い季節がくるね
くちびるにほのおを灯し
悴む手に息を吹きかけて
陽炎は 静かにわきたつ
(書きかけの秋)
遠く引き伸ばされた栞には
おりおりの挨拶が
書き込まれていて
金木犀の
そろそろ香る夜という
ことごとく
うらはらな日々で
ちょっとした葉をむしったり
庭の花のあるがままを
押し花にしたりと
すこしかなしかった夏の
名残がさわやかに虫とともに
しんでいく
読んだ後の手紙を
丁寧に重ねてもって
雨は降らないから
傘はおよしよ
折々おりるように暮れて
ああオリオンの光るしっぽ
金木犀いろの
とりあえずの返信を
祈るように折る
(いぶき)
まつ毛の凝る季節に
切り揃えた前髪を
吹き上げることはなく
そんな風な指切りをした
博物館の書庫に
古代の生き物の骨が
静かに燃える
はしゃいだ演台の上に
秋のひかりは
錐のように差し込んで
花々のまぼろしを
次々に散らしていくのだ
花は花から生まれるもの
けれど
もう冬が来るから
先におやすみ
求めなくても
響くものはある
代わりにないて
祈りの形に
手をこすり合わせれば
かすかに ぬくい







