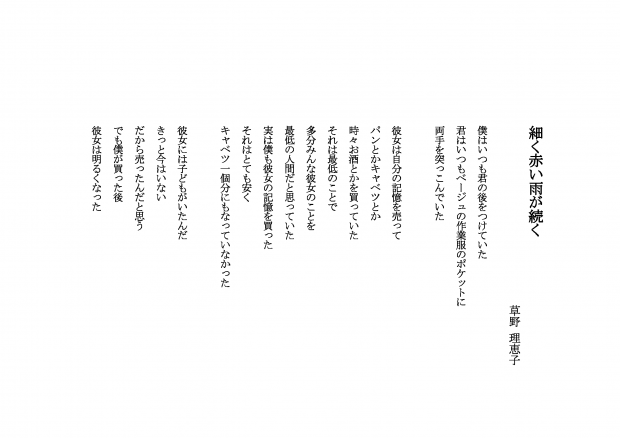
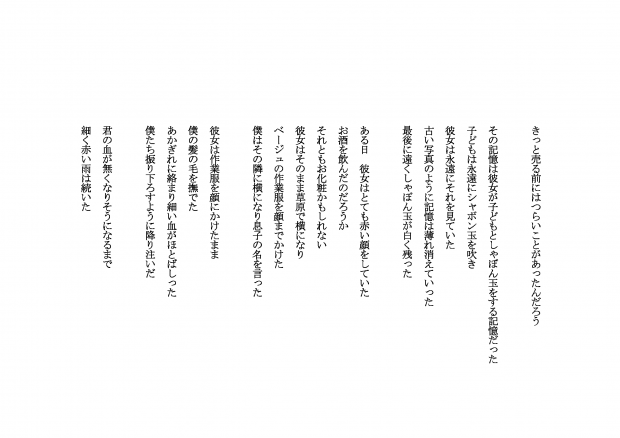
細く赤い雨が続く 草野 理恵子
僕はいつも君の後をつけていた
君はいつもベージュの作業服のポケットに
両手を突っこんでいた
彼女は自分の記憶を売って
パンとかキャベツとか
時々お酒とかを買っていた
それは最低のことで
多分みんな彼女のことを
最低の人間だと思っていた
実は僕も彼女の記憶を買った
それはとても安く
キャベツ一個分にもなっていなかった
彼女には子どもがいたんだ
きっと今はいない
だから売ったんだと思う
でも僕が買った後
彼女は明るくなった
きっと売る前にはつらいことがあったんだろう
その記憶は彼女が子どもとしゃぼん玉をする記憶だった
子どもは永遠にシャボン玉を吹き
彼女は永遠にそれを見ていた
古い写真のように記憶は薄れ消えていった
最後に遠くしゃぼん玉が白く残った
ある日 彼女はとても赤い顔をしていた
お酒を飲んだのだろうか
それともお化粧かもしれない
彼女はそのまま草原で横になり
ベージュの作業服を顔までかけた
僕はその隣に横になり息子の名を言った
彼女は作業服を顔にかけたまま
僕の髪の毛を撫でた
あかぎれに絡まり細い血がほとばしった
僕たち振り下ろすように降り注いだ
君の血が無くなりそうになるまで
細く赤い雨は続いた






