





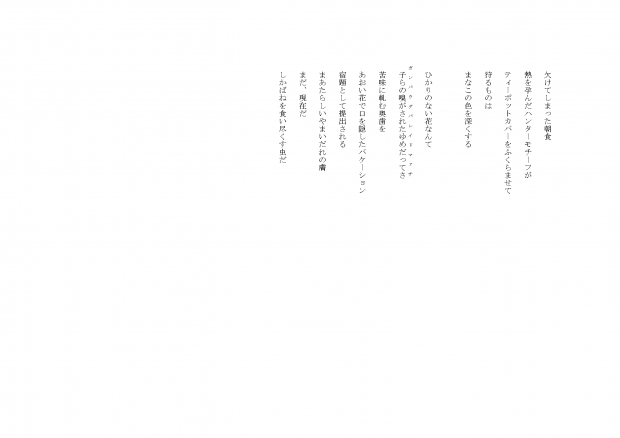
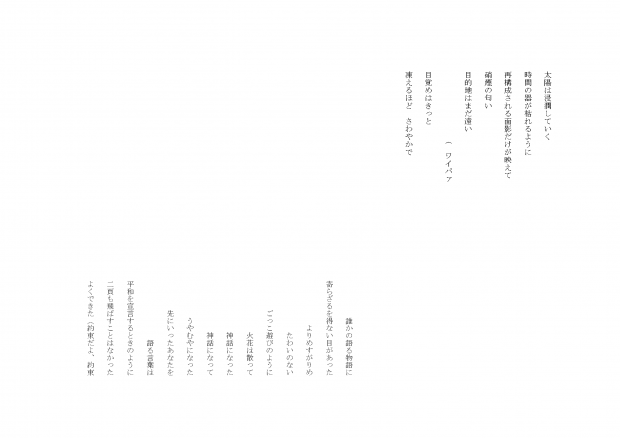
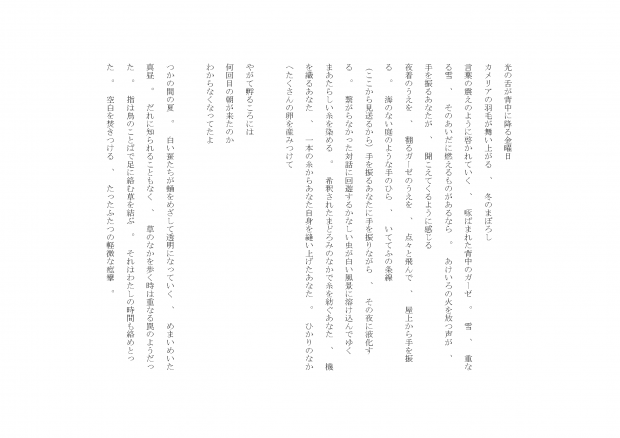


パサージュ 横山 黒鍵
蛇口からは歌を模した
水滴が落ちている
アレルギー性の称揚のなか
徐々に再定義の襞にうるおって
乗り換え客の陳腐な猥談が
すいていの澱を透過する
あなたは首を振らなかった
サイレンがなるほどに遠ざかる
帰路は果てしない戦場となる
( いくつも差し出された名詞の
( 視座に追いついた残滓が
( 拭いきれない
あなたの沈んだ献身に
いつまでも降り続ける
灰と灰と雨
( ワイパァ
はりつめたざわめき の
( 看過する椋鳥 の
( 息吹 の
( 偏ったつらら の
グラフィティ、
フレーバーテキスト
言葉にした先から
えきかしていく
色褪せた不眠症を撫ぜながら
まぶたをひとつ ふたつ痙攣させて
絶え間なくささやきを遡行する
欠けてしまった朝食
熱を孕んだハンターモチーフが
ティーポットカバーをふくらませて
狩るものは
まなこの色を深くする
ひかりのない花なんて
子らの嗅がされたゆめだってさ
苦味に軋む奥歯を
あおい花で口を隠したバケーション
宿題として提出される
まあたらしいやまいだれの膚
まだ、現在だ
しかばねを食い尽くす虫だ
太陽は浸潤していく
時間の器が枯れるように
再構成される面影だけが映えて
硝煙の匂い
目的地はまだ遠い
( ワイパァ
目覚めはきっと
凍えるほど さわやかで
誰かの語る物語に
寄らざるを得ない目があった
よりめすがりめ
たわいのない
ごっこ遊びのように
火花は散って
神話になった
神話になって
うやむやになった
先にいったあなたを
語る言葉は
平和を宣言するときのように
二頁も飛ばすことはなかった
よくできた(約束だよ、約束
光の舌が背中に降る金曜日
カメリアの羽毛が舞い上がる 、 冬のまぼろし
言葉の震えのように啓かれていく 、 啄ばまれた背中のガーゼ 。 雪 、 重な
る雪 、 そのあいだに燃えるものがあるなら 。 あけいろの火を放つ声が 、
手を振るあなたが 、 聞こえてくるように感じる
夜着のうえを 、 翻るガーゼのうえを 、 点々と飛んで 、 屋上から手を振
る 。 海のない庭のような手のひら 、 いててふの条線
(ここから見送るから)手を振るあなたに手を振りながら 、 その夜に液化す
る 。 繋がらなかった対話に回遊するかなしい虫が白い風景に溶け込んでゆく
まあたらしい糸を染める 。 希釈されたまどろみのなかで糸を紡ぐあなた 、 機
を織るあなた 、 一本の糸からあなた自身を縫い上げたあなた 。 ひかりのなか
へたくさんの卵を産みつけて
やがて孵るころには
何回目の朝が来たのか
わからなくなってたよ
つかの間の夏 。 白い蚕たちが蛹をめざして透明になっていく 、 めまいめいた
真昼 。 だれに知られることもなく 、 草のなかを歩く時は重なる罠のようだっ
た 。 指は鳥のことばで足に絡む草を結ぶ 。 それはわたしの時間も絡めとっ
た 。 空白を焚きつける 、 たったふたつの軽微な痙攣 。
約束 。 約束だよ 、 じゃんけんに負けたら 、 ずっと僕についてくるって
(ずっと僕についてくるって……) そんな約束をしたのは 、 丘の上に立つ古び
た劇場の 。 白い林檎の花が咲く季節に 、 飛び交う紋白蝶のように 、 白く
眩しく儚んで
なぎ倒された野の花の草いきれ
無貌の網目のなかへ
こぼれていったとき
窓ガラスにたどり着いたあけいろの鳥の羽 。 それはカメリア 。 手紙 、 言
葉として触れられる草の根の罠 。 赤黒い隧道の内側から響く多重奏 、 弔いに
鳴る鳥の声 。 わたしを呼ぶ 。 喉から貫通して背中へ
凍える 、 空の震えが 、 冬の針葉樹林に届くとき 、 喪屋で眠るあなたに
新しい産着を着せる
光の舌が背中のガーゼを剥がす 、 羽毛の皮膚をそよがせる冬のまぼろし 。 う
すい沈黙は 、 わたしの背中の羽毛を発情させる
、 吃音に震える細い喉を背いて
ねむる頭を
やさしく埋めてください
金曜日の影絵
手招きのうごきで
あなたを愛さずにはいられなかった 。 海のない庭に 、 あけいろの羽根を落と
して行ったあなた 。 屋上のように剥き出しだったあなた
鳥の遊ぶ日 。 二人の足に絡む草を結んだ 、 指の先 。 あなたがしかけた罠
に 、 震えのように啓かれていく 、 一枚のガーゼ 。 健全な緑 、 溢れて
いた重みその陰で交わされ舌先に遺された発音を掠れさせていく
白い林檎の花が咲く季節の 、 飛び交う消印のように
七夕の星が離れていくように
流れてしまった八日のたましい
だれかの語る
神話のように
きっと神など
信じていないくせに







