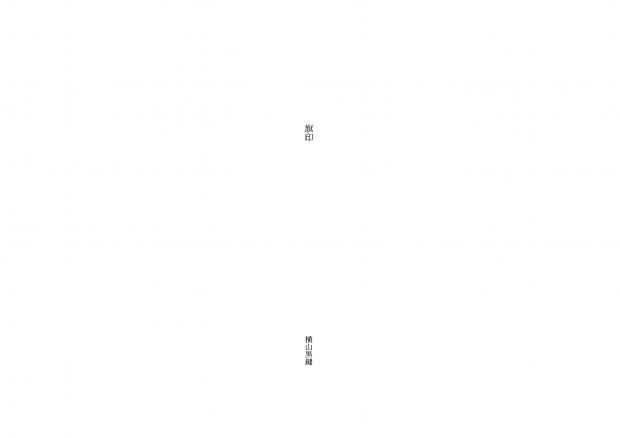


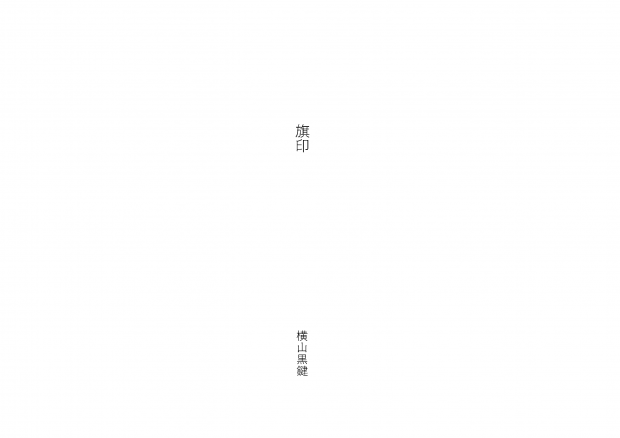
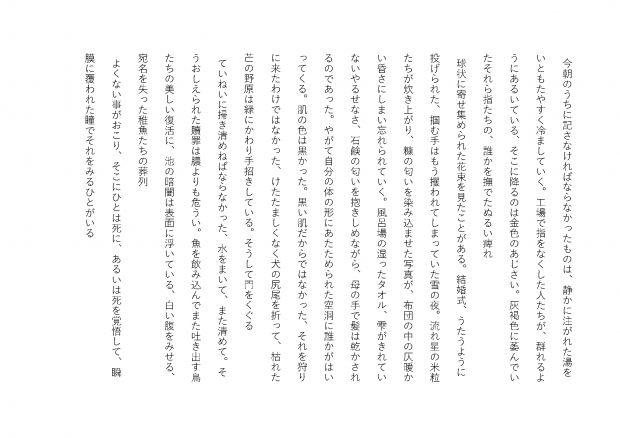
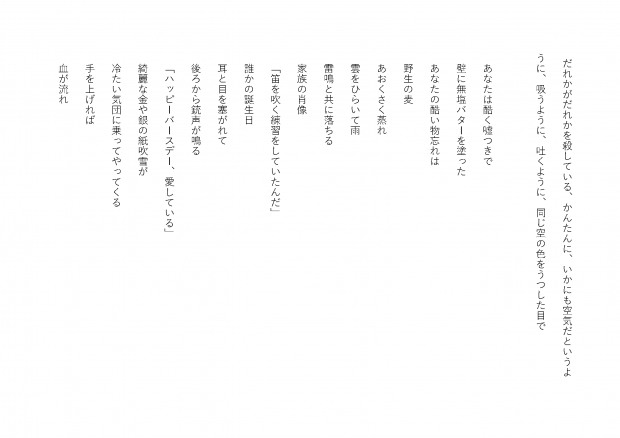
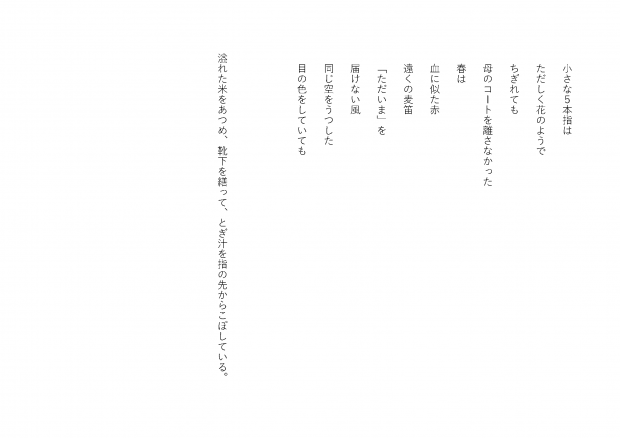
連載第6回
旗印
横山 黒鍵
今朝のうちに記さなければならなかったものは、静かに注がれた湯をいともたやすく冷ましていく。工場で指をなくした人たちが、群れるようにあるいている、そこに降るのは金色のあじさい。灰褐色に萎んでいたそれら指たちの、誰かを撫でたぬるい痺れ
球状に寄せ集められた花束を見たことがある。結婚式、うたうように投げられた、掴む手はもう攫われてしまっていた雪の夜。流れ星の米粒たちが炊き上がり、糠の匂いを染み込ませた写真が、布団の中の仄暖かい昏さにしまい忘れられていく。風呂場の湿ったタオル、雫がきれていないやるせなさ、石鹸の匂いを抱きしめながら、母の手で髪は乾かされるのであった。やがて自分の体の形にあたためられた空洞に誰かがはいってくる。肌の色は黒かった。黒い肌だからではなかった、それを狩りに来たわけではなかった、けたたましくなく犬の尻尾を折って、枯れた芒の野原は緑にかわり手招きしている。そうして門をくぐる
ていねいに掃き清めねばならなかった、水をまいて、また清めて。そうおしえられた贖罪は膿よりも危うい。魚を飲み込んでまた吐き出す鳥たちの美しい復活に、池の暗闇は表面に浮いている、白い腹をみせる、宛名を失った稚魚たちの葬列
よくない事がおこり、そこにひとは死に、あるいは死を覚悟して、瞬膜に覆われた瞳でそれをみるひとがいる
だれかがだれかを殺している、かんたんに、いかにも空気だというように、吸うように、吐くように、同じ空の色をうつした目で
あなたは酷く嘘つきで
壁に無塩バターを塗った
あなたの酷い物忘れは
野生の麦
あおくさく蒸れ
雲をひらいて雨
雷鳴と共に落ちる
家族の肖像
「笛を吹く練習をしていたんだ」
誰かの誕生日
耳と目を塞がれて
後ろから銃声が鳴る
「ハッピーバースデー、愛している」
綺麗な金や銀の紙吹雪が
冷たい気団に乗ってやってくる
手を上げれば
血が流れ
小さな5本指は
ただしく花のようで
ちぎれても
母のコートを離さなかった
春は
血に似た赤
遠くの麦笛
「ただいま」を
届けない風
同じ空をうつした
目の色をしていても
溢れた米をあつめ、靴下を繕って、とぎ汁を指の先からこぼしている。





