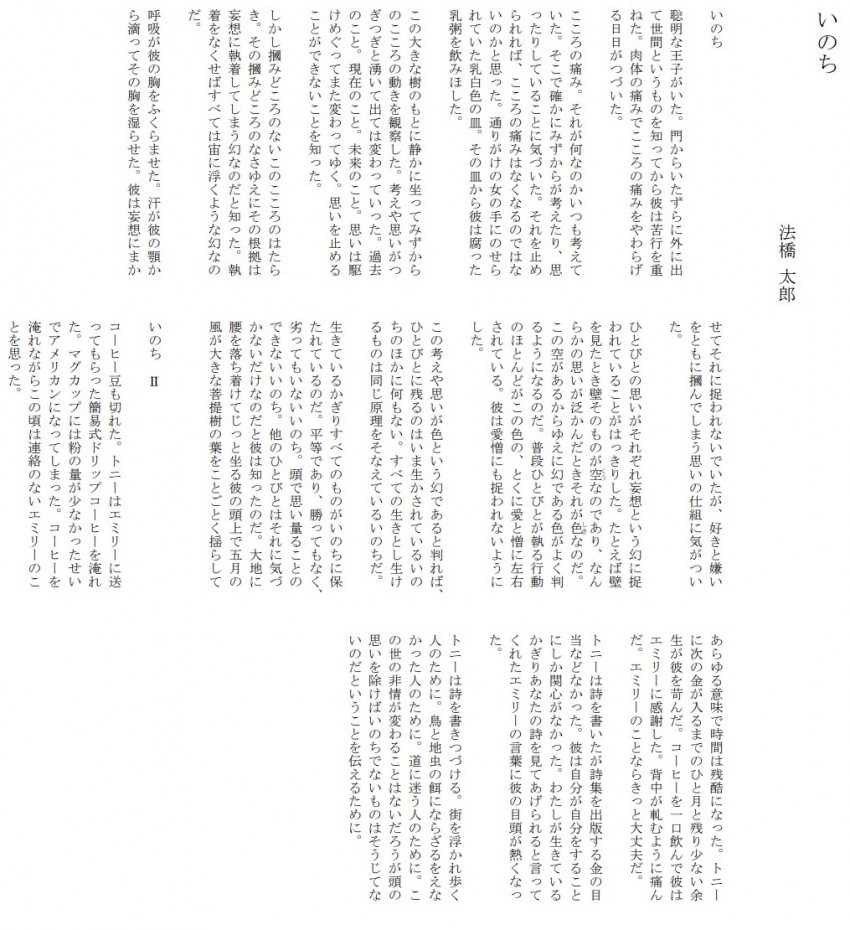いのち 法橋太郎
いのち
聡明な王子がいた。門からいたずらに外に出
て世間というものを知ってから彼は苦行を重
ねた。肉体の痛みでこころの痛みをやわらげ
る日日がつづいた。
こころの痛み。それが何なのかいつも考えて
いた。そこで確かにみずからが考えたり、思
ったりしていることに気づいた。それを止め
られれば、こころの痛みはなくなるのではな
いのかと思った。通りがけの女の手にのせら
れていた乳白色の皿。その皿から彼は腐った
乳粥を飲みほした。
この大きな樹のもとに静かに坐ってみずから
のこころの動きを観察した。考えや思いがつ
ぎつぎと湧いて出ては変わっていった。過去
のこと。現在のこと。未来のこと。思いは駆
けめぐってまた変わってゆく。思いを止める
ことができないことを知った。
しかし摑みどころのないこのこころのはたら
き。その摑みどころのなさゆえにその根拠は
妄想に執着してしまう幻なのだと知った。執
着をなくせばすべては宙に浮くような幻なの
だ。
呼吸が彼の胸をふくらませた。汗が彼の顎か
ら滴ってその胸を湿らせた。彼は妄想にまか
せてそれに捉われないでいたが、好きと嫌い
をともに摑んでしまう思いの仕組に気がつい
た。
ひとびとの思いがそれぞれ妄想という幻に捉
われていることがはっきりした。たとえば壁
を見たとき壁そのものが空(くう)なのであり、なん
らかの思いが泛かんだときそれが色(しき)なのだ。
この空があるからゆえに幻である色がよく判
るようになるのだ。普段ひとびとが執る行動
のほとんどがこの色の、とくに愛と憎に左右
されている。彼は愛憎にも捉われないように
した。
この考えや思いが色という幻であると判れば、
ひとびとに残るのはいま生かされているいの
ちのほかに何もない。すべての生きとし生け
るものは同じ原理をそなえているいのちだ。
生きているかぎりすべてのものがいのちに保
たれているのだ。平等であり、勝ってもなく、
劣ってもいないいのち。頭で思い量ることの
できないいのち。他のひとびとはそれに気づ
かないだけなのだと彼は知ったのだ。大地に
腰を落ち着けてじっと坐る彼の頭上で五月の
風が大きな菩提樹の葉をことごとく揺らして
いのち Ⅱ
コーヒー豆も切れた。トニーはエミリーに送
ってもらった簡易式ドリップコーヒーを淹れ
た。マグカップには粉の量が少なかったせい
でアメリカンになってしまった。コーヒーを
淹れながらこの頃は連絡のないエミリーのこ
とを思った。
あらゆる意味で時間は残酷になった。トニー
に次の金が入るまでのひと月と残り少ない余
生が彼を苛んだ。コーヒーを一口飲んで彼は
エミリーに感謝した。背中が軋むように痛ん
だ。エミリーのことならきっと大丈夫だ。
トニーは詩を書いたが詩集を出版する金の目
当などなかった。彼は自分が自分をすること
にしか関心がなかった。わたしが生きている
かぎりあなたの詩を見てあげられると言って
くれたエミリーの言葉に彼の目頭が熱くなっ
た。
トニーは詩を書きつづける。街を浮かれ歩く
人のために。鳥と地虫の餌にならざるをえな
かった人のために。道に迷う人のために。こ
の世の非情が変わることはないだろうが頭の
思いを除けばいのちでないものはそうじてな
いのだということを伝えるために。