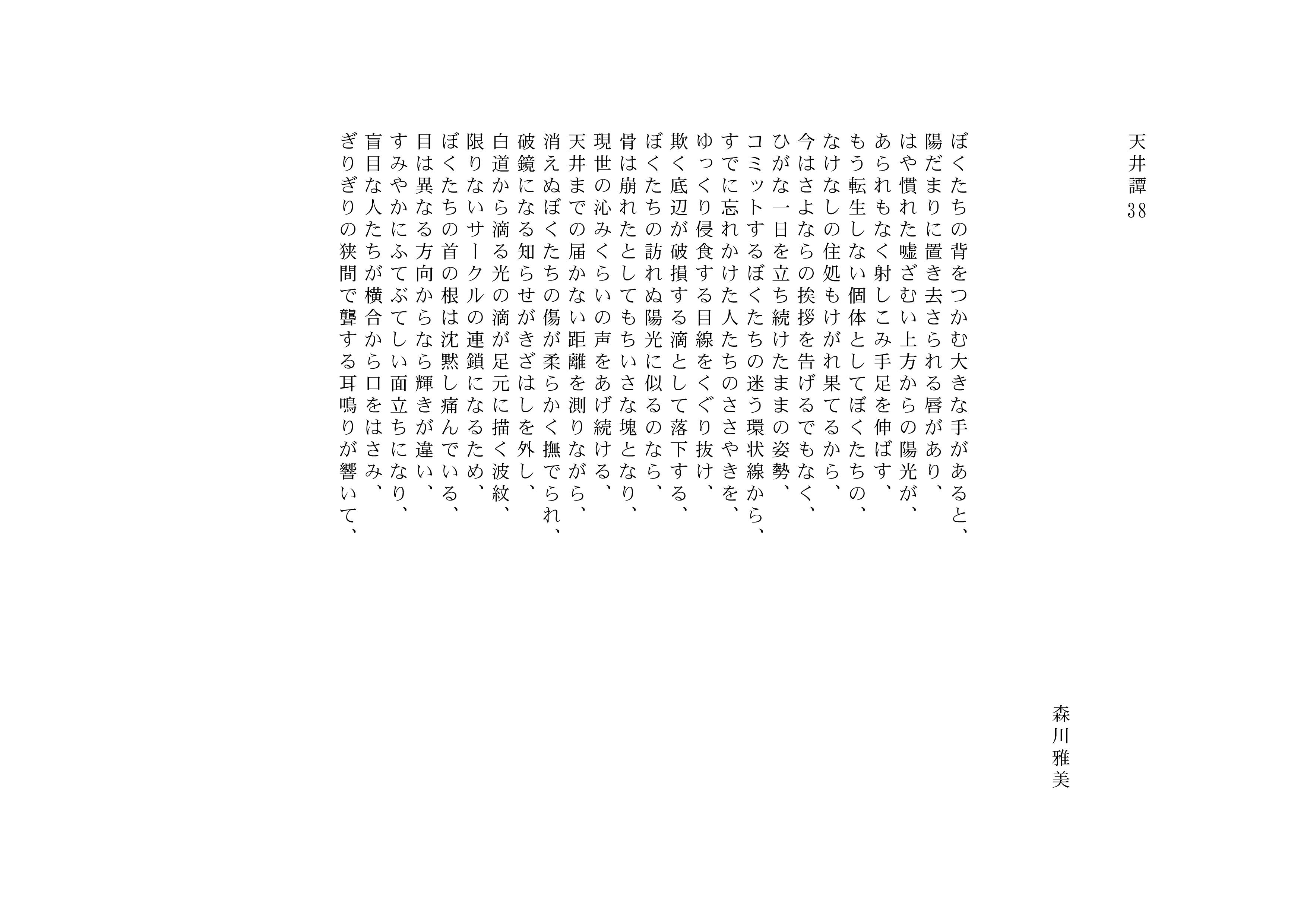天井譚38 森川雅美
ぼくたちの背をつかむ大きな手があると、
陽だまりに置き去さられる唇があり、
はや慣れた嘘ざむい上方からの陽光が、
あられもなく射しこみ手足を伸ばす、
もう転生しない個体としてぼくたちの、
なけなしの住処もけがれ果てるから、
今はさよならの挨拶を告げるでもなく、
ひがな一日を立ち続けたままの姿勢、
コミットするぼくたちの迷う環状線から、
すでに忘れかけた人たちのささやきを、
ゆっくり侵食する目線をくぐり抜け、
欺く底辺が破損する滴として落下する、
ぼくたちの訪れぬ陽光に似るのなら、
骨は崩れたとしてもちいさな塊となり、
現世の沁みくらいの声をあげ続ける、
天井までの届かない距離を測りながら、
消えぬぼくたちの傷が柔らかく撫でられ、
破鏡になる知らせがきざはしを外し、
白道から滴る光の滴が足元に描く波紋、
限りないサークルの連鎖になるため、
ぼくたちの首の根は沈黙し痛んでいる、
目は異なる方向からなら輝きが違い、
すみやかにふてぶてしい面立ちになり、
盲目な人たちが横合から口をはさみ、
ぎりぎりの狭間で聾する耳鳴りが響いて、