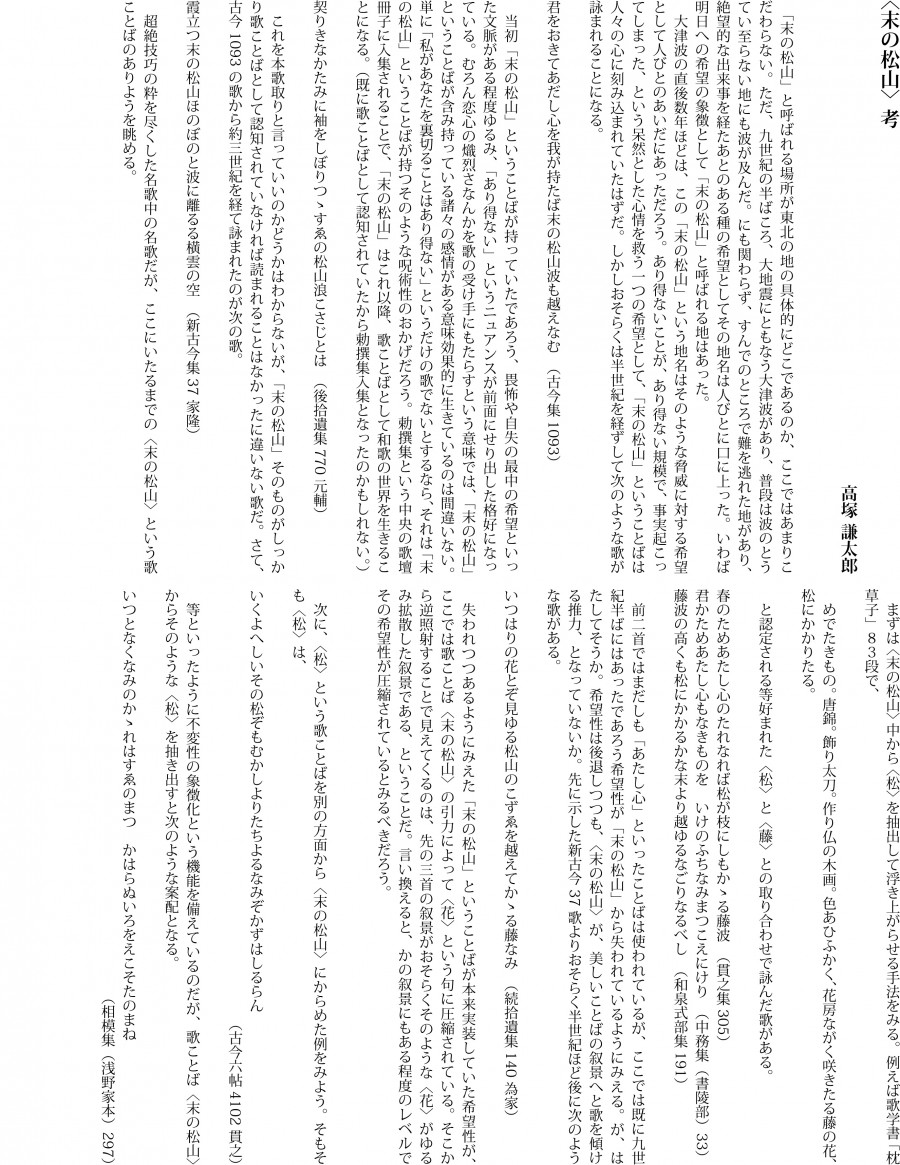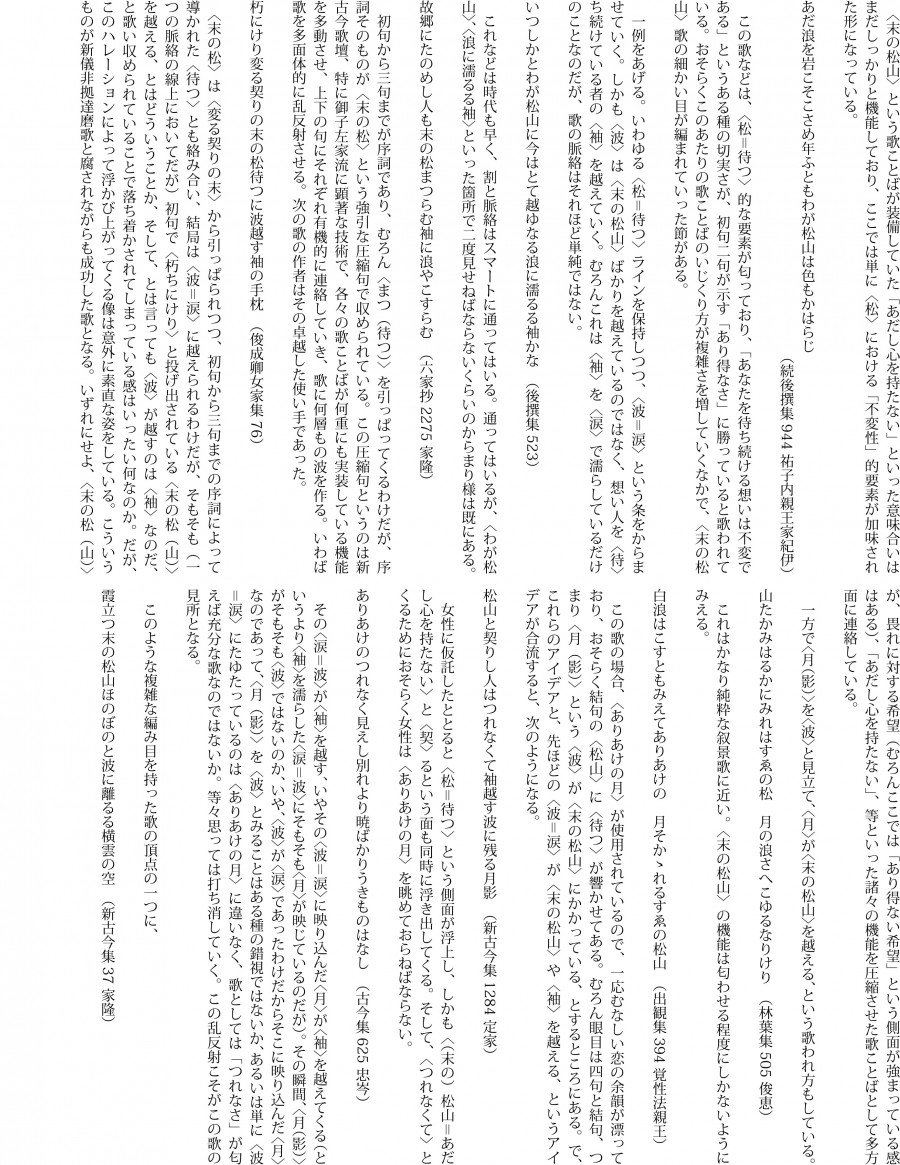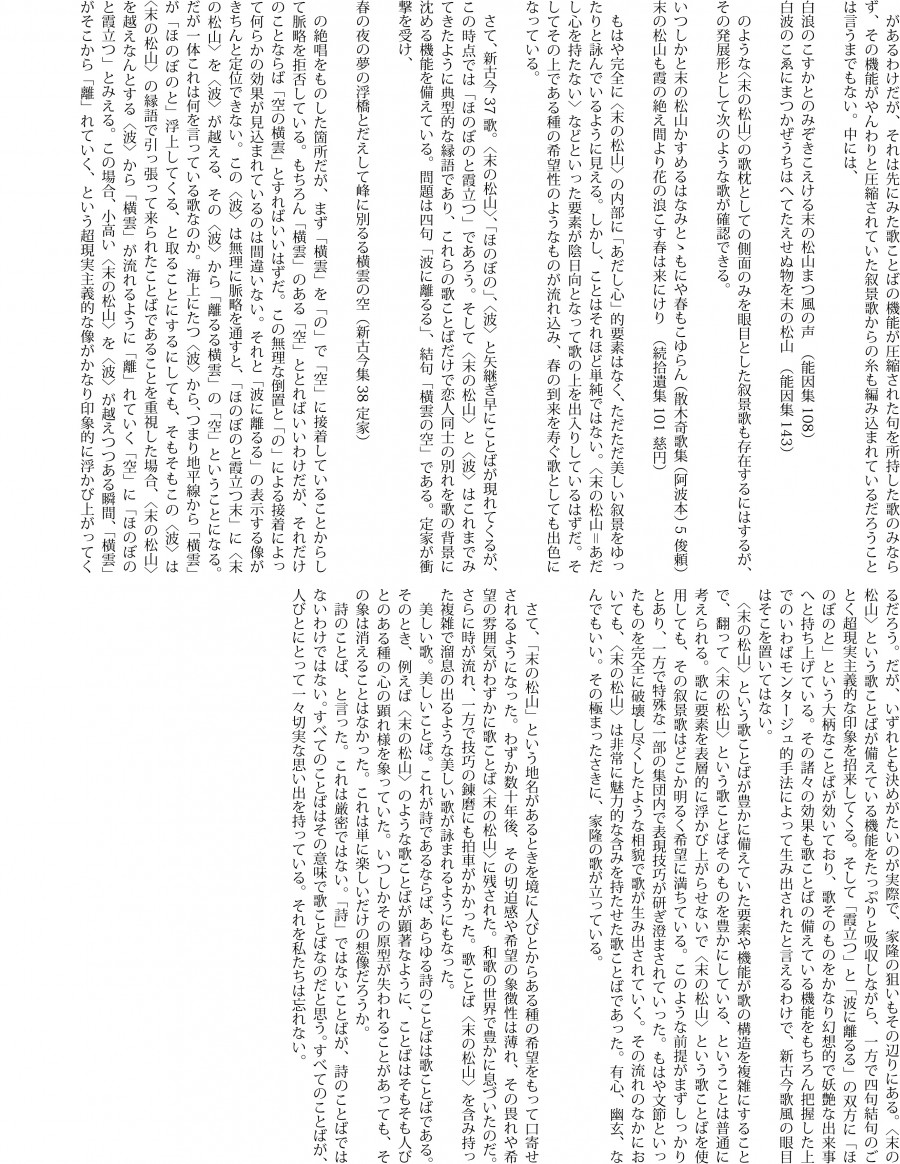〈末の松山〉考 高塚 謙太郎
「末の松山」と呼ばれる場所が東北の地の具体的にどこであるのか、ここではあまりこだわらない。ただ、九世紀の半ばころ、大地震にともなう大津波があり、普段は波のとうてい至らない地にも波が及んだ。にも関わらず、すんでのところで難を逃れた地があり、絶望的な出来事を経たあとのある種の希望としてその地名は人びとに口に上った。いわば明日への希望の象徴として「末の松山」と呼ばれる地はあった。
大津波の直後数年ほどは、この「末の松山」という地名はそのような脅威に対する希望として人びとのあいだにあっただろう。あり得ないことが、あり得ない規模で、事実起こってしまった、という呆然とした心情を救う一つの希望として、「末の松山」ということばは人々の心に刻み込まれていたはずだ。しかしおそらくは半世紀を経ずして次のような歌が詠まれることになる。
君をおきてあだし心を我が持たば末の松山波も越えなむ (古今集1093)
当初「末の松山」ということばが持っていたであろう、畏怖や自失の最中の希望といった文脈がある程度ゆるみ、「あり得ない」というニュアンスが前面にせり出した格好になっている。むろん恋心の熾烈さなんかを歌の受け手にもたらすという意味では、「末の松山」ということばが含み持っている諸々の感情がある意味効果的に生きているのは間違いない。単に「私があなたを裏切ることはあり得ない」というだけの歌でないとするなら、それは「末の松山」ということばが持つそのような呪術性のおかげだろう。勅撰集という中央の歌壇冊子に入集されることで、「末の松山」はこれ以降、歌ことばとして和歌の世界を生きることになる。(既に歌ことばとして認知されていたから勅撰集入集となったのかもしれない。)
契りきなかたみに袖をしぼりつゝすゑの松山浪こさじとは (後拾遺集770 元輔)
これを本歌取りと言っていいのかどうかはわからないが、「末の松山」そのものがしっかり歌ことばとして認知されていなければ読まれることはなかったに違いない歌だ。さて、古今1093の歌から約三世紀を経て詠まれたのが次の歌。
霞立つ末の松山ほのぼのと波に離るる横雲の空 (新古今集37 家隆)
超絶技巧の粋を尽くした名歌中の名歌だが、ここにいたるまでの〈末の松山〉という歌ことばのありようを眺める。
まずは〈末の松山〉中から〈松〉を抽出して浮き上がらせる手法をみる。例えば歌学書「枕草子」83段で、
めでたきもの。唐錦。飾り太刀。作り仏の木画。色あひふかく、花房ながく咲きたる藤の花、松にかかりたる。
と認定される等好まれた〈松〉と〈藤〉との取り合わせで詠んだ歌がある。
春のためあたし心のたれなれば松が枝にしもかゝる藤波 (貫之集305)
君かためあたし心もなきものを いけのふちなみまつこえにけり (中務集(書陵部)33)
藤波の高くも松にかかるかな末より越ゆるなごりなるべし (和泉式部集191)
前二首ではまだしも「あたし心」といったことばは使われているが、ここでは既に九世紀半ばにはあったであろう希望性が「末の松山」から失われているようにみえる。が、はたしてそうか。希望性は後退しつつも、〈末の松山〉が、美しいことばの叙景へと歌を傾ける推力、となっていないか。先に示した新古今37歌よりおそらく半世紀ほど後に次のような歌がある。
いつはりの花とぞ見ゆる松山のこずゑを越えてかゝる藤なみ (続拾遺集140 為家)
失われつつあるようにみえた「末の松山」ということばが本来実装していた希望性が、ここでは歌ことば〈末の松山〉の引力によって〈花〉という句に圧縮されている。そこから逆照射することで見えてくるのは、先の三首の叙景がおそらくそのような〈花〉がゆるみ拡散した叙景である、ということだ。言い換えると、かの叙景にもある程度のレベルでその希望性が圧縮されているとみるべきだろう。
次に、〈松〉という歌ことばを別の方面から〈末の松山〉にからめた例をみよう。そもそも〈松〉は、
いくよへしいその松ぞもむかしよりたちよるなみぞかずはしるらん
(古今六帖4102 貫之)
等といったように不変性の象徴化という機能を備えているのだが、歌ことば〈末の松山〉からそのような〈松〉を抽き出すと次のような案配となる。
いつとなくなみのかゝれはすゑのまつ かはらぬいろをえこそたのまね
(相模集(浅野家本)297)
〈末の松山〉という歌ことばが装備していた「あだし心を持たない」といった意味合いはまだしっかりと機能しており、ここでは単に〈松〉における「不変性」的要素が加味された形になっている。
あだ浪を岩こそこさめ年ふともわが松山は色もかはらじ
(続後撰集944 祐子内親王家紀伊)
この歌などは、〈松=待つ〉的な要素が匂っており、「あなたを待ち続ける想いは不変である」というある種の切実さが、初句二句が示す「あり得なさ」に勝っていると歌われている。おそらくこのあたりの歌ことばのいじくり方が複雑さを増していくなかで、〈末の松山〉歌の細かい目が編まれていった節がある。
一例をあげる。いわゆる〈松=待つ〉ラインを保持しつつ、〈波=涙〉という条をからませていく。しかも〈波〉は〈末の松山〉ばかりを越えているのではなく、想い人を〈待〉ち続けている者の〈袖〉を越えていく。むろんこれは〈袖〉を〈涙〉で濡らしているだけのことなのだが、歌の脈絡はそれほど単純ではない。
いつしかとわが松山に今はとて越ゆなる浪に濡るる袖かな (後撰集523)
これなどは時代も早く、割と脈絡はスマートに通ってはいる。通ってはいるが、〈わが松山〉、〈浪に濡るる袖〉といった箇所で二度見せねばならないくらいのからまり様は既にある。
故郷にたのめし人も末の松まつらむ袖に浪やこすらむ (六家抄2275 家隆)
初句から三句までが序詞であり、むろん〈まつ(待つ)〉を引っぱってくるわけだが、序詞そのものが〈末の松〉という強引な圧縮句で収められている。この圧縮句というのは新古今歌壇、特に御子左家流に顕著な技術で、各々の歌ことばが何重にも実装している機能を多動させ、上下の句にそれぞれ有機的に連絡していき、歌に何層もの波を作る。いわば歌を多面体的に乱反射させる。次の歌の作者はその卓越した使い手であった。
朽にけり変る契りの末の松待つに波越す袖の手枕 (俊成卿女家集76)
〈末の松〉は〈変る契りの末〉から引っぱられつつ、初句から三句までの序詞によって導かれた〈待つ〉とも絡み合い、結局は〈波=涙〉に越えられるわけだが、そもそも(一つの脈絡の線上においてだが)初句で〈朽ちにけり〉と投げ出されている〈末の松(山)〉を越える、とはどういうことか、そして、とは言っても〈波〉が越すのは〈袖〉なのだ、と歌い収められていることで落ち着かされてしまっている感はいったい何なのか。だが、このハレーションによって浮かび上がってくる像は意外に素直な姿をしている。こういうものが新儀非拠達磨歌と腐されながらも成功した歌となる。いずれにせよ、〈末の松(山)〉が、畏れに対する希望(むろんここでは「あり得ない希望」という側面が強まっている感はある)、「あだし心を持たない」、等といった諸々の機能を圧縮させた歌ことばとして多方面に連絡している。
一方で〈月(影)〉を〈波〉と見立て、〈月〉が〈末の松山〉を越える、という歌われ方もしている。
山たかみはるかにみれはすゑの松 月の浪さへこゆるなりけり (林葉集505 俊恵)
これはかなり純粋な叙景歌に近い。〈末の松山〉の機能は匂わせる程度にしかないようにみえる。
白浪はこすともみえてありあけの 月そかゝれるすゑの松山 (出観集394 覚性法親王)
この歌の場合、〈ありあけの月〉が使用されているので、一応むなしい恋の余韻が漂っており、おそらく結句の〈松山〉に〈待つ〉が響かせてある。むろん眼目は四句と結句、つまり〈月(影)〉という〈波〉が〈末の松山〉にかかっている、とするところにある。で、これらのアイデアと、先ほどの〈波=涙〉が〈末の松山〉や〈袖〉を越える、というアイデアが合流すると、次のようになる。
松山と契りし人はつれなくて袖越す波に残る月影 (新古今集1284 定家)
女性に仮託したととると〈松=待つ〉という側面が浮上し、しかも〈(末の)松山=あだし心を持たない〉と〈契〉るという面も同時に浮き出してくる。そして、〈つれなくて〉とくるためにおそらく女性は〈ありあけの月〉を眺めておらねばならない。
ありあけのつれなく見えし別れより暁ばかりうきものはなし (古今集625 忠岑)
その〈涙=波〉が〈袖〉を越す、いやその〈波=涙〉に映り込んだ〈月〉が〈袖〉を越えてくる(というより〈袖〉を濡らした〈涙=波〉にそもそも〈月〉が映じているのだが)。その瞬間、〈月(影)〉がそもそも〈波〉ではないのか、いや、〈波〉が〈涙〉であったわけだからそこに映り込んだ〈月〉なのであって、〈月(影)〉を〈波〉とみることはある種の錯視ではないか、あるいは単に〈波=涙〉にたゆたっているのは〈ありあけの月〉に違いなく、歌としては「つれなさ」が匂えば充分な歌なのではないか。等々思っては打ち消していく。この乱反射こそがこの歌の見所となる。
このような複雑な編み目を持った歌の頂点の一つに、
霞立つ末の松山ほのぼのと波に離るる横雲の空 (新古今集37 家隆)
があるわけだが、それは先にみた歌ことばの機能が圧縮された句を所持した歌のみならず、その機能がやんわりと圧縮されていた叙景歌からの糸も編み込まれているだろうことは言うまでもない。中には、
白浪のこすかとのみぞきこえける末の松山まつ風の声 (能因集108)
白波のこゑにまつかぜうちはへてたえせぬ物を末の松山 (能因集143)
のような〈末の松山〉の歌枕としての側面のみを眼目とした叙景歌も存在するにはするが、その発展形として次のような歌が確認できる。
いつしかと末の松山かすめるはなみとゝもにや春もこゆらん
(散木奇歌集(阿波本)5 俊頼)
末の松山も霞の絶え間より花の浪こす春は来にけり (続拾遺集101 慈円)
もはや完全に〈末の松山〉の内部に「あだし心」的要素はなく、ただただ美しい叙景をゆったりと詠んでいるように見える。しかし、ことはそれほど単純ではない。〈末の松山=あだし心を持たない〉などといった要素が陰日向となって歌の上を出入りしているはずだ。そしてその上である種の希望性のようなものが流れ込み、春の到来を寿ぐ歌としても出色になっている。
さて、新古今37歌。〈末の松山〉、「ほのぼの」、〈波〉と矢継ぎ早にことばが現れてくるが、この時点では「ほのぼのと霞立つ」であろう。そして〈末の松山〉と〈波〉はこれまでみてきたように典型的な縁語であり、これらの歌ことばだけで恋人同士の別れを歌の背景に沈める機能を備えている。問題は四句「波に離るる」、結句「横雲の空」である。定家が衝撃を受け、
春の夜の夢の浮橋とだえして峰に別るる横雲の空(新古今集38 定家)
の絶唱をものした箇所だが、まず「横雲」を「の」で「空」に接着していることからして脈略を拒否している。もちろん「横雲」のある「空」ととればいいわけだが、それだけのことならば「空の横雲」とすればいいはずだ。この無理な倒置と「の」による接着によって何らかの効果が見込まれているのは間違いない。それと「波に離るる」の表示する像がきちんと定位できない。この〈波〉は無理に脈略を通すと、「ほのぼのと霞立つ末」に〈末の松山〉を〈波〉が越える、その〈波〉から「離るる横雲」の「空」ということになる。だが一体これは何を言っている歌なのか。海上にたつ〈波〉から、つまり地平線から「横雲」が「ほのぼのと」浮上してくる、と取ることにするにしても、そもそもこの〈波〉は〈末の松山〉の縁語で引っ張って来られたことばであることを重視した場合、〈末の松山〉を越えなんとする〈波〉から「横雲」が流れるように「離」れていく「空」に「ほのぼのと霞立つ」とみえる。この場合、小高い〈末の松山〉を〈波〉が越えつつある瞬間、「横雲」がそこから「離」れていく、という超現実主義的な像がかなり印象的に浮かび上がってくるだろう。だが、いずれとも決めがたいのが実際で、家隆の狙いもその辺りにある。〈末の松山〉という歌ことばが備えている機能をたっぷりと吸収しながら、一方で四句結句のごとく超現実主義的な印象を招来してくる。そして「霞立つ」と「波に離るる」の双方に「ほのぼのと」という大柄なことばが効いており、歌そのものをかなり幻想的で妖艶な出来事へと持ち上げている。その諸々の効果も歌ことばの備えている機能をもちろん把握した上でのいわばモンタージュ的手法によって生み出されたと言えるわけで、新古今歌風の眼目はそこを置いてはない。
〈末の松山〉という歌ことばが豊かに備えていた要素や機能が歌の構造を複雑にすることで、翻って〈末の松山〉という歌ことばそのものを豊かにしている、ということは普通に考えられる。歌に要素を表層的に浮かび上がらせないで〈末の松山〉という歌ことばを使用しても、その叙景歌はどこか明るく希望に満ちている。このような前提がまずしっかりとあり、一方で特殊な一部の集団内で表現技巧が研ぎ澄まされていった。もはや文節といったものを完全に破壊し尽くしたような相貌で歌が生み出されていく。その流れのなかにおいても、〈末の松山〉は非常に魅力的な含みを持たせた歌ことばであった。有心、幽玄、なんでもいい。その極まったさきに、家隆の歌が立っている。
さて、「末の松山」という地名があるときを境に人びとからある種の希望をもって口寄せされるようになった。わずか数十年後、その切迫感や希望の象徴性は薄れ、その畏れや希望の雰囲気がわずかに歌ことば〈末の松山〉に残された。和歌の世界で豊かに息づいたのだ。さらに時が流れ、一方で技巧の錬磨にも拍車がかかった。歌ことば〈末の松山〉を含み持った複雑で溜息の出るような美しい歌が詠まれるようにもなった。
美しい歌。美しいことば。これが詩であるならば、あらゆる詩のことばは歌ことばである。そのとき、例えば〈末の松山〉のような歌ことばが顕著なように、ことばはそもそも人びとのある種の心の顕れ様を象っていた。いつしかその原型が失われることがあっても、その象は消えることはなかった。これは単に楽しいだけの想像だろうか。
詩のことば、と言った。これは厳密ではない。「詩」ではないことばが、詩のことばではないわけではない。すべてのことばはその意味で歌ことばなのだと思う。すべてのことばが、人びとにとって一々切実な思い出を持っている。それを私たちは忘れない。