
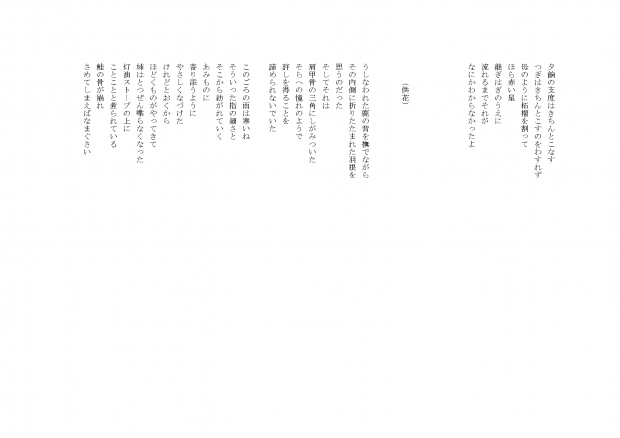
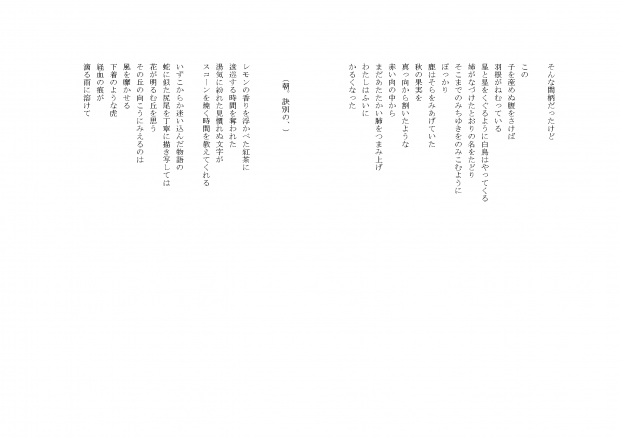
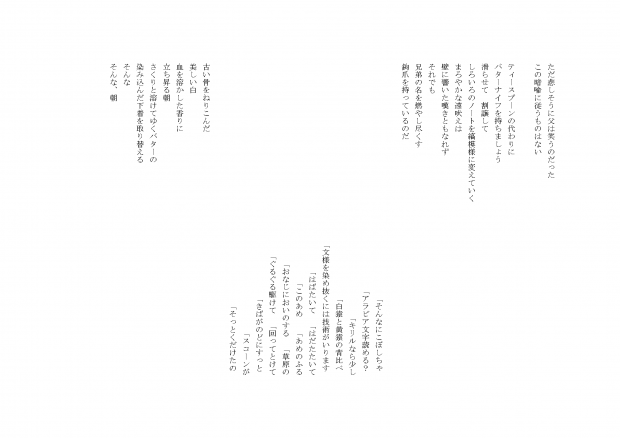
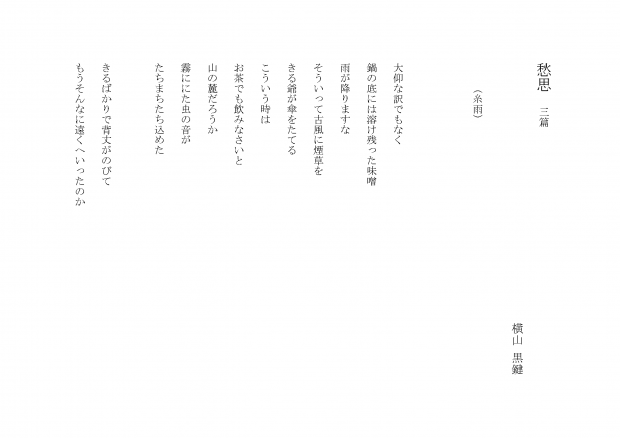
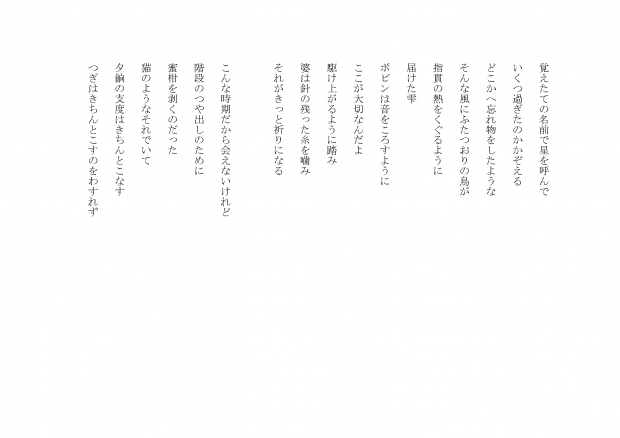
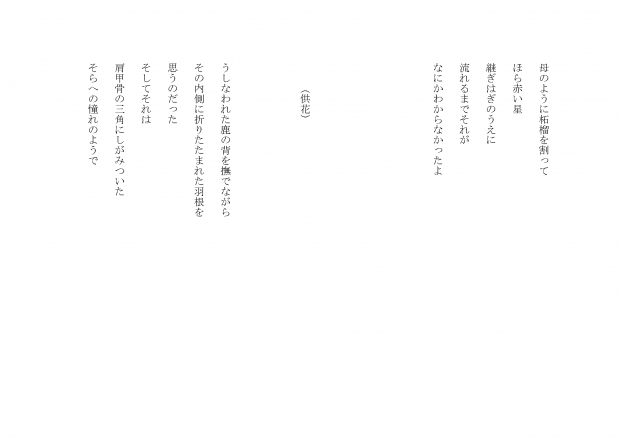
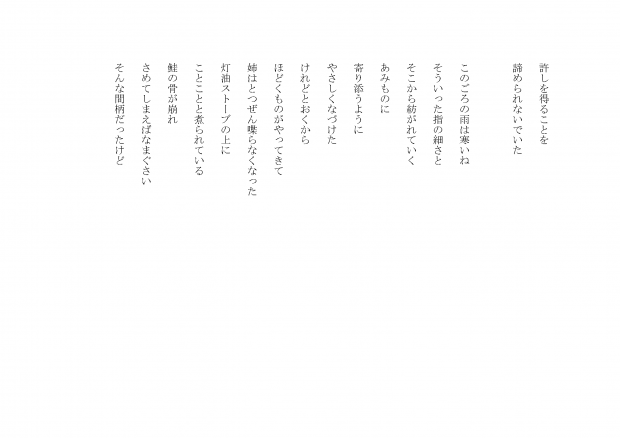
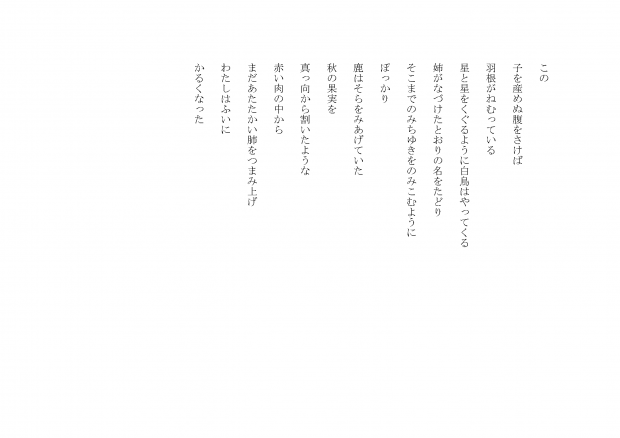
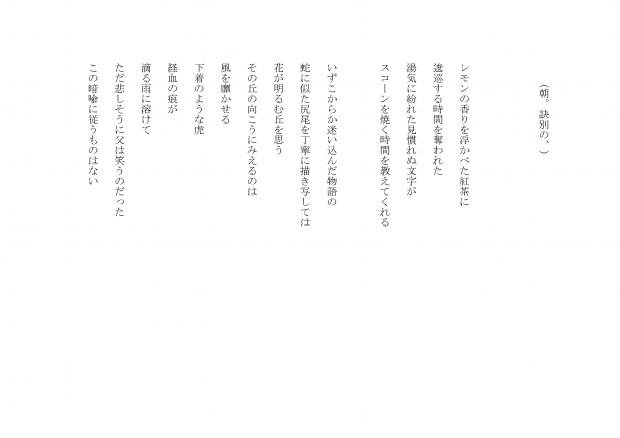
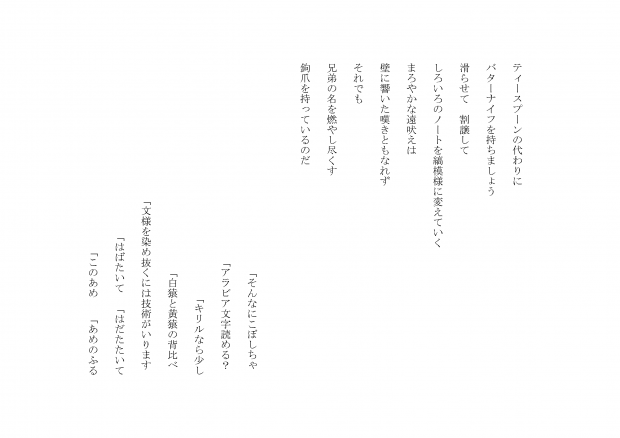
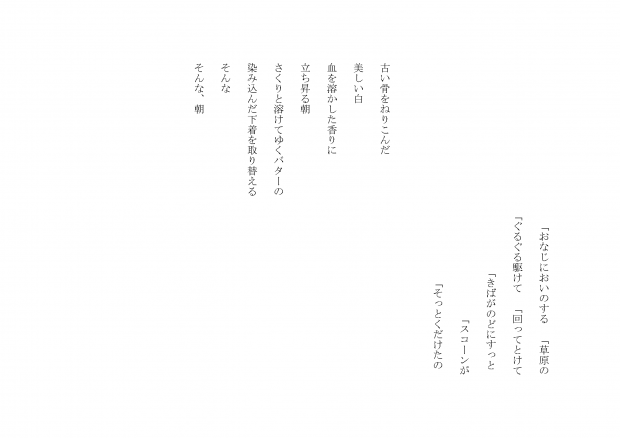
愁思 三篇
横山黒鍵
(糸雨)
大仰な訳でもなく
鍋の底には溶け残った味噌
雨が降りますな
そういって古風に煙草を
きる爺が傘をたてる
こういう時は
お茶でも飲みなさいと
山の麓だろうか
霧ににた虫の音が
たちまちたち込めた
きるばかりで背丈がのびて
もうそんなに遠くへいったのか
覚えたての名前で星を呼んで
いくつ過ぎたのかかぞえる
どこかへ忘れ物をしたような
そんな風にふたつおりの鳥が
指貫の熱をくぐるように
届けた雫
ボビンは音をころすように
ここが大切なんだよ
駆け上がるように踏み
婆は針の残った糸を噛み
それがきっと祈りになる
こんな時期だから会えないけれど
階段のつや出しのために
蜜柑を剥くのだった
猫のようなそれでいて
夕餉の支度はきちんとこなす
つぎはきちんとこすのをわすれず
母のように柘榴を割って
ほら赤い星
継ぎはぎのうえに
流れるまでそれが
なにかわからなかったよ
(供花)
うしなわれた鹿の背を撫でながら
その内側に折りたたまれた羽根を
思うのだった
そしてそれは
肩甲骨の三角にしがみついた
そらへの憧れのようで
許しを得ることを
諦められないでいた
このごろの雨は寒いね
そういった指の細さと
そこから紡がれていく
あみものに
寄り添うように
やさしくなづけた
けれどとおくから
ほどくものがやってきて
姉はとつぜん喋らなくなった
灯油ストーブの上に
ことことと煮られている
鮭の骨が崩れ
さめてしまえばなまぐさい
そんな間柄だったけど
この
子を産めぬ腹をさけば
羽根がねむっている
星と星をくぐるように白鳥はやってくる
姉がなづけたとおりの名をたどり
そこまでのみちゆきをのみこむように
ぽっかり
鹿はそらをみあげていた
秋の果実を
真っ向から割いたような
赤い肉の中から
まだあたたかい肺をつまみ上げ
わたしはふいに
かるくなった
(朝。訣別の、)
レモンの香りを浮かべた紅茶に
逡巡する時間を奪われた
湯気に紛れた見慣れぬ文字が
スコーンを焼く時間を教えてくれる
いずこからか迷い込んだ物語の
蛇に似た尻尾を丁寧に描き写しては
花が明るむ丘を思う
その丘の向こうにみえるのは
風を靡かせる
下着のような虎
経血の痕が
滴る雨に溶けて
ただ悲しそうに父は笑うのだった
この暗喩に従うものはない
ティースプーンの代わりに
バターナイフを持ちましょう
滑らせて 割譲して
しろいろのノートを縞模様に変えていく
まろやかな遠吠えは
壁に響いた嘆きともなれず
それでも
兄弟の名を燃やし尽くす
鉤爪を持っているのだ
「そんなにこぼしちゃ
「アラビア文字読める?
「キリルなら少し
「白猿と黄猿の背比べ
「文様を染め抜くには技術がいります
「はばたいて 「はだたたいて
「このあめ 「あめのふる
「おなじにおいのする 「草原の
「ぐるぐる駆けて 「回ってとけて
「きばがのどにすっと
「スコーンが
「そっとくだけたの
古い骨をねりこんだ
美しい白
血を溶かした香りに
立ち昇る朝
さくりと溶けてゆくバターの
染み込んだ下着を取り替える
そんな
そんな、朝








