短歌をつくる人間にとって、俳句は近しい親戚のようなものだ。その半面、「七・七」という長いしっぽを抱えた自らの抒情が、時に重たく、時に湿っぽく感じられ、基本的に「私性」を盛り込むことの少ない俳句の潔さがまぶしくてならなかったりする。だから、『俳コレ』を読んで最も驚いたのは、魅力的な「私性」をたくさん発見したことである。
ヒヤシンスしあわせがどうしても要る 福田若之
僕のほか腐るものなく西日の部屋
からっぽのプールを洗う満たすために
これはほとんど、短歌と地続きの抒情ではないか――。溌剌としたパワーと達者な詠みぶりとが併存しているが、何よりも作者の姿がくっきりと浮かび上がっていることに惹かれる。どこか短歌的で、「ヒヤシンス」や「西日の部屋」は、何だか寺山修司や加藤治郎を思わせる。三句目には、キャメロンの『ママがプールを洗う日』を思い出してしまった。
会社やめたしやめたしやめたし落花飛花 松本てふこ
地下鉄によく乗る日なり一の酉
菜の花を見てきし躰洗ひけり
奔放さが魅力の作者である。何か投げ出したような体当たりの句風が小気味よい。町の風景を活写した作品にも個人的な手触りが感じられるのは、この人独自の身体感覚で捉えているからではないか。
二十歳つよき凍星のみ愛す 矢口晃
泣けばいいのに落葉など焚いてゐる
まちがへてほたるぶくろの中にをり
この人の句にも、「わたくし」が濃く漂う。自らを見つめる視線が、ひりひりしていて切ない。不安と孤独感を抱く繊細な青年像が浮かんでくるが、句柄は決して小さくない。
これらの作者たちは、いずれも80-90年代の生まれである。俳句に関してはまるで門外漢の私であるが、こうした若い人たちの伸びやかさは新鮮に感じられる。
けれども、若い世代がみな「私性」を出しているかと言えば、そうではないのも当然だ。
絵も文字も下手な看板海の家 小野あらた
黒飴の傷舐めてをる夜長かな
初雪やリボン逃げ出すかたちして 野口る理
夕立やとほくのビルはこはれそう
集まつてだんだん蟻の力濃し 南十二国
春の草月は地球をはなれぬよ
1993年生まれの小野は、本書に登場する最も若い作家である。モノにこだわった丹念な描写は、一歩手前で「私性」を巧みに避けているようだ。細密な絵を思わせるこまやかな表現の下に、太々とした精神が覗いて見える。
野口は1986年生まれ。繊細さの中に、都市生活者の醒めたまなざしと、子どものような真っすぐな視線がほどよく混ざり合っている。少女性を湛えた詠みぶりが印象的だが、「しづかなるひとのうばへる歌留多かな」のような艶っぽい句もあって、どきどきさせる。「私性」という観点からすると、彼女の作品も従来のオーソドクスな路線といえようか。
南十二国は1980年生まれ。独特の叙景句を作る人だ。人間や地球を俯瞰した視点が、鋭く物事の本質を突いており、爽快な読後感が得られる。
本書は20代から70代まで幅広い作家を紹介している。20人の作品100句とかなり読み応えのある構成にしており、1人ひとりの世界にたっぷり浸ることができる。登場する最年長の作家は、1934年生まれの渋川京子である。しかし、ベテランであることは手堅い作風を意味しない。
ハンカチを正しくたたみ出奔す 渋川京子
マフラーの白美し貞女とはおそろし
良夜かな独りになりに夫が逝く
激しいものを秘めた心が切々と伝わってくる。そして、ここにも強烈な「私性」が存在する。「つくし煮るどの時間にもつながらず」といった、世界に対する違和感がこの作家を支えているのだろうか。
本書の座談会で、髙柳克弘が「俳句を続けていく道に、結社以外の選択肢が出てきた」ことを指摘しているのが印象に残った。歌壇にも似たような状況があり、ここ十年ほど新人賞の応募者にも「無所属」と記す人が増える一方だ。結社に所属しない人たちによる自由な風が、俳壇に「私性」をもたらした一因だとすると、歌壇ではどんな新しい動きが出てきたのだろう。
ともあれ、伝統ある短詩型の世界が刻々と変化を遂げているということ自体、実に喜ばしいことだと思う。年代も詠風も異なる20人の作品をまとめた本書こそ、その何よりの証左であり、豊かな実りの一つであろう。
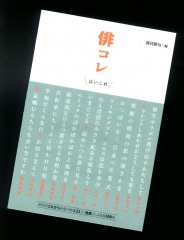 俳コレ 週刊俳句編 web shop 邑書林で買う |







