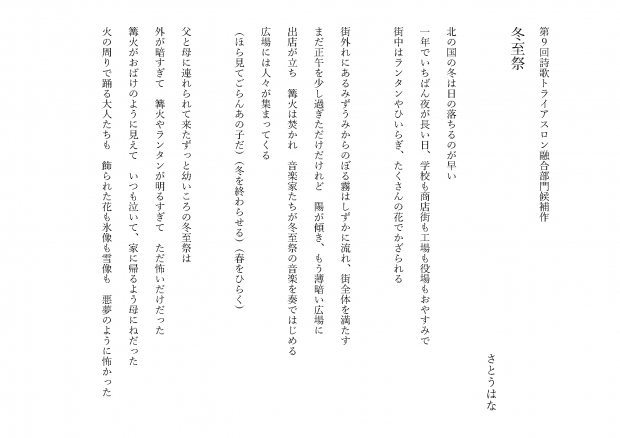
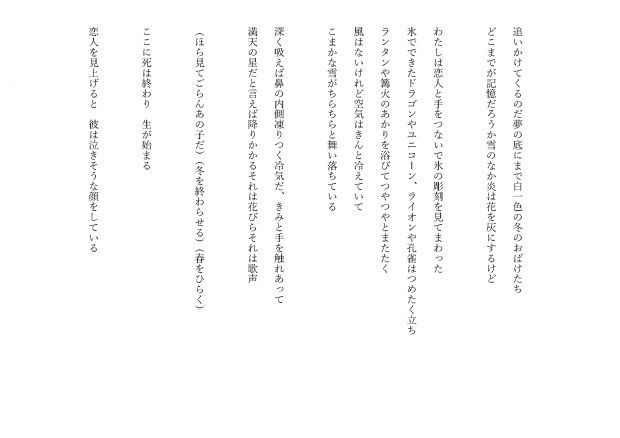
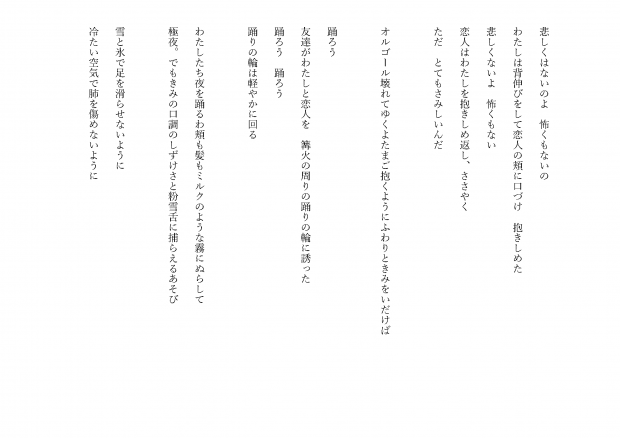
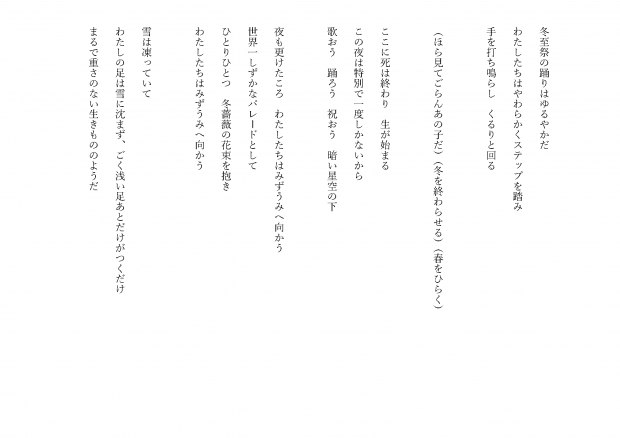
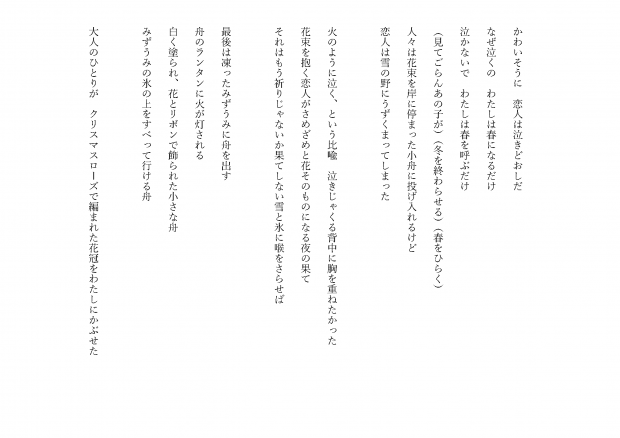
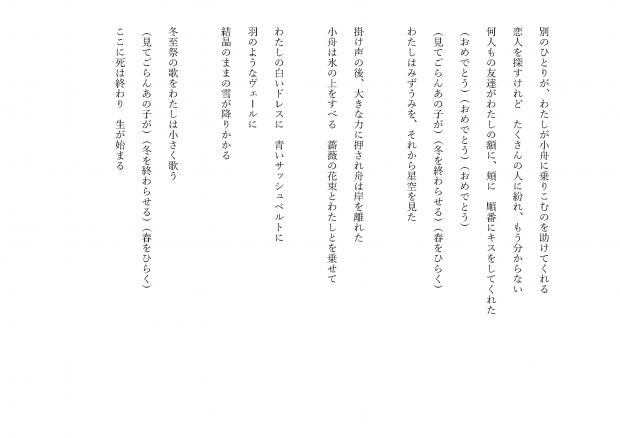
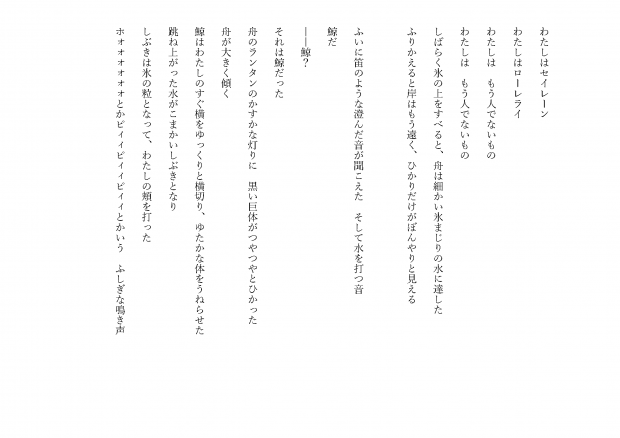
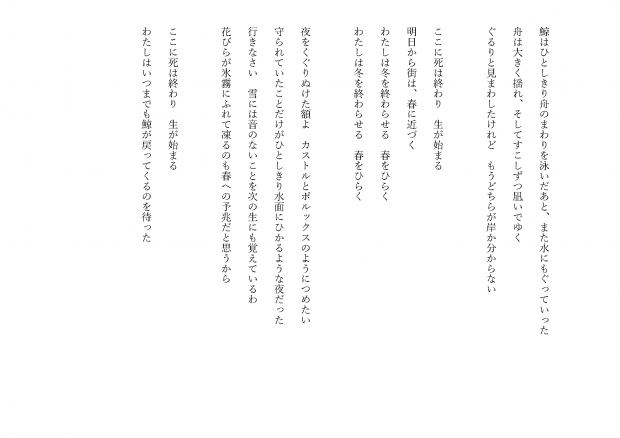
第9回詩歌トライアスロン融合部門候補作
冬至祭 さとうはな
北の国の冬は日の落ちるのが早い
一年でいちばん夜が長い日、学校も商店街も工場も役場もおやすみで
街中はランタンやひいらぎ、たくさんの花でかざられる
街外れにあるみずうみからのぼる霧はしずかに流れ、街全体を満たす
まだ正午を少し過ぎただけだけれど 陽が傾き、もう薄暗い広場に
出店が立ち 篝火は焚かれ 音楽家たちが冬至祭の音楽を奏ではじめる
広場には人々が集まってくる
(ほら見てごらんあの子だ)(冬を終わらせる)(春をひらく)
父と母に連れられて来たずっと幼いころの冬至祭は
外が暗すぎて 篝火やランタンが明るすぎて ただ怖いだけだった
篝火がおばけのように見えて いつも泣いて、家に帰るよう母にねだった
火の周りで踊る大人たちも 飾られた花も氷像も雪像も 悪夢のように怖かった
追いかけてくるのだ夢の底にまで白一色の冬のおばけたち
どこまでが記憶だろうか雪のなか炎は花を灰にするけど
わたしは恋人と手をつないで氷の彫刻を見てまわった
氷でできたドラゴンやユニコーン、ライオンや孔雀はつめたく立ち
ランタンや篝火のあかりを浴びてつやつやとまたたく
風はないけれど空気はきんと冷えていて
こまかな雪がちらちらと舞い落ちている
深く吸えば鼻の内側凍りつく冷気だ、きみと手を触れあって
満天の星だと言えば降りかかるそれは花びらそれは歌声
(ほら見てごらんあの子だ)(冬を終わらせる)(春をひらく)
ここに死は終わり 生が始まる
恋人を見上げると 彼は泣きそうな顔をしている
悲しくはないのよ 怖くもないの
わたしは背伸びをして恋人の頬に口づけ 抱きしめた
悲しくないよ 怖くもない
恋人はわたしを抱きしめ返し、ささやく
ただ とてもさみしいんだ
オルゴール壊れてゆくよたまご抱くようにふわりときみをいだけば
踊ろう
友達がわたしと恋人を 篝火の周りの踊りの輪に誘った
踊ろう 踊ろう
踊りの輪は軽やかに回る
わたしたち夜を踊るわ頬も髪もミルクのような霧にぬらして
極夜。でもきみの口調のしずけさと粉雪舌に捕らえるあそび
雪と氷で足を滑らせないように
冷たい空気で肺を傷めないように
冬至祭の踊りはゆるやかだ
わたしたちはやわらかくステップを踏み
手を打ち鳴らし くるりと回る
(ほら見てごらんあの子だ)(冬を終わらせる)(春をひらく)
ここに死は終わり 生が始まる
この夜は特別で一度しかないから
歌おう 踊ろう 祝おう 暗い星空の下
夜も更けたころ わたしたちはみずうみへ向かう
世界一しずかなパレードとして
ひとりひとつ 冬薔薇の花束を抱き
わたしたちはみずうみへ向かう
雪は凍っていて
わたしの足は雪に沈まず、ごく浅い足あとだけがつくだけ
まるで重さのない生きもののようだ
かわいそうに 恋人は泣きどおしだ
なぜ泣くの わたしは春になるだけ
泣かないで わたしは春を呼ぶだけ
(見てごらんあの子が)(冬を終わらせる)(春をひらく)
人々は花束を岸に停まった小舟に投げ入れるけど
恋人は雪の野にうずくまってしまった
火のように泣く、という比喩 泣きじゃくる背中に胸を重ねたかった
花束を抱く恋人がさめざめと花そのものになる夜の果て
それはもう祈りじゃないか果てしない雪と氷に喉をさらせば
最後は凍ったみずうみに舟を出す
舟のランタンに火が灯される
白く塗られ、花とリボンで飾られた小さな舟
みずうみの氷の上をすべって行ける舟
大人のひとりが クリスマスローズで編まれた花冠をわたしにかぶせた
別のひとりが、わたしが小舟に乗りこむのを助けてくれる
恋人を探すけれど たくさんの人に紛れ、もう分からない
何人もの友達がわたしの額に、頬に 順番にキスをしてくれた
(おめでとう)(おめでとう)(おめでとう)
(見てごらんあの子が)(冬を終わらせる)(春をひらく)
わたしはみずうみを、それから星空を見た
掛け声の後、大きな力に押され舟は岸を離れた
小舟は氷の上をすべる 薔薇の花束とわたしとを乗せて
わたしの白いドレスに 青いサッシュベルトに
羽のようなヴェールに
結晶のままの雪が降りかかる
冬至祭の歌をわたしは小さく歌う
(見てごらんあの子が)(冬を終わらせる)(春をひらく)
ここに死は終わり 生が始まる
わたしはセイレーン
わたしはローレライ
わたしは もう人でないもの
わたしは もう人でないもの
しばらく氷の上をすべると、舟は細かい氷まじりの水に達した
ふりかえると岸はもう遠く、ひかりだけがぼんやりと見える
ふいに笛のような澄んだ音が聞こえた そして水を打つ音
鯨だ
――鯨?
それは鯨だった
舟のランタンのかすかな灯りに 黒い巨体がつやつやとひかった
舟が大きく傾く
鯨はわたしのすぐ横をゆっくりと横切り、ゆたかな体をうねらせた
跳ね上がった水がこまかいしぶきとなり
しぶきは氷の粒となって、わたしの頬を打った
ホォォォォォォとかピィィピィィピィィとかいう ふしぎな鳴き声
鯨はひとしきり舟のまわりを泳いだあと、また水にもぐっていった
舟は大きく揺れ、そしてすこしずつ凪いでゆく
ぐるりと見まわしたけれど もうどちらが岸か分からない
ここに死は終わり 生が始まる
明日から街は、春に近づく
わたしは冬を終わらせる 春をひらく
わたしは冬を終わらせる 春をひらく
夜をくぐりぬけた額よ カストルとポルックスのようにつめたい
守られていたことだけがひとしきり水面にひかるような夜だった
行きなさい 雪には音のないことを次の生にも覚えているわ
花びらが氷霧にふれて凍るのも春への予兆だと思うから
ここに死は終わり 生が始まる
わたしはいつまでも鯨が戻ってくるのを待った







