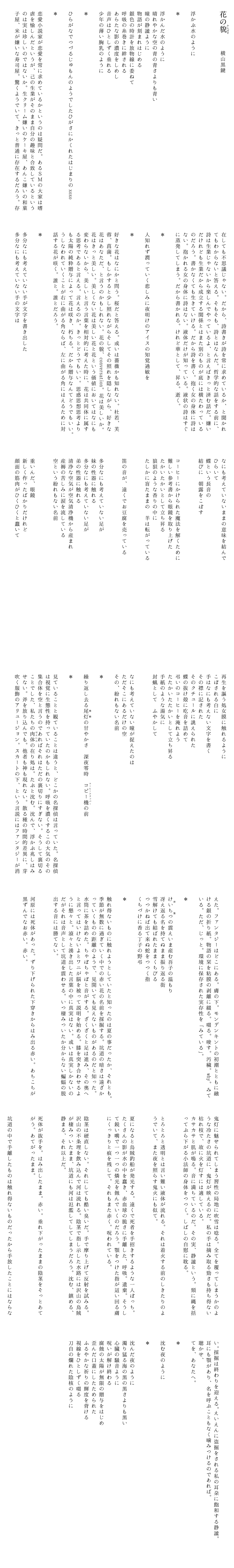花の
浮かぶ水のように
*
浮かんだ水のように
晴れやかな空の青の青さよりも青い
瞳の静謐ように
物語が刻まれはじめる
銀色の時計を放物線に委ねて
呼吸の糸巻きに絆される
あらたな影の濃度をしめし
音声はひとしずく垂れる
少年の薄い胸乳のように
*
ひらがなでつづるじゅもんのようでしたひがさにかくれたはじまりのxoxo
*
恋愛小説家が恋愛を常に求めているかというのは疑問だ。あるSMの大家は嗜
虐を愉しんだというが、己の生業がそのまま自分の趣味と合致しているという
のは実は珍しいのではないか。生クリーム嫌いのケーキ屋、あんこ嫌いの和菓
子屋、米が嫌いな寿司屋。驚くようでいて、きっと普通に存在するだろう。存
在しても不思議じゃない。だから、詩書きが詩を常に求めているか、と聞かれ
てもわからないと答える。そもそも、詩とはなんだ。哲学的な話をする前に、
詩は生業じゃないから楽しんでやっているよ、と言えばきっと済む話だ。嫌い
だけれども生業だから成立する関係とはまた別のものが底には横たわっている
のだろう。書かなくても生きていける。だから詩を書く。抱く女の身体に詩は
ない。抱かれる女の身体に詩はない。液体だけが知っている。液状の詩はすぐ
に蒸発してしまう。だから書かれる。けれど華として、昇る。逝く。
*
人知れず潤っていく悲しみに夜明けのアイスの知覚過敏を
*
好きな花はなにかと問う。桜だと答える。或いは薔薇かも知れない。杜若、芙
蓉、菖蒲。もしかすると少し照れながらそしてその照れを隠しながら、好きな
花はあなただ、と言うのかもしれない。花の貌、conversation。花は美しいか。
花はきっと美しい。美しくない花は美しい花と花という価値においてはなにも
変わらないから、美しいと言う言葉を相対的に考えた時に、花は共同体に属す
る思考であると言える。言えるのか。きっとどうでもいい。思惑思想思考より
も太陽の純粋贈与によって花は咲き、朽ちる。だから贈与なんてどうでもいい。
うしなわれていくことが右に曲がる角ならば、左に曲がる角にはえるために対
話する花が咲く。誰と。誰とだろう。
*
多分なにも考えていない手が文字を書き出した
多分なにも考えていない手の文字は
なにも考えていないままの意味を結んで
ひらいて
蝶という長音の
結びに 朝露をこぼす
コーヒーにかけられた魔法を解くために
難しい参考書から眼鏡を取り上げた
たかいたかいとして立ち昇る
狼狽のような香りの中に
たしかに盲たままの 羊は転がっている
笛の音が、遠くでお豆腐を売っている
多分なにも考えていない足が
妹の性器に触れる
多分なにも考えていない足が
弟の性器に触れる
清浄な空気が空気清浄機から産まれ
産褥の苦しみに涙を流している
空という紛れもない名前
重いんだ、眼鏡
新しく作ったばかりだけれど
顔面の筋肉がひくひくと蠢いて
再生を謳う処女膜に触れるように
こぼされる白に
手はなにも考えない文字を書く
その襟に記された
そのクチュールに誂えられた
蝶の抜け殻に吃音を詰めて
弔いのコーヒーを淹れよう
たたかいたたかいとして立ち昇る
手紙のような湯気に
封蝋として ふやかして
なにも考えていない瞳が捉えたのは
ただそこにあるだけの空
その、紛れもない名前
*
繰り返し去る
*
見ていることと観ていることは違うと、どこかの名探偵は言っていた。名探偵
は視覚に生態性を持っていたのかもしれない。呼吸を濃くするこの大気のその
集合体を空と言うのであればそれはただの裏切りにすぎない。そうして裏切る
ことでした、私たちの
せない。斧を放り込んでも。他者も神も現れない。散る種の時間的差異に、芽
吹く服飾のアリュージョン。スカートの下、という言説にはファンタジーが消
えた。ファンタジーはどこにある。膚の下。モンデンキントの初潮とともに融
ける銀の折り紙。物語の栞を粘膜の剥離に綴る。啜る。唆す。汚穢。why。みて
いる。ただ、じっと。環境に保存された実存性を「みている」。
*
冴え返る名を持てぬまま振り返る街
雪解けても結ばれたままくちびる
つつかねば出て来ぬ蛇をつつく指
くちづけに香る丁子の野弔
*
触れ得ないものに触れようとしていたと知ったのは夏の事だったか、それとも。
季節が無数に過ぎていく中での赤い花の名前を採掘する。坑道の暗さは遠ざか
っていくものの距離のようで、見開いても見えないものがあるのだと知った。
水筒に茶を詰めた。ちゃぽちゃぽと音がする。ざくざくと足は進み、その奥へ
と言ってはいけないよとワニが脳を被って説明を始める。膝を突き合わせるよ
うに懇々と。滾々と湧き出した言葉の中に真実はない。或いは真実しかないの
だがそれは音声として坑道を震わせる。いつ棲みついたか分からない蝙蝠の脱
出する音には勝てない。
河原には死体があった。ずり下げられた下穿きからはみ出る赤い。あちこちが
黒ずんでなお赤い。赤い。
鬼灯に魅せられてしまう習性の局地に吹雪は唸る。全てを覆ってしまうかのよ
うな冷たさの坑道に、鬼灯が映えるのだ。私の手は摘み取る勁さも持ち得ない
枯れ枝で、故に火を灯すには適している。
カサカサと肌が鳴る。音に満ちているのだ。その実、静謐という。頸に縄を括
ってぶら下がる小法師の身体をつつく。しばしの自慰に耽る。
とろとろと透明とは言い難い液体が流れる。それは着火する前のしきたりのよ
うでいて、また夜を照らす鬼火にも似て。
夏になると烏賊釣船が発光する。遠くで死者を手招きするような一人ぼっち。
たくさんの影が水の中を蠢き、赤血球の脆さに手離した、呼吸。遺棄。そうし
て鋭い嘴で一つ一つの燐光を蝕んでいくのだろう。顎をつけた指が這い回る膚
にくっきりと痕を残して。それもまた赤く。呪われている。
陰茎は硬直しない。それにしても酷い臭いだ。手で摩り上げて反射を試みる。
沢山の不条理を飲み込んで河は流れる。陰茎で指し示した水路には沢山の烏賊
が棲みついたまま、坑道にも河は氾濫してしてしまうだろう。沈む、鎮める、
静まる、それ以上だ。
死体が抜手を。はみ出したまま。赤い。垂れ下がったままの陰茎をそっとあて
がう。あてがったまま。
坑道の中で手離したものは触れ得ないものだったから手放したことにはならな
い。採掘は終わりを迎える。えいえんに盗掘をされる私の耳朶に飽和する静謐。
耳にも顎があり、名を呼ぶこともなく噛みつけるのであれば。
聴かせ、
てを、あなたへ。
*
沈む夜のように
*
沈んだ夜のように
濁り猛る海の黒の黒さよりも黒い
心臓の騒音ように
呪いが解け終わる
腐蝕の太陽が無限の贈与をはじめ
歪んだ口蓋にしたためられた
ふるやかな祈りの輝度を背ける
視線をひとしずく啜る
刀自の爛れた陰核のように