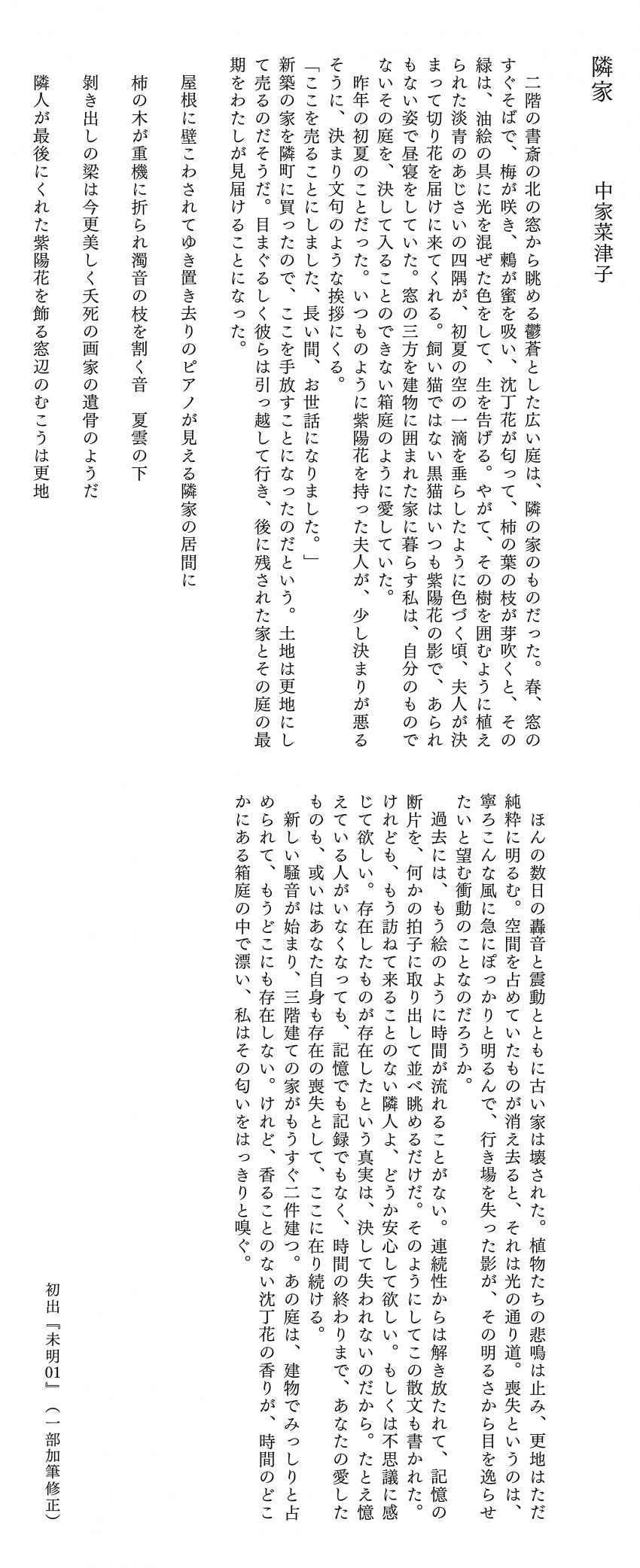隣家 中家 菜津子
二階の書斎の北の窓から眺める鬱蒼とした広い庭は、隣の家のものだった。春、窓のすぐそ
ばで、梅が咲き、鶫が蜜を吸い、沈丁花が匂って、柿の葉の枝が芽吹くと、その緑は、油絵の
具に光を混ぜた色をして、生を告げる。やがて、その樹を囲むように植えられた淡青のあじ
さいの四隅が、初夏の空の一滴を垂らしたように色づく頃、夫人が決まって切り花を届けに来
てくれる。飼い猫ではない黒猫はいつも紫陽花の影で、あられもない姿で昼寝をしていた。窓
の三方を建物に囲まれた家に暮らす私は、自分のものでないその庭を、決して入ることのでき
ない箱庭のように愛していた。
昨年の初夏のことだった。いつものように紫
陽花を持った夫人が、少し決まりが悪るそうに、
決まり文句のような挨拶にくる。
「ここを売ることにしました、長い間、お世話になりました。」
新築の家を隣町に買ったので、ここを手放すことになったのだという。土地は更地にして売る
のだそうだ。目まぐるしく彼らは引っ越して行き、後に残された家とその庭の最期をわたしが
見届けることになった。
屋根に壁こわされてゆき置き去りのピアノが見える隣家の居間に
柿の木が重機に折られ濁音の枝を割く音 夏雲の下
剝き出しの梁は今更美しく夭死の画家の遺骨のようだ
隣人が最後にくれた紫陽花を飾る窓辺のむこうは更地
ほんの数日の轟音と震動とともに古い家は壊された。植物たちの悲鳴は止み、更地はただ純
粋に明るむ。空間を占めていたものが消え去ると、それは光の通り道。喪失というのは、寧ろ
こんな風に急にぽっかりと明るんで、行き場を失った影が、その明るさから目を逸らせたいと
望む衝動のことなのだろうか。
過去には、もう絵のように時間が流れることがない。連続性からは解き放たれて、記憶の断
片を、何かの拍子に取り出して並べ眺めるだけだ。そのようにしてこの散文も書かれた。けれ
ども、もう訪ねて来ることのない隣人よ、どうか安心して欲しい。もしくは不思議に感じて欲
しい。存在したものが存在したという真実は、決して失われないのだから。たとえ憶えている
人がいなくなっても、記憶でも記録でもなく、時間の終わりまで、あなたの愛したものも、或
いはあなた自身も存在の喪失として、ここに在り続ける。
新しい騒音が始まり、三階建ての家がもうすぐ二件建つ。あの庭は、建物でみっしりと占め
られて、もうどこにも存在しない。けれど、香ることのない沈丁花の香りが、時間のどこかに
ある箱庭の中で漂い、私はその匂いをはっきりと嗅ぐ。
初出『未明01』(一部加筆修正)