てのひらのばつた重たくなりて飛ぶ 矢口 晃
いちばんのきれいなときを蛇でいる 岡野泰輔
盆の波虚ろの貝の動きゐる 小林千史
ででむしの腹ゆゆゆゆと動きけり 南十二国
蒲公英は閉ぢ海鳥は岩つかむ 小林千史
早春や飛び立つ鳩の足赤し 小野あらた
玉虫の身をおつぴろげ空を出ず 小林千史
仔を呼べるとき白鳥の白極む 小林千史
バルコンにて虫の中身は黄色かな 野口る理
日曜日いそぎんちゃくに蟹が寄る 矢口 晃
……………
日暮れとともに、路地裏の小さな店がぽっと光った。看板には、『Haut-Colle’』の文字。
ここは知る人ぞ知る、会員制フランス料理店。
席数も22席と非常に少なく、しかしあっさりとした品のよい内装が好ましい。
もちろん味も三つ星級。会員制とはいえ、この店に客の途絶える日はないのだ。
しかし。
今夜、『Haut-Colle’』に来る客はただ一人。
彼が来る夜だけは、他の客をとらないとシェフは堅く決めているのだ。
なぜか。
彼はここのオーナーだからだ。
それだけではない。
機嫌次第でわけのわからないことを言いまくるうえに、新しいメニューの説明をことこまかに求めたあげく、食べ散らかすだけ食べ散らかして、マズイ!とつっ返すこともしばしば。
そのうえ一番困るのは、オーナーが新メニューの名前を決める、という取り決めが契約書にあり、そのセンスがむちゃくちゃ悪いことだ(それはおいおいわかる)。
さて、今まさにここにその彼が居る。諸君、紹介しよう。このいかにも底意地の悪そうな紳士こそ、『Haut-Colle’』のオーナーであり悪名高き書評家にして自称グルメ、オナカム氏である。
オナカム氏は店の前でコートを脱ぐと、ゴシックロリータ調のワンピースを整え(本筋には何の関係もないが、オナカム氏はここぞというときしばしば女装するのだ)、本の扉を開くように店のドアをチリンと押した。
「いらっしゃいませ、お待ちしておりました、オナカム様」
シェフは(ちっ、またいつもの女装かよ)と内心苦々しく思いながらもそんなことはおくびにも出さず丁重にお辞儀をした。
「うむ。わしはもう、おなかのむしが鳴いて鳴いて困ってをるのだ。早速席へ案内してくれたまへ」
「はい、ではコートをこちらへ」
オナカム氏は狭いオナカム氏専用赤絨毯廊下をまっすぐ奥へ、突き当りの非常に悪趣味な、鹿の剥製がでかでかと壁にかけられた部屋へと案内された。
「今宵のメニューは…」
「黙れ。さっさとせい。紙幅の関係がある」オナカム氏は煙草に火をつけながら横柄に応えた。
エラソーな女装親父め、ていうかだいたい喫煙しながらフランス料理のフルコース食って味わかんのかよ、とシェフはまた苦々しく思ったがもちろん顔色一つ変えずに厨房へ合図を出した。
「まずはオードブルでございます」
ワゴンの上には曇りひとつないクロッシュがあり、それをあけると
てのひらのばつた重たくなりて飛ぶ 矢口 晃
という一枚の短冊。
そう、ここは俳句をコース仕立てで味わう、一風変わったフランス料理店なのである。
「ふむ」
オナカム氏はまずその短冊をあらゆる角度からじろじろみた。
「ま、見た目はシンプルイズザベストといふところかな。悪くない」
とエラソーに言いながら、一口。
「ふーむ、む。ちょっとオードブルにしては、重いんぢあなひかねへ?」
「いえいえ、もうしばし、お待ちくださいますれば…」
「ほう?…おっ!!」
オナカム氏は、突然目をまんまるにした。
「軽いっ!さっきまでの重みが消えて、ふっと軽くなったぞ!なんという味わい!これは愉快なオードブルぢあ!成程、斯様な句であったか。うむ、わしにも覚えがある、子供の頃にばったを取っててのひらに載せるとな、しばらくしてぴょーんとどこかへ飛んでいってしまうんじゃ。そのとき一瞬ばったはふとももに力をこめて、重くなったように感ずる。あの感じを的確に表現してをる。名句じゃ、名句じゃ」
「ありがとうございます」
シェフはかしこまって頭を下げかけた、そのとき、
「だがな、晃!」
オナカム氏は突如立ち上がってテーブルにハイヒールを載せ、叫んだ!
「やっぱり重いんだよ、この句はよ、もっと【飛ぶ】に照準を絞るべきなんだよ、なのにてめーは『ばつたが飛ぶ前に一瞬重くなること』を発見したことに舞い上がって、ドヤ顔で【重たくなりて】なんつって中七全部使いきってよ!そんなに字数食う話じゃねえよ、飛ぶ前に重くなるってのはよ!まじ重てえよ中七!もっと軽く言えるんだよこんなことは!どうにでも調理してやれるが、たとえばなー」
「オナカム様!」
シェフは珍しく強い調子でオナカム氏の言葉を遮った。
「彼はまだ若き青年にございますれば、この青春性を生かして、年長者の添削等はいかがなものかと…また、次の皿も既にご用意できております」
「む…そうか?そうだな、青春性。うむ。若い芽を摘むのはよくなひ。ではこの新オードブルに名前を与えるとしよう。短冊を持て」
「は、ここに」
オナカム氏は少しも考えることなく短冊にすらすらとこう書いた。
『三種のばつたのゼリー寄せ~名もなき草を添えて~』
「これでいこう。三種のばつたはトノサマとキチキチとショウリョウじゃ。ただし味はもっと軽やかに、もうちと、うまいことまとめろ」
「は、ありがとうございます」
シェフは内心(よかった、思ったより今日のオナカム氏は普通だ)と思った。
しかしここからどんどん暴走するのが御中虫、じゃなかった、オナカム氏なのである…。
「では、次はスープでございます」
シェフがクロッシュを開けると、
いちばんのきれいなときを蛇でいる 岡野泰輔
「おお、これはまた耽美な句じゃのう、好みじゃ、好みじゃ…『いちばんのきれいなときを』とするするとひらがなできて、『蛇』という毒のある漢字でぴりりと引き締め、またするするとひらがなでおさめる。この一句全体がまさに蛇体を成してをる。喉越しもよく、少々の毒もあり、まったく申し分ない句じゃ」
「ありがとうございま」
「だがな、泰輔!」
オナカム氏は銀のスプーンを握りしめたままワゴンを蹴り倒して、叫んだ!
「甘えてんじゃねーよ、【蛇】に!甘えてんじゃねーよ、『蛇のもつ耽美性』に!そんなのはなあ、それこそエデンの昔っからあったイマージュなんだ、てめえの手柄じゃねえんだ、それをなんだ、【いちばんのきれいなときを】などと耽美に耽美を重ね薔薇に薔薇を添えるやうなバッカな真似しやがって、得意になってんじゃねーよ、ええ!? だいたいてめーの句は全部」
「オナカム様!」
シェフは蹴り倒されたワゴンを立て直しつつ、しかしキリッとした目つきでオナカム氏の暴言を遮った。
「オナカム様の御腹立ち、いちいちごもっともに存じますれば、料理人にも厳しく申し伝えますゆえ、ここはひとつ、穏便に、穏便に…なにゆえ今宵のメニューは新進気鋭の俳人たちの饗宴ゆえ、どうぞその広いお心でお受け取りくださいませぬか」
オナカム氏は乱れた髪型(傍目には坊主頭なのだが彼の中ではなにか決まりごとがあるらしい)を手櫛で直しつつ、落としたリボンを頭のてっぺんにつけて(これはどうやってつけているのか誰も知らない)、
「おお、そうであった、そうであった…今宵は気鋭の饗宴メニュー。少々のことには目をつぶらねばなるまいて。これからの俳人をつぶす気など、わしにはこれっぽっちもないのじゃからなあ」
(嘘吐け)と思いながらシェフは、
「では、メニューに名前を頂戴できましょうか」
と短冊を差しだした。
オナカム氏は少しも考えることなく短冊にすらすらとこう書いた。
『蛇の薬膳スープ~少女の接吻のやうに召し上がれ~』
「蛇は滋養にも美容にもよいからのう。そして何よりその耽美なエロスを味わうがよい、ほっほっほ」
「は、ありがとうございます」
シェフは内心(やべえ、なんかちょっと変になってきてるよ…)と思った。
仕方がない、もともとそういう人なんだから。
「オナカム様、次の皿は、魚料理二種でございます」
「ほう、二種盛りか。どれどれ」
シェフがクロッシュを開けると、
盆の波虚ろの貝の動きゐる 小林千史
ででむしの腹ゆゆゆゆと動きけり 南十二国
の二句が並んである。
「おい、二句とも魚ではないぞ?」
「は、さようで。ただ、いま一番活きのいい魚介類が、この二句でしたので、今宵はこちらをお召し上がりになっていただきたく…」
「そうか。ではまず、貝の方からいただくぞ。うむ…?この貝、ほんとうに活きがいいのか…?なんだか不穏な味がするぞ…?というか、身はあるのか?んん?これは…ああ!成程!盆か!盆返りしてきた祖霊を貝に託したのだな?この不可思議な味わい、やっと得心がいった!妙かな、妙かな!」
「ありがとうございますオナカム様、では続いて二皿目もご賞味されたく」
「うむ、続けてゆこう、次はででむしとな?おお、これはほんたうに活きがいいわい、ゆゆゆゆ、と動いてをる、わはは、舌の上でもゆゆゆゆ、喉でもゆゆゆゆ、腹のなかでもゆゆゆゆ、わは、わは、わはは!」
「ありがとうござ」
「だがな、千史!十二国!」
オナカム氏はナイフとフォークをチャリーンと放りあげてテーブルにグサリグサリと刺さるのを見届けてから、叫んだ!
「刺すぞ!おまいら!動物が動くのはあったりまえやんけ!せっかく上の方からいい言葉並べて来てんのにや、最後『動きゐる』で『動きけり』って、そんなケツの持たせ方ガキでもやりよるぞ?『虚ろの貝』『腹ゆゆゆゆと』このセンスはええ。ええけどな、そこで浮かれたんやろ、ケツの穴締めるっちゅうこと忘れたやろ、そこまでがええさかいに、余計に最後でガックーて落ちてまうんや、わかるか?『そんなオチかい!』って突っ込まれても、おまいら言い返す言葉ないんちゃうんけ!ええ!?もっと言うとな」
「オナカム様!」
シェフはテーブルに突き刺さったナイフとフォークを静かに抜きつつ、オナカム氏の言葉を遮った。
「何度も申し上げるようで恐縮ですが、今宵は…」
「ああ、もうよい、紙幅の関係などもあるのだ、忘れておった。さくさく行かねばフルコースじゃからのう。短冊持ってこい」
オナカム氏は用意された短冊にさらさらとこう書きつけた。
『活貝の五種盛り~フランべ盆提灯とゝもに~』
『ででむしのをどり食い~赤ワインを注げよ!歓喜の歌を歌へよ!~』
「よいか、貝のほうはフランべすることを忘れるな、盆の灯を表現するのだ、そして、ででむしのほうは、ゆゆゆゆと高らかに!BGMは『歓喜の歌』を大音量で!」
「は、ありがとうございます」
シェフは内心(いつのまに五種盛りになったり歓喜の歌になったりしてんだよ!)と舌打ちしたが、もう遅かった。
「さあ、いよいよメインの肉料理だな!期待してをるぞ!」
オナカム氏はナプキンを首に巻くとそわそわして言った。
「はい、本日は少し趣向を凝らしまして、鳥づくしでございます」
「鳥づくし?牛や羊もあったろうに?」
「はい、あるにはあったのですが、精選した結果、鳥を扱う料理人の腕が冴えておりましたのです」
「ふむ、ではさっそく持ってくるがよい」
ワゴンのクロッシュを開けるとそこには
蒲公英は閉ぢ海鳥は岩つかむ 小林千史
オナカム氏はまず一口食べると、ほうと感嘆の声を上げた。
「これは硬派な句ぢぁ!目に浮かぶのは…そう、崖、日本海に面した断崖!蒲公英はその上に咲いてゐるのだらふ…しかし【閉ぢ】てゐる。まるで作者の心が閉ぢてゐるやうにも感じられる…作者はいま、ある種の人間不信に陥ってゐるのかもしれぬ…しかしそんななか、【海鳥は岩つかむ】!ここが強い!ここに作者の確たる信念がある!作者はいま苦しい局面にゐるやうだが、このゆるぎない信念がある限り、きっと明るい未来が待ってをる!よい、これはよいぞ!苦しさの中にも矜持あり!」
「ありがとうご」
「だがな、千史!」
オナカム氏はやおら立ち上がると窓際に走りゆき窓をバアン!と開けて、叫んだ!
「いまどきこんなシーン、演歌でも歌わねーぞオラ!ってゆうか演歌に負けてんじゃねーかオラ!蒲公英が閉ぢてゐる、これはなかなかよい、心理描写としても秀逸だしかしな海鳥が岩つかんじゃだめだろそれやったらそれゆったらおしまいだよ!『それは写生なんです!』とかゆうなよ!写生だとしても見逃さねばならない写生もあるのだ、蒲公英にズームインしたまではよかったがそこからなぜ岩つかむ海鳥にパンしてしまったのだ馬鹿者!ここで読者は『あーあ、また例の(わたし今は頑なで世間と合わない生き方してる、だけどこの一途な思い、忘れたくない…!)的ヒロインが出ちゃったよ』てしらけるんだよ!そこんとこわかってんのかァーーー!!!そのうえ」
「オナカム様!」
シェフはオナカム氏の開けた窓から吹き込む強風に煽られたテーブルクロスを直しながらたしなめた。
「今宵は」
「もうよい!わかっておる!短冊を!」
オナカム氏は少し(いやだいぶか?)不機嫌な顔つきで短冊にさらさらとこう書いた。
『蒲公英の香りの海鳥岩塩包み焼き~二時間ドラマ犯人崖っぷちの局面をむかへて~』
「この句には二時間ドラマ程度の味わいしかないが、そこを蒲公英の香りでなんとかごまかせ、よいな」
「は、ありがとうございます」
シェフは内心(あーあー、だんだん毒が出てきたなーやべえなー)と思ったがもちろん顔には出さなかったし、出しても無駄だとわかっていた。
「今の句で少々興を削がれた。次の肉料理とソルベは一緒に食す」
「かしこまりました、こちらでございます」
シェフは慣れた手つきでクロッシュのふたを開けた。
早春や飛び立つ鳩の足赤し 小野あらた
玉虫の身をおつぴろげ空を出ず 小林千史
「ふむ。肉料理は鳩の句、ソルベは玉虫か。ではまず肉料理から」
オナカム氏は鳩の句を一口。
「この香り…!早春、たしかに早春の風がいまわしの口中を駆け抜けて行ったぞよ!そして…おお、軽くなった、飛び立った、その足の赤さよ!眼を瞑った方がこの句の味わいは深くなりそうだな…うむ、やはりそうだ、こうして目を瞑ると早春の爽やかな一風、そしてさあっと飛び立った鳩の足の鮮やかな赤い色が、瞼の裏にいつまでも残る…よい、よいぞ、きりりとしたものを感じる一句じゃ。…うむ、わしの機嫌もだいぶ直った。次の句はソルベだったな、続けて食すぞ。おお、これはさっきの句とは逆に目を開いて食さねばこの価値はわかるまい。なんといううつくしい玉虫の輝きじゃ。しかもこの中七のおおらかなこと!いやいや、それともこれは『死』を暗喩してゐるのか?いやいや、そのような読みはわしの好みではない、ここは玉虫氏が大の字になり生を謳歌してゐると見たてよう…そうでなくては【空を出ず】が効くまい。こんなにも、こんなにも玉虫氏は大きくのびあがってゐるのに、空といふさらなる果てしないものを超えられはしないのだ、そうだ、うむ、深い、深いぞ…」
「ありがと…」
「だがな、あらた、千史!」
オナカム氏はまたも立ち上がり、さっきから開けっ放しの窓…外は既に真っ暗で、しかも暴風雨になっていた…に向かって、叫んだ!
「まず、鳩の句!ピントをもっと絞れ!これは誰か別のヤツにも言ったことだが、このさい【早春】なんて邪魔でしかねーんだよ!中七、下五、とくに下五だろ言いたいことは!なんだこのぼやぼやした季語!こういう場合は無季でも字足らずでもいいんだよ!無理やり季語で埋めんな!季語だってそんな扱われ方したくねーよ!それからな、玉虫のやつ!これもある意味同じだ!中七下五、特に下五が本質なんだよ、玉虫ぢぁなくたっていいんだよ、語呂がいいからって、季語だからって、テキトーこいてんじゃねーよ!本当にこの句を生かす季語を探せ、なかったら創れ!わかったか!なに、わからぬ?じゃあもっと言おう」
「オナカム様!」
「短冊!」
オナカム氏はさっきより更に不機嫌に加速を付けた様子でこう書いた。
『鳩の赤足やわらか煮~玉虫に捧ぐオマージュ~』
『ほろにが玉虫のシャーベット~墓石を裏返すとたいていゐます~』
「ま、どちらもどちらだがソルベの方が句格は上だと感じたからな、そういうサブタイトルにしておいたぞよ」
「ありがとうございます」
シェフは内心(鳩料理になんで玉虫のオマージュが入ってんだよ、しかも玉虫のソルベには墓石とかって無茶苦茶だよもう)と思ったが顔に出す元気もなかった。
「最後の肉料理でございます、オナカム様」
「うむ」
シェフがクロッシュを開けると、
仔を呼べるとき白鳥の白極む 小林千史
「ほう!最後は白鳥か!では一口…む、これは母親の味がするな?しかも仔を呼んでゐる、なにやら切実そうに呼んでゐる…危機か?危機に瀕してゐるのか仔は?【白極む】ときては…仔を思う痛切さを感じる一句じゃ。最後の肉料理にふさわしい、シンプルだが美しい一句だ」
「ありが」
「だがな、千史!またおまへかって感じもするが!」
オナカム氏はもはや暴風雨を通り越して台風到来としか思えない部屋の中で(誰も窓を閉めないのは、何度閉めてもオナカム氏が開けることがわかっているからだ)、叫んだ!
「この句、何歳で作ったんや!? 俳句教室で初心者が老先生の真似して作ったか、もしくは己が枯れすぎて手抜きしてるとしか見えんぞ、わしには!【白極む】でキマったぜ!とか思ったんかもわからんがな、白鳥を見たら誰でも最初はそこを詠うもんなんじゃドアホ!とにかくこの手抜き感には脱力や!俳句なめんなァーーー!!」
「オナカム様!」
「短冊!」
もう部屋の中は荒れ放題だったがオナカム氏はまったくそんなことを意に解さぬ不機嫌振りで短冊にこうしたためた。
『白鳥の!【レンジでチン!羽毛仕立て】~「たかしちゃん、はよ帰りやぁ、ご飯出来たでぇ」公園にて~』
「こんなぬるい句は即席ごはんで十分だな!料理人としても一品ラク出来てよかろう」
「は、ありがとうございます」
シェフは内心(いやいやいや、これは言いすぎでしょう…ってゆうかタイトルもサブタイトルも原句から離れすぎでしょう…肉料理やのに即席ごはんて)と思ったが以下略。
「では、お口直しのチーズでございます」
「うむ、ではバルコンへ案内せよ」
「は?」
「バルコンで食す、と言っておるのだ」
「は、はい」
シェフは(ああああもうだからこのおっさん、いやなんだよおおおお!! 台風だっつの!)と思いながらずぶぬれのバルコニーへ席を用意し、オナカム氏を案内した。
そしてクロッシュを開くと、
バルコンにて虫の中身は黄色かな 野口る理
「おお!わしは預言者のようだのう!この句にはちゃんと『バルコンにて』と書いておるではないか!わはは!ではいただくぞ!」
機嫌を直した様子で、一口。
「む…むにゅ?むにゅにゅ??これは…虫…?か?いや、チーズだよな、チーズ…いや違う虫だ!虫の中身なのだ!わしは今それを確認した!そしてまた作者も、バルコンにて、虫の中身が黄色であるということを確認したのだ!この抗えない写生感!そして作者は間違いなく女性だ!こういったさゝやかな残虐性をさらっといってのけるのは、主として若い女性に多いものなのだ!名前は?おお、る理か、そうか!読者に嫌悪感を抱かせることなくまとめてくるこの手腕!さすがだ!」
「あり」
「だがな、る理!」
オナカム氏はロココ調のバルコンの手すりに足を掛けて、叫んだ!
「むかつくぞ!【バルコンにて】っておまえナニサマやねん!要するにベランダやろ!物干し場ちゃうんけ!それをあえて【バルコンにて】と字余りで言い変えたおまへの姫根性、まじむかつく!どーせ便所スリッパで虫踏みつぶしただけやねんやろが!それをいかにも15Cmのハイヒールのかかとできゅっと踏んだみたいにイメージ操作しやがって、さらに【かな】の修辞技法により、まるで、あたくしがしたことではないんですの、あたくしには虫を踏みつぶしたといふ罪悪感も快楽もないんですの、善悪のない透明な妖精ですの、あたくしはただ、虫の中身が黄色い、そんな客観的な事実を述べたにすぎないことですのよ、うふふ、うふうふ、ってなァ!! おまへはどこまでゆるふわ不思議ごっこをする気か!いい加減」
「オナカム様!」
「短冊!」
『ムシルザン地方のムシルザン・チーズ~ある種の虫の中身に酷似してゐますがチーズですの~』
「なに、ムシルザン地方はどこか?知るか!!」
「は、失礼しました」
シェフは…もういいよね、みんなわかってるよね。うんうん。
「最後のメニューとなりました、オナカム様。デザートでございます」
「うむ。ではひきつづきバルコンにて食す」
日曜日いそぎんちゃくに蟹が寄る 矢口 晃
「ほう。これはまた、のどかな一句じゃのう。いそぎんちゃくか。愛らしい。しかし、うむ。この句、下五が曲者じゃな? 【日曜日】【いそぎんちゃく】と来て【蟹が寄る】…蟹はいそぎんちゃくをどうしようといふのだ?ああそうか、食べるわけではないな、共生を図ろうとしてをるだけじゃな、蟹がイソギンチャクを手に持って威嚇するという、あれのことだろう、ならばよい。しかし…いそぎんちゃくの身としては、嬉しいわけではないのかな?うむ、共生と言うのは少し違うようだ…まあしかし、いずれにしろ、【日曜日】が全てを救ってくれてゐる句である。平和かな、平和かな」
「あ」
「だがな、晃!」
オナカム氏は雷雨もなんのその、バルコンの手すりからさらに身を乗り出して、叫んだ!
「【日曜日】にしたのは、大きな間違いだったかもしれんぞ!仮にこれを『金曜日』にしたらどうか?一挙に蟹の不穏性が高まろう。また『火曜日の』にしたらどうか?読者はがぜん、いそぎんちゃくと蟹の火のように赤い色を想起し、鮮やかな句となったろう。ところがおまへが選んだのは最も無難な『日曜日』だった!がっかりだ、がっかりだよ晃!おまへには冒険心といふものがないのか?実験精神はないのか?この句にはそういうところが感じられん!ぬるいんだ!ぬりいいい!!!!!!わあああああああ」
「オナカム様!」
シェフはバルコンに駆け寄った。オナカム氏は興奮のあまり、バルコンから転落したのだ。
「いかがなさいますか、シェフ」
と、今まで奥ではらはら見守っていた今日の料理人たちはシェフにたずねた。
「よい、捨て置け、ヤツのコートは外に放り出しておけ、みんな毎度のことながら、罵倒に耐えてくれてごくろうだったね。さあ、ゆっくり休んでくれたまえ、ああ、最後のメニューのタイトルは私が決めよう」
シェフはそういうと、短冊をとりだしてこう書いた。
『シェフの気まぐれ日曜日~蟹といそぎんちゃくの泡雪~』
「うむ、無難でよい。やはりメニューはこうでなくてはな」
彼はシェフ帽を脱ぎ、椅子に腰かけ、軽くため息をついた。そしてちらりとこちらを見ると、
「ああ、こんなひどい書評を読んでくださったみなさまにも厚くお礼申しあげます。今回はとりわけ長かったですが、来週からは通常営業に戻りますので、安心してください、まあ、通常営業でもひどいことに変わりはないですがね、ハハハ、では失礼」
といって、看板のライトを消した。
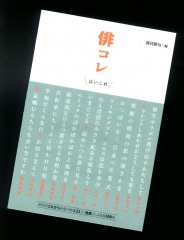 俳コレ 週刊俳句編 web shop 邑書林で買う |
執筆者紹介
- 御中虫(おなか・むし)
1979年8月13日大阪生。京都市立芸術大学美術学部中退。
第3回芝不器男俳句新人賞受賞。平成万葉千人一首グランプリ受賞。
第14回毎日新聞俳句大賞小川軽舟選入選。第2回北斗賞佳作入選。第19回西東
三鬼賞秀逸入選。文学の森俳句界賞受賞。第14回尾崎放哉賞入選。






2012年5月22日 : spica - 俳句ウェブマガジン -
on 5月 22nd, 2012
@ :
[…] した「設定コント」の由。しかし、「だがな、る理!」は変わらず。 http://shiika.sakura.ne.jp/haiku/hai-colle/2012-03-23-7062.html 御中虫10句選の中より選ぶとすれば いちばんのきれいなときを蛇 […]