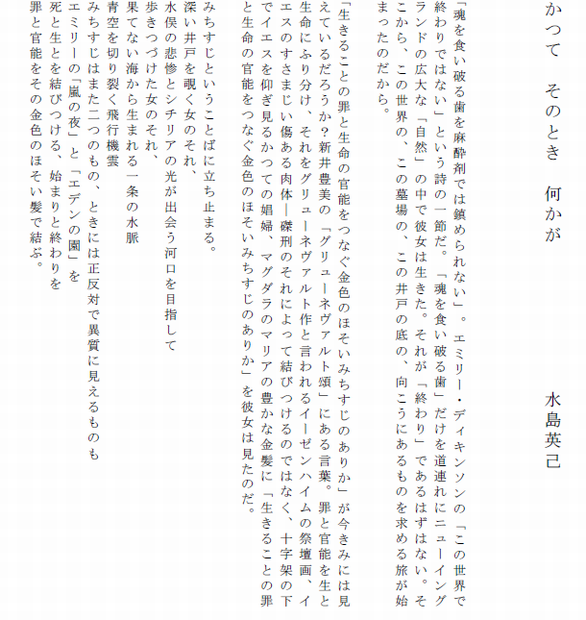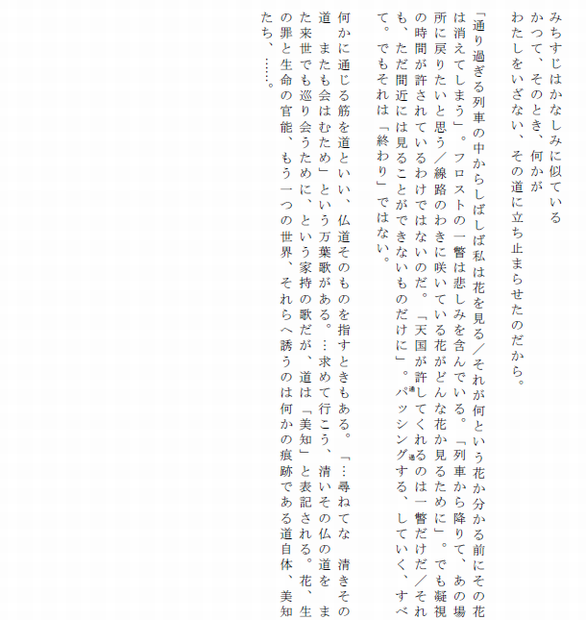かつて そのとき 何かが 水島英己
「魂を食い破る歯を麻酔剤では鎮められない」。エミリー・ディキンソンの「この世界で終わりではない」という詩の一節だ。「魂を食い破る歯」だけを道連れにニューイングランドの広大な「自然」の中で彼女は生きた。それが「終わり」であるはずはない。そこから、この世界の、この墓場の、この井戸の底の、向こうにあるものを求める旅が始まったのだから。
「生きることの罪と生命の官能をつなぐ金色のほそいみちすじのありか」が今きみには見えているだろうか?新井豊美の「グリューネヴァルト頌」にある言葉。罪と官能を生と生命にふり分け、それをグリューネヴァルト作と言われるイーゼンハイムの祭壇画、イエスのすさまじい傷ある肉体―磔刑のそれによって結びつけるのではなく、十字架の下でイエスを仰ぎ見るかつての娼婦、マグダラのマリアの豊かな金髪に「生きることの罪と生命の官能をつなぐ金色のほそいみちすじのありか」を彼女は見たのだ。
みちすじということばに立ち止まる。
深い井戸を覗く女のそれ、
水俣の悲惨とシチリアの光が出会う河口を目指して
歩きつづけた女のそれ、
果てない海から生まれる一条の水脈
青空を切り裂く飛行機雲
みちすじはまた二つのもの、ときには正反対で異質に見えるものも
エミリーの「嵐の夜」と「エデンの園」を
死と生とを結びつける、始まりと終わりを
罪と官能をその金色のほそい髪で結ぶ。
みちすじはかなしみに似ている
かつて、そのとき、何かが
わたしをいざない、その道に立ち止まらせたのだから。
「通り過ぎる列車の中からしばしば私は花を見る/それが何という花か分かる前にその花は消えてしまう」。フロストの一瞥は悲しみを含んでいる。「列車から降りて、あの場所に戻りたいと思う/線路のわきに咲いている花がどんな花か見るために」。でも凝視の時間が許されているわけではないのだ。「天国が許してくれるのは一瞥だけだ/それも、ただ間近には見ることができないものだけに」。
何かに通じる筋を道といい、仏道そのものを指すときもある。「…尋ねてな 清きその道 またも会はむため」という万葉歌がある。…求めて行こう、清いその仏の道を また来世でも巡り会うために、という家持の歌だが、道は「美知」と表記される。花、生の罪と生命の官能、もう一つの世界、それらへ誘うのは何かの痕跡である道自体、美知たち、……。