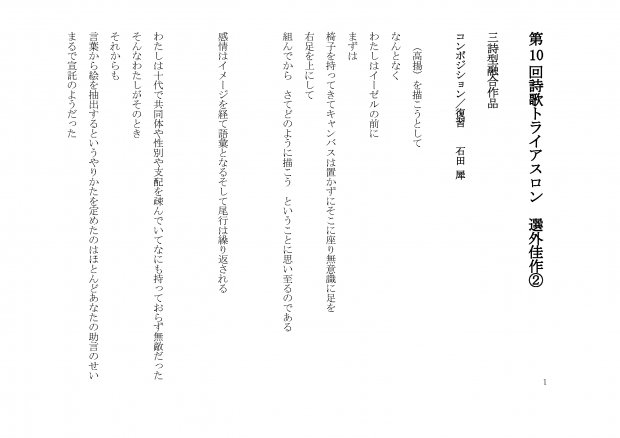
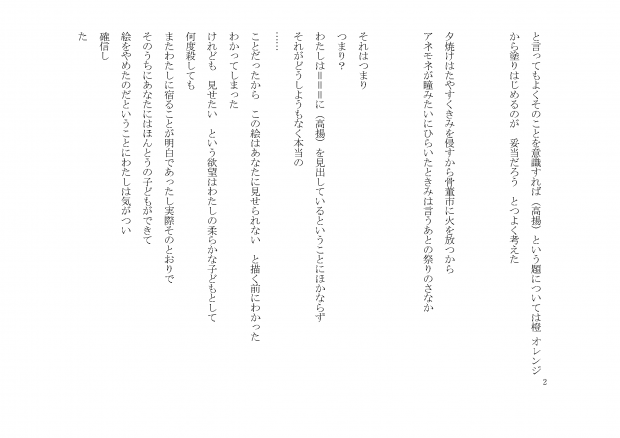
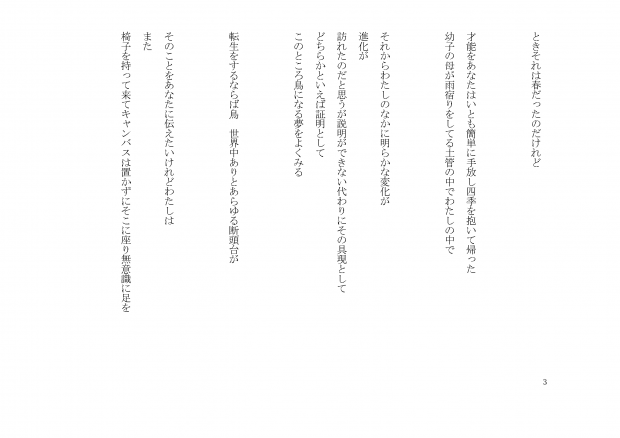
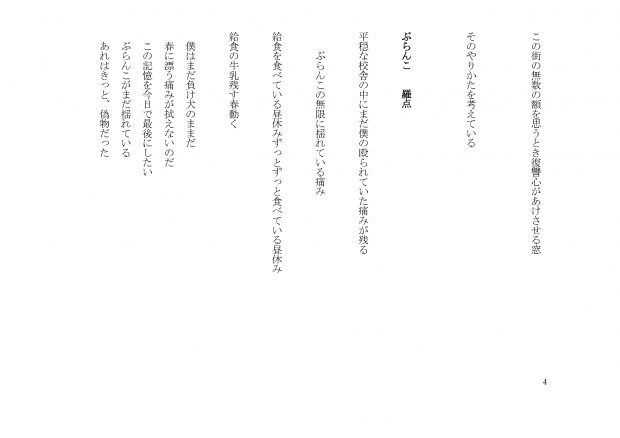
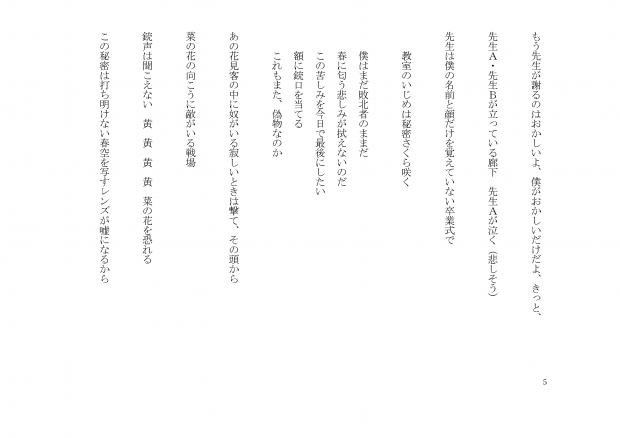
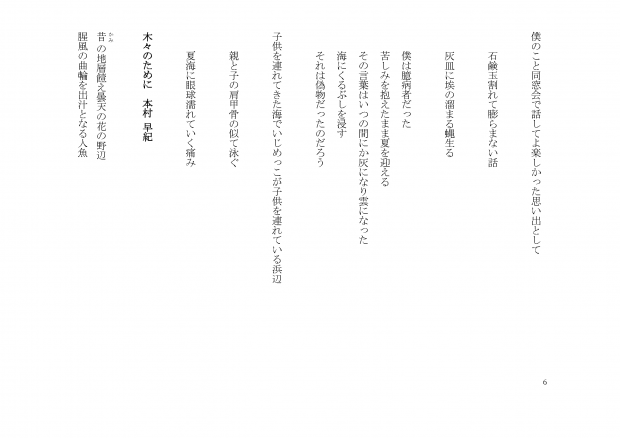
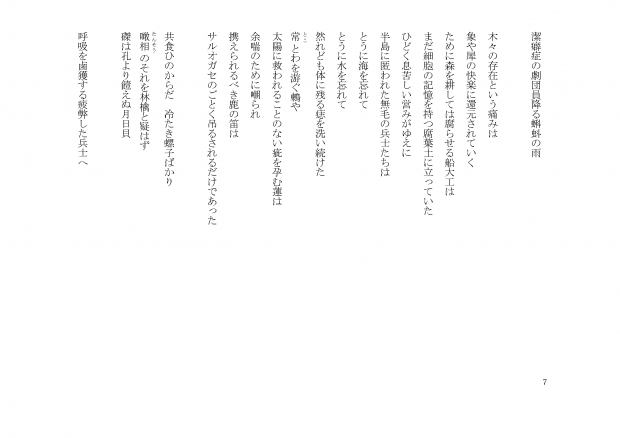
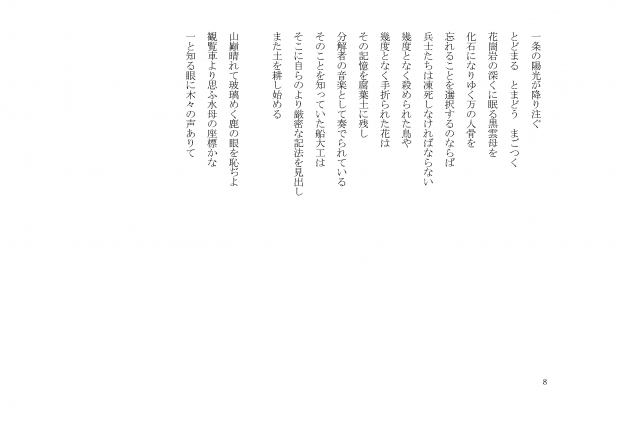
第10回詩歌トライアスロン 選外佳作②
三詩型融合作品
コンポジション/復習 石田 犀
(高揚)を描こうとして
なんとなく
わたしはイーゼルの前に
まずは
椅子を持ってきてキャンバスは置かずにそこに座り無意識に足を
右足を上にして
組んでから さてどのように描こう ということに思い至るのである
感情はイメージを経て語彙となるそして尾行は繰り返される
わたしは十代で共同体や性別や支配を疎んでいてなにも持っておらず無敵だった
そんなわたしがそのとき
それからも
言葉から絵を抽出するというやりかたを定めたのはほとんどあなたの助言のせい
まるで宣託のようだった
と言ってもよくそのことを意識すれば(高揚)という題については橙
オレンジ
から塗りはじめるのが 妥当だろう とつよく考えた
夕焼けはたやすくきみを侵すから骨董市に火を放つから
アネモネが瞳みたいにひらいたときみは言うあとの祭りのさなか
それはつまり
つまり?
わたしは===に(高揚)を見出しているということにほかならず
それがどうしようもなく本当の
……
ことだったから この絵はあなたに見せられない と描く前にわかった
わかってしまった
けれども 見せたい という欲望はわたしの柔らかな子どもとして
何度殺しても
またわたしに宿ることが明白であったし実際そのとおりで
そのうちにあなたにはほんとうの子どもができて
絵をやめたのだということにわたしは気がつい
確信し
た
ときそれは春だったのだけれど
才能をあなたはいとも簡単に手放し四季を抱いて帰った
幼子の母が雨宿りをしてる土管の中でわたしの中で
それからわたしのなかに明らかな変化が
進化が
訪れたのだと思うが説明ができない代わりにその具現として
どちらかといえば証明として
このところ鳥になる夢をよくみる
転生をするならば鳥 世界中ありとあらゆる断頭台が
そのことをあなたに伝えたいけれどわたしは
また
椅子を持って来てキャンバスは置かずにそこに座り無意識に足を
この街の無数の額を思うとき復讐心があけさせる窓
そのやりかたを考えている
ぶらんこ 羅点
平穏な校舎の中にまだ僕の殴られていた痛みが残る
ぶらんこの無限に揺れている痛み
給食を食べている昼休みずっとずっと食べている昼休み
給食の牛乳残す春動く
僕はまだ負け犬のままだ
春に漂う痛みが拭えないのだ
この記憶を今日で最後にしたい
ぶらんこがまだ揺れている
あれはきっと、偽物だった
もう先生が謝るのはおかしいよ、僕がおかしいだけだよ、きっと、
先生A・先生Bが立っている廊下 先生Aが泣く(悲しそう)
先生は僕の名前と顔だけを覚えていない卒業式で
教室のいじめは秘密さくら咲く
僕はまだ敗北者のままだ
春に匂う悲しみが拭えないのだ
この苦しみを今日で最後にしたい
額に銃口を当てる
これもまた、偽物なのか
あの花見客の中に奴がいる寂しいときは撃て、その頭から
菜の花の向こうに敵がいる戦場
銃声は聞こえない 黄 黄 黄 黄 菜の花を恐れる
この秘密は打ち明けない春空を写すレンズが嘘になるから
僕のこと同窓会で話してよ楽しかった思い出として
石鹸玉割れて膨らまない話
灰皿に埃の溜まる蝿生る
僕は臆病者だった
苦しみを抱えたまま夏を迎える
その言葉はいつの間にか灰になり雲になった
海にくるぶしを浸す
それは偽物だったのだろう
子供を連れてきた海でいじめっこが子供を連れている浜辺
親と子の肩甲骨の似て泳ぐ
夏海に眼球濡れていく痛み
木々のために 本村 早紀
昔(かみ)の地層饐え曇天の花の野辺
腥風の曲輪を出汁となる人魚
潔癖症の劇団員降る蝌蚪の雨
木々の存在という痛みは
象や犀の快楽に還元されていく
ために森を耕しては腐らせる船大工は
まだ細胞の記憶を持つ腐葉土に立っていた
ひどく息苦しい営みがゆえに
半島に匿われた無毛の兵士たちは
とうに海を忘れて
とうに水を忘れて
然れども体に残る痣を洗い続けた
常(とこ)とわを游ぐ鶫や
太陽に救われることのない疵を孕む蓮は
余喘のために嘲られ
携えられるべき鹿の笛は
サルオガセのごとく吊るされるだけであった
共食ひのからだ 冷たき螺子ばかり
噉相(たんそう)のそれを林檎と疑はず
磔は孔より饐えぬ月日貝
呼吸を鹵獲する疲弊した兵士へ
一条の陽光が降り注ぐ
とどまる とまどう まごつく
花崗岩の深くに眠る黒雲母を
化石になりゆく万の人骨を
忘れることを選択するのならば
兵士たちは凍死しなければならない
幾度となく殺められた鳥や
幾度となく手折られた花は
その記憶を腐葉土に残し
分解者の音楽として奏でられている
そのことを知っていた船大工は
そこに自らのより厳密な記法を見出し
また土を耕し始める
山巓晴れて玻璃めく鹿の眼を恥ぢよ
観覧車より思ふ水母の座標かな
一と知る眼に木々の声ありて








