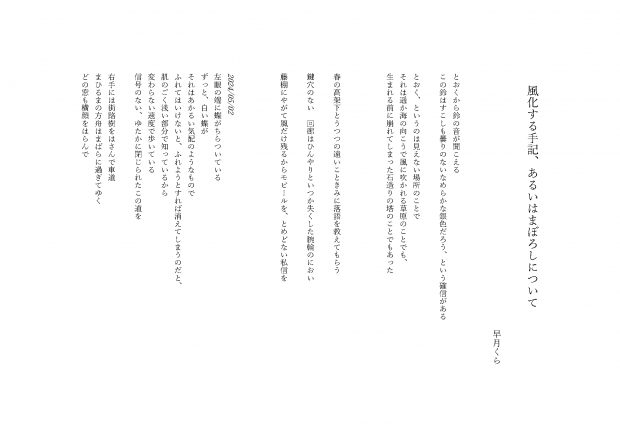
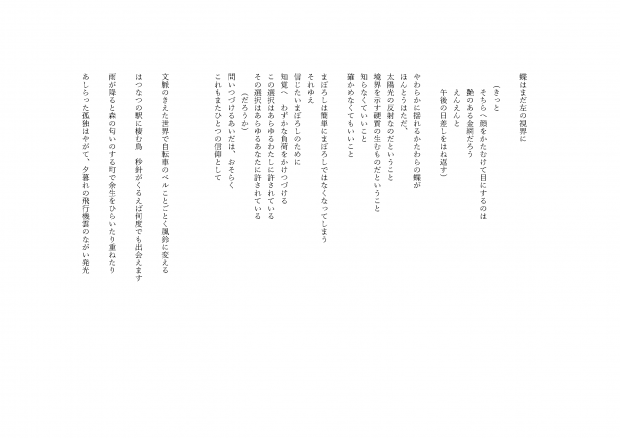

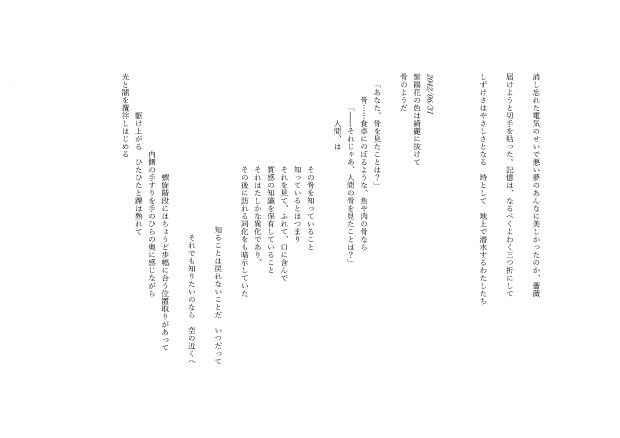
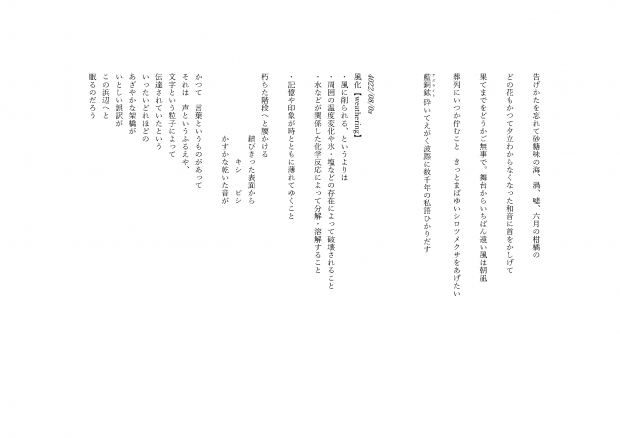

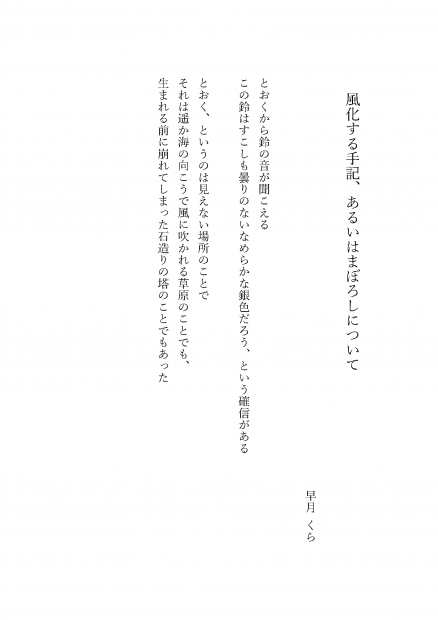
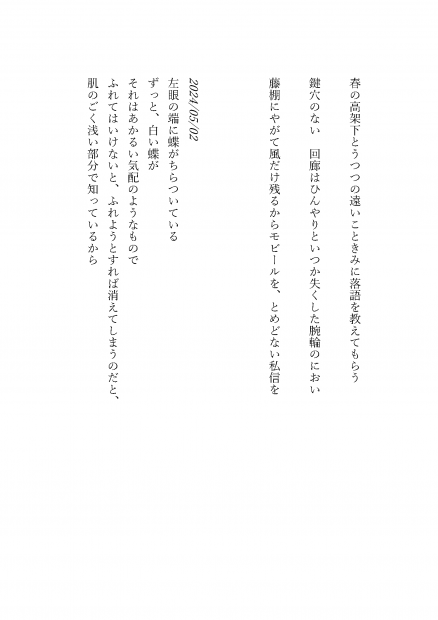
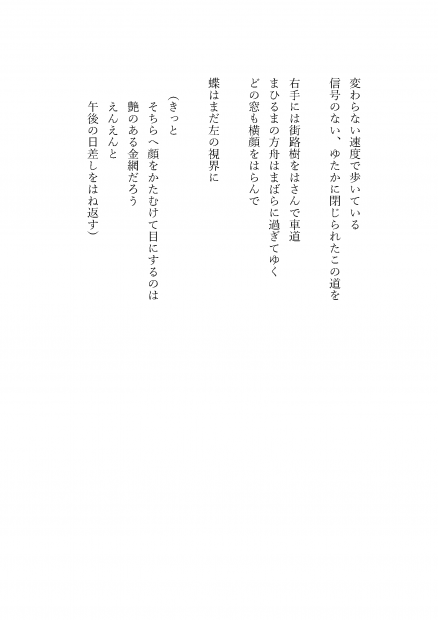
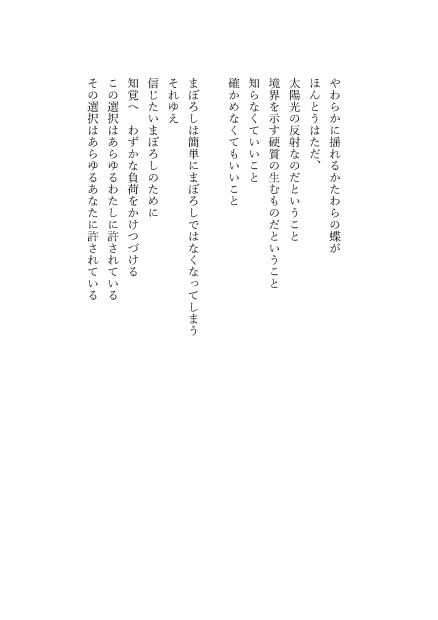
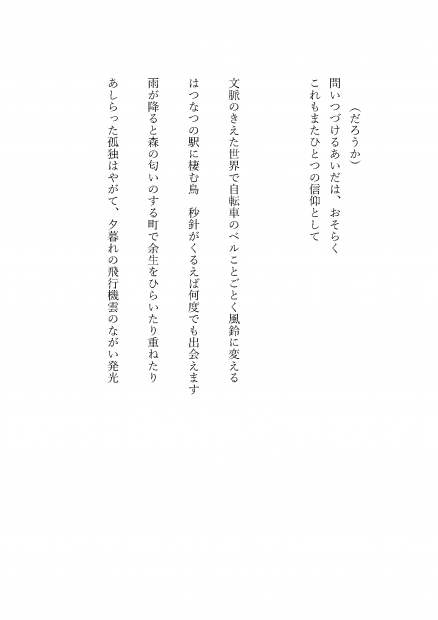
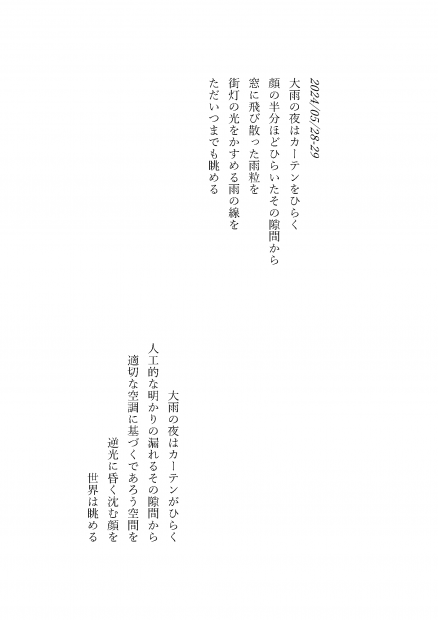
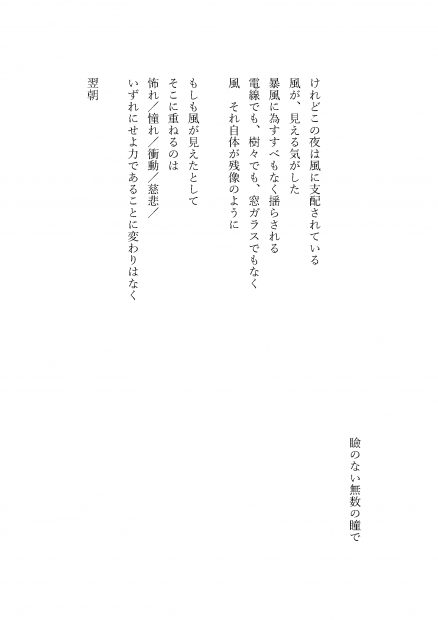
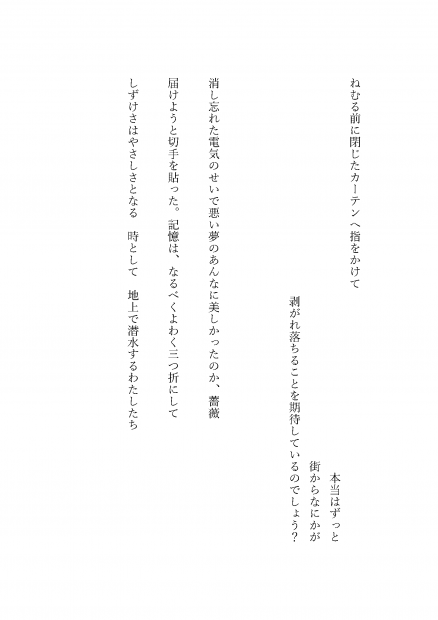
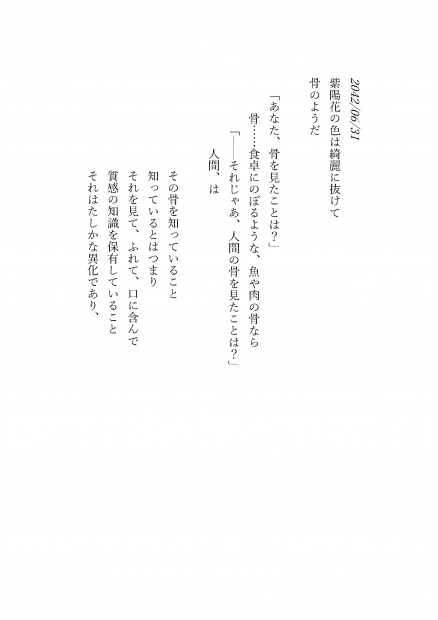
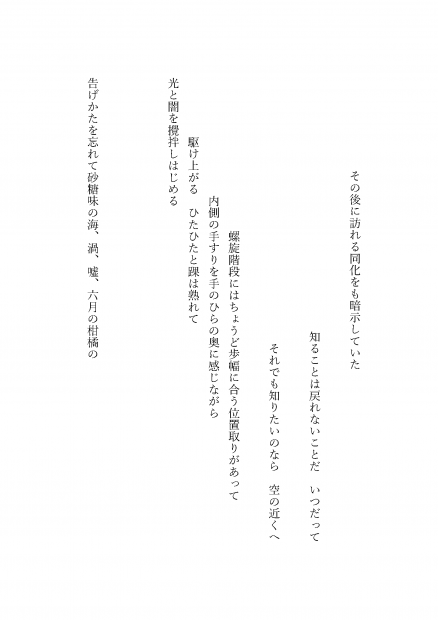
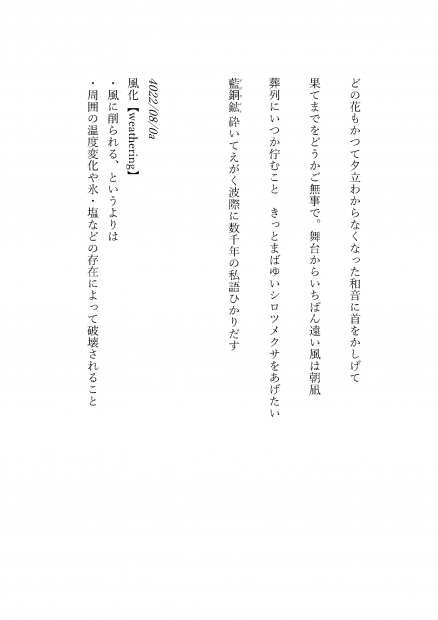
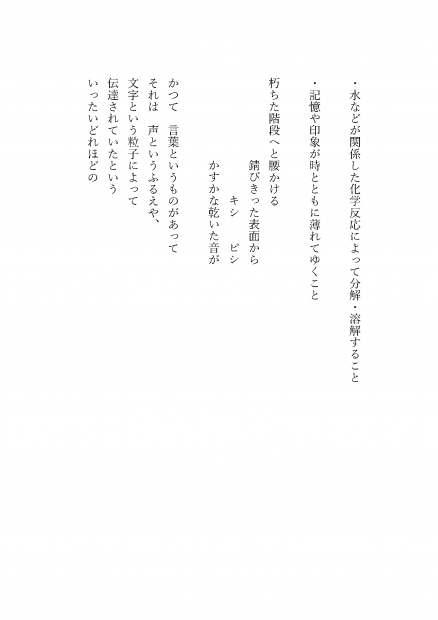

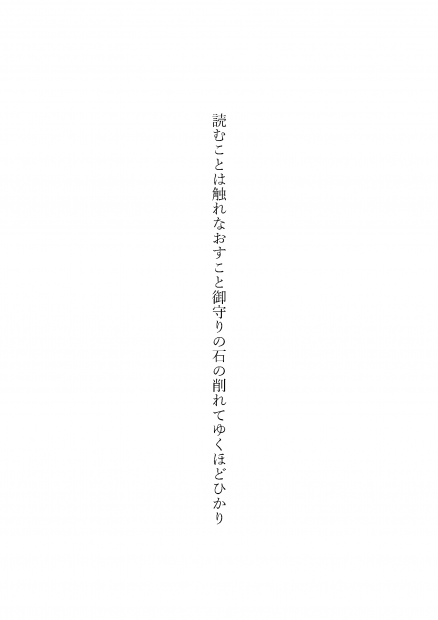
第9回詩歌トライアスロン三詩型融合型受賞連載第6回
風化する手記、あるいはまぼろしについて
早月くら
とおくから鈴の音が聞こえる
この鈴はすこしも曇りのないなめらかな銀色だろう、という確信がある
とおく、というのは見えない場所のことで
それは遥か海の向こうで風に吹かれる草原のことでも、
生まれる前に崩れてしまった石造りの塔のことでもあった
春の高架下とうつつの遠いこときみに落語を教えてもらう
鍵穴のない 回廊はひんやりといつか失くした腕輪のにおい
藤棚にやがて風だけ残るからモビールを、とめどない私信を
2024/05/02
左眼の端に蝶がちらついている
ずっと、白い蝶が
それはあかるい気配のようなもので
ふれてはいけないと、ふれようとすれば消えてしまうのだと、
肌のごく浅い部分で知っているから
変わらない速度で歩いている
信号のない、ゆたかに閉じられたこの道を
右手には街路樹をはさんで車道
まひるまの方舟はまばらに過ぎてゆく
どの窓も横顔をはらんで
蝶はまだ左の視界に
(きっと
そちらへ顔をかたむけて目にするのは
艶のある金網だろう
えんえんと
午後の日差しをはね返す)
やわらかに揺れるかたわらの蝶が
ほんとうはただ、
太陽光の反射なのだということ
境界を示す硬質の生むものだということ
知らなくていいこと
確かめなくてもいいこと
まぼろしは簡単にまぼろしではなくなってしまう
それゆえ
信じたいまぼろしのために
知覚へ わずかな負荷をかけつづける
この選択はあらゆるわたしに許されている
その選択はあらゆるあなたに許されている
(だろうか)
問いつづけるあいだは、おそらく
これもまたひとつの信仰として
文脈のきえた世界で自転車のベルことごとく風鈴に変える
はつなつの駅に棲む鳥 秒針がくるえば何度でも出会えます
雨が降ると森の匂いのする町で余生をひらいたり重ねたり
あしらった孤独はやがて、夕暮れの飛行機雲のながい発光
2024/05/28-29
大雨の夜はカーテンをひらく
顔の半分ほどひらいたその隙間から
窓に飛び散った雨粒を
街灯の光をかすめる雨の線を
ただいつまでも眺める
大雨の夜はカーテンがひらく
人工的な明かりの漏れるその隙間から
適切な空調に基づくであろう空間を
逆光に昏く沈む顔を
世界は眺める
瞼のない無数の瞳で
けれどこの夜は風に支配されている
風が、見える気がした
暴風に為すすべもなく揺らされる
電線でも、樹々でも、窓ガラスでもなく
風 それ自体が残像のように
もしも風が見えたとして
そこに重ねるのは
怖れ/憧れ/衝動/慈悲/
いずれにせよ力であることに変わりはなく
翌朝
ねむる前に閉じたカーテンへ指をかけて
本当はずっと
街からなにかが
剥がれ落ちることを期待しているのでしょう?
消し忘れた電気のせいで悪い夢のあんなに美しかったのか、薔薇
届けようと切手を貼った。記憶は、なるべくよわく三つ折にして
しずけさはやさしさとなる 時として 地上で潜水するわたしたち
2042/06/31
紫陽花の色は綺麗に抜けて
骨のようだ
「あなた、骨を見たことは?」
骨……食卓にのぼるような、魚や肉の骨なら
「——それじゃあ、人間の骨を見たことは?」
人間、は
その骨を知っていること
知っているとはつまり
それを見て、ふれて、口に含んで
質感の知識を保有していること
それはたしかな異化であり、
その後に訪れる同化をも暗示していた
知ることは戻れないことだ いつだって
それでも知りたいのなら 空の近くへ
螺旋階段にはちょうど歩幅に合う位置取りがあって
内側の手すりを手のひらの奥に感じながら
駆け上がる ひたひたと踝は熟れて
光と闇を攪拌しはじめる
告げかたを忘れて砂糖味の海、渦、嘘、六月の柑橘の
どの花もかつて夕立わからなくなった和音に首をかしげて
果てまでをどうかご無事で。舞台からいちばん遠い風は朝凪
葬列にいつか佇むこと きっとまばゆいシロツメクサをあげたい
藍銅鉱(アズライト)砕いてえがく波際に数千年の私語ひかりだす
4022/08/0a
風化【weathering】
・風に削られる、というよりは
・周囲の温度変化や氷・塩などの存在によって破壊されること
・水などが関係した化学反応によって分解・溶解すること
・記憶や印象が時とともに薄れてゆくこと
朽ちた階段へと腰かける
錆びきった表面から
キシ ピシ
かすかな乾いた音が
かつて 言葉というものがあって
それは 声というふるえや、
文字という粒子によって
伝達されていたという
いったいどれほどの
あざやかな架橋が
いとしい誤訳が
この浜辺へと
眠るのだろう
読むことは触れなおすこと御守りの石の削れてゆくほどひかり








