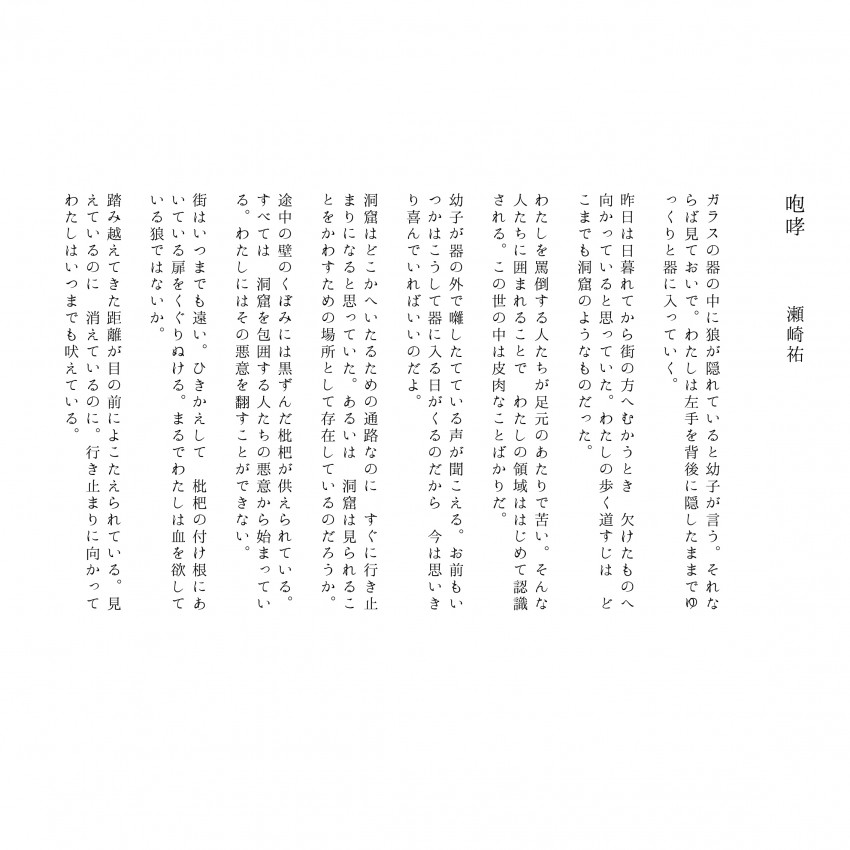咆哮 瀬崎祐
ガラスの器の中に狼が隠れていると幼子が言う。それな
らば見ておいで。わたしは左手を背後に隠したままでゆ
っくりと器に入っていく。
昨日は日暮れてから街の方へむかうとき 欠けたものへ
向かっていると思っていた。わたしの歩く道すじは ど
こまでも洞窟のようなものだった。
わたしを罵倒する人たちが足元のあたりで苦い。そんな
人たちに囲まれることで わたしの領域ははじめて認識
される。この世の中は皮肉なことばかりだ。
幼子が器の外で囃したてている声が聞こえる。お前もい
つかはこうして器に入る日がくるのだから 今は思いき
り喜んでいればいいのだよ。
洞窟はどこかへいたるための通路なのに すぐに行き止
まりになると思っていた。あるいは 洞窟は見られるこ
とをかわすための場所として存在しているのだろうか。
途中の壁のくぼみには黒ずんだ枇杷が供えられている。
すべては 洞窟を包囲する人たちの悪意から始まってい
る。わたしにはその悪意を翻すことができない。
街はいつまでも遠い。ひきかえして 枇杷の付け根にあ
いている扉をくぐりぬける。まるでわたしは血を欲して
いる狼ではないか。
踏み越えてきた距離が目の前によこたえられている。見
えているのに 消えているのに。行き止まりに向かって
わたしはいつまでも吠えている。