読みと詠み
平成23年12月23日、『俳コレ』シンポジウムで提案された第一部のテーマが「詠むと読むのあいだで」であった。これを神野紗希と佐藤文香が軽快に語り合っていたが、彼らは仲間たちの句会で読みができたと言う。読みから詠みがあったことは事実だろうが、読みからできる詠み以外の詠みについては語られていない。この世代はお互い読み合うという意識が強かったと言うことを言いたいのだろうが、仲間たちから離れて詠む(制作する)という可能性は、俳句甲子園の集団からはうまく伝わってこない。しかし一方で、芝不器男賞の冨田拓也や関悦史は、詠んだうえでの読み、というプロセスがあったと思う。少し古い世代になれば、攝津幸彦がそうであり、攝津が言うには俳句について何も学ばなかった、俳句はひねることだという思い込みで作り続けたと言う。確かに後者は独りよがりな詠みしか行われないのではないかという危惧があるが、一方で読みを経たうえでの詠みは何をもってその独創性を保証するのかという心配もあるのである。
未だかって誰ひとり詠んだことのない俳句を詠みたい、我々読者もそうした俳句を読んでみたい、という熱望は文学の根幹にある思いだろう。それは作者作者の内面からわき上がるものであって、読み合うことによって生まれるものではない。もちろん、そうして詠まれたものを共感もって語り合う場所も必要であり、例えばトリスタン・ツァラがチューリッヒのキャバレー・ヴォルテールで朗読会を開くなどの場として俳句甲子園も後世位置づけられるかもしれない。その場は、是非過激であってほしいものだ。
さてそのためには、選は暴力であり、旧世代の新世代に対する抑圧であり、詠むことを至上とする主張が見えなければならない。『俳コレ』シンポジウムの第二部「撰ぶこと撰ばれること」が中途半端であったのはそうしたことに由来しているだろう。「大人は判ってくれない」という声はどこからもわきあがってこなかった。第一回目の『新撰21』シンポジウムで登壇した北大路翼の情痴・風俗に満ちた俳句は多少そういう気味があったし、北大路の発言自身「大人は判ってくれない」とわめいているようなものだ。狂犬のように見なされること自身、若い作家にとっては名誉なことではなかろうか。
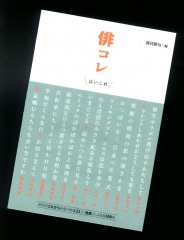 俳コレ 週刊俳句編 web shop 邑書林で買う |
執筆者紹介
- 筑紫磐井(つくし・ばんせい)
1950年、東京生まれ。「豈」発行人。句集に『筑紫磐井集』、評論集に『定型詩学の原理』など。あとのもろもろは省略。





