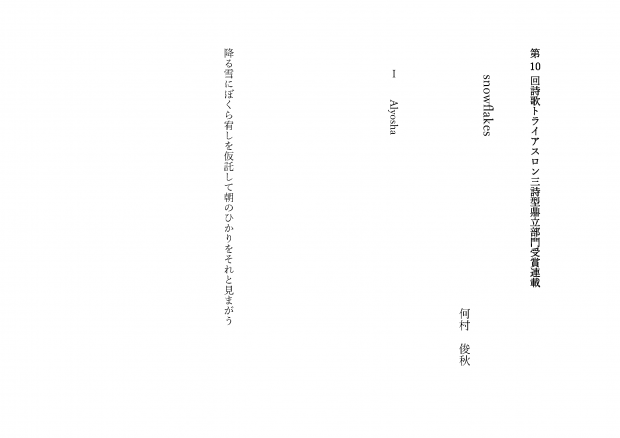
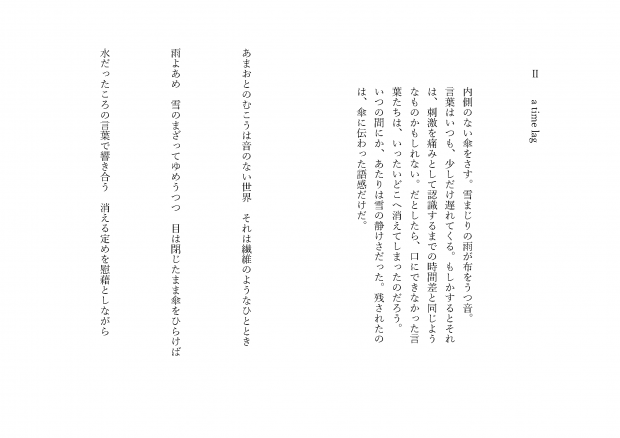
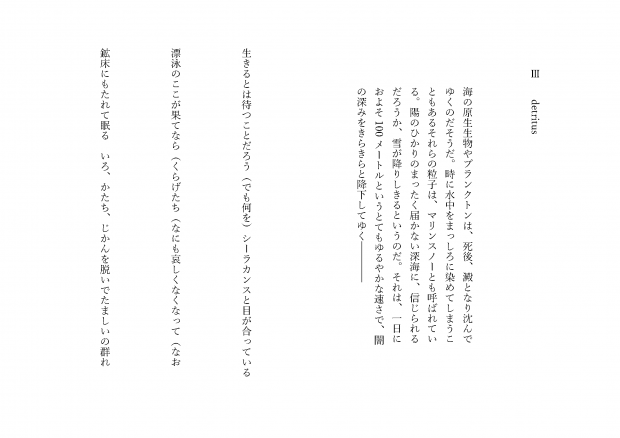
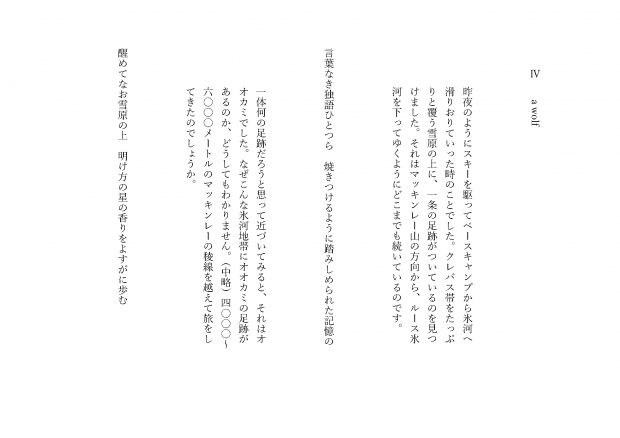
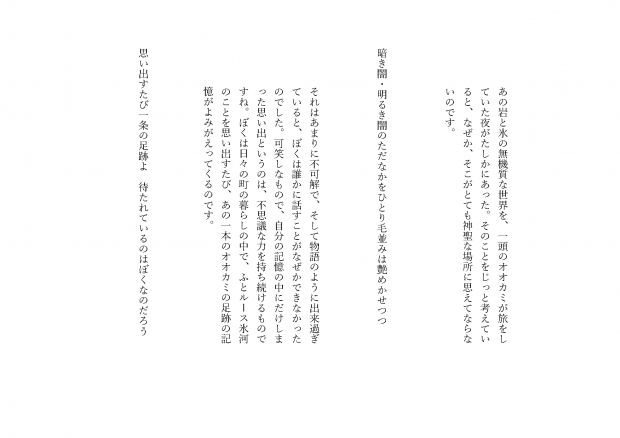
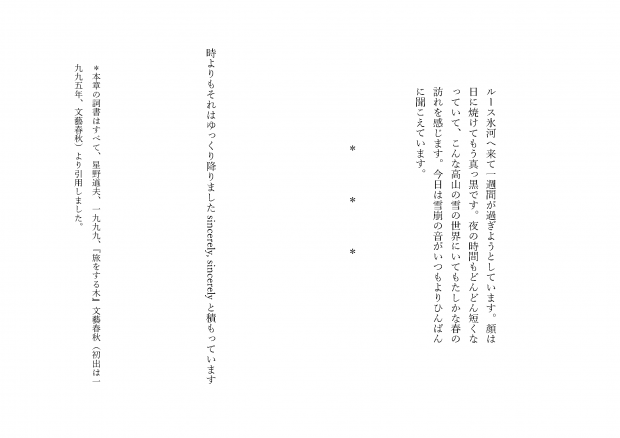
第10回詩歌トライアスロン三詩型鼎立部門受賞連載
snowflakes
何村 俊秋
Ⅰ Alyosha
降る雪にぼくら宥しを仮託して朝のひかりをそれと見まがう
Ⅱ a time lag
内側のない傘をさす。雪まじりの雨が布をうつ音。
言葉はいつも、少しだけ遅れてくる。もしかするとそれは、刺激を痛みとして認識するまでの時間差と同じようなものかもしれない。だとしたら、口にできなかった言葉たちは、いったいどこへ消えてしまったのだろう。
いつの間にか、あたりは雪の静けさだった。残されたのは、傘に伝わった語感だけだ。
あまおとのむこうは音のない世界 それは繊維のようなひととき
雨よあめ 雪のまざってゆめうつつ 目は閉じたまま傘をひらけば
水だったころの言葉で響き合う 消える定めを慰藉としながら
Ⅲ detritus
海の原生生物やプランクトンは、死後、澱となり沈んでゆくのだそうだ。時に水中をまっしろに染めてしまうこともあるそれらの粒子は、マリンスノーとも呼ばれている。陽のひかりのまったく届かない深海に、信じられるだろうか、雪が降りしきるというのだ。それは、一日におよそ100メートルというとてもゆるやかな速さで、闇の深みをきらきらと降下してゆく────
生きるとは待つことだろう(でも何を)シーラカンスと目が合っている
漂泳のここが果てなら(くらげたち(なにも哀しくなくなって(なお
鉱床にもたれて眠る いろ、かたち、じかんを脱いでたましいの群れ
Ⅳ a wolf
昨夜のようにスキーを駆ってベースキャンプから氷河へ滑りおりていった時のことでした。クレバス帯をたっぷりと覆う雪原の上に、一条の足跡がついているのを見つけました。それはマッキンレー山の方向から、ルース氷河を下ってゆくようにどこまでも続いているのです。
言葉なき独語ひとつら 焼きつけるように踏みしめられた記憶の
一体何の足跡だろうと思って近づいてみると、それはオオカミでした。なぜこんな氷河地帯にオオカミの足跡があるのか、どうしてもわかりません。(中略)四〇〇〇~六〇〇〇メートルのマッキンレーの稜線を越えて旅をしてきたのでしょうか。
醒めてなお雪原の上 明け方の星の香りをよすがに歩む
あの岩と氷の無機質な世界を、一頭のオオカミが旅をしていた夜がたしかにあった。そのことをじっと考えていると、なぜか、そこがとても神聖な場所に思えてならないのです。
暗き闇・明るき闇のただなかをひとり毛並みは艶めかせつつ
それはあまりに不可解で、そして物語のように出来過ぎていると、ぼくは誰かに話すことがなぜかできなかったのでした。可笑しなもので、自分の記憶の中にだけしまった思い出というのは、不思議な力を持ち続けるものですね。ぼくは日々の町の暮らしの中で、ふとルース氷河のことを思い出すたび、あの一本のオオカミの足跡の記憶がよみがえってくるのです。
思い出すたび一条の足跡よ 待たれているのはぼくなのだろう
ルース氷河へ来て一週間が過ぎようとしています。顔は日に焼けてもう真っ黒です。夜の時間もどんどん短くなっていて、こんな高山の雪の世界にいてもたしかな春の訪れを感じます。今日は雪崩の音がいつもよりひんぱんに聞こえています。
* * *
時よりもそれはゆっくり降りましたsincerely, sincerelyと積もっています
*本章の詞書はすべて、星野道夫、一九九九、『旅をする木』文藝春秋(初出は一九九五年、文藝春秋)より引用しました。








