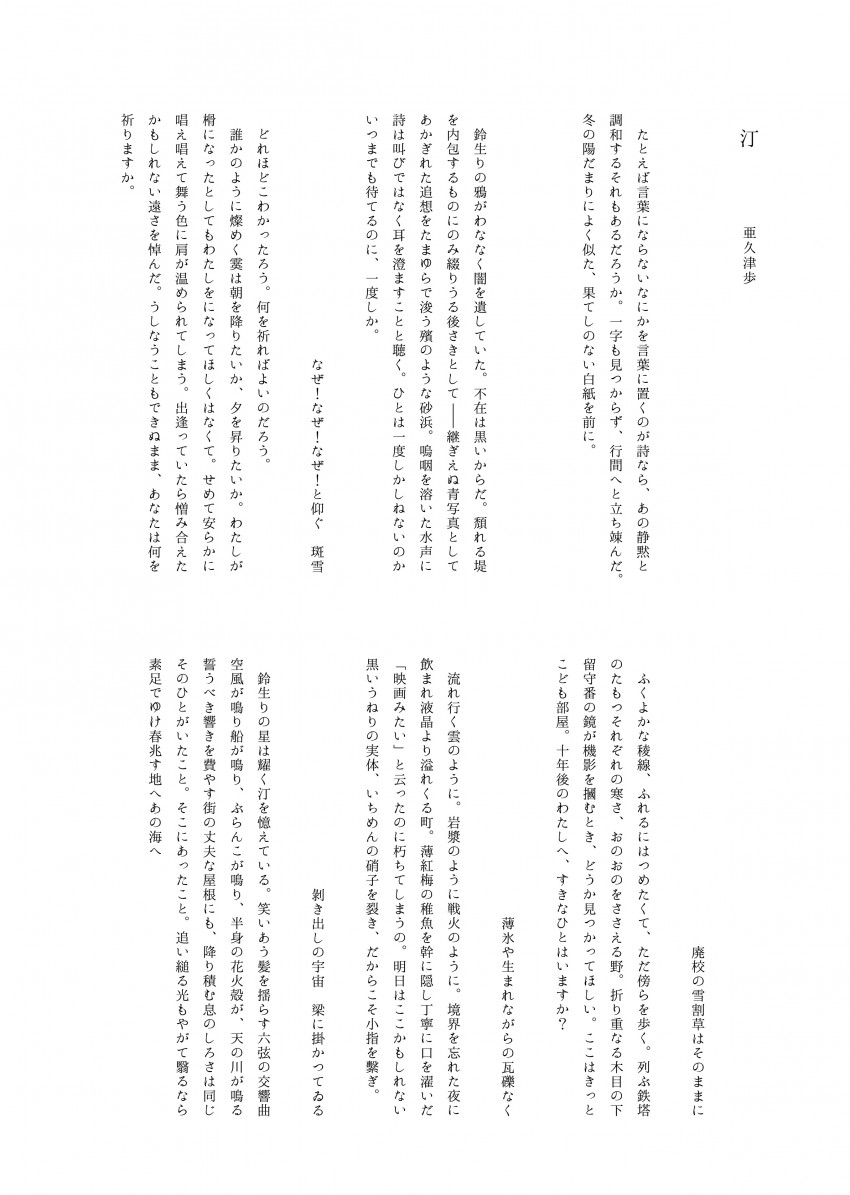汀 亜久津歩
たとえば言葉にならないなにかを言葉に置くのが詩なら、あの静黙と
調和するそれもあるだろうか。一字も見つからず、行間へと立ち竦んだ。
冬の陽だまりによく似た、果てしのない白紙を前に。
鈴生りの鴉がわななく闇を遺していた。不在は黒いからだ。頽れる堤
を内包するものにのみ綴りうる後さきとして――継ぎえぬ青写真として
あかぎれた追想をたまゆらで浚う殯のような砂浜。嗚咽を溶いた水声に
詩は叫びではなく耳を澄ますことと聴く。ひとは一度しかしねないのか
いつまでも待てるのに、一度しか。
なぜ!なぜ!なぜ!と仰ぐ 斑雪
どれほどこわかったろう。何を祈ればよいのだろう。
誰かのように燦めく霙は朝を降りたいか、夕を昇りたいか。わたしが
榾になったとしてもわたしをになってほしくはなくて。せめて安らかに
唱え唱えて舞う色に肩が温められてしまう。出逢っていたら憎み合えた
かもしれない遠さを悼んだ。うしなうこともできぬまま、あなたは何を
祈りますか。
廃校の雪割草はそのままに
ふくよかな稜線、ふれるにはつめたくて、ただ傍らを歩く。列ぶ鉄塔
のたもつそれぞれの寒さ、おのおのをささえる野。折り重なる木目の下
留守番の鏡が機影を摑むとき、どうか見つかってほしい。ここはきっと
こども部屋。十年後のわたしへ、すきなひとはいますか?
薄氷や生まれながらの瓦礫なく
流れ行く雲のように。岩漿のように戦火のように。境界を忘れた夜に
飲まれ液晶より溢れくる町。薄紅梅の稚魚を幹に隠し丁寧に口を濯いだ
「映画みたい」と云ったのに朽ちてしまうの。明日はここかもしれない
黒いうねりの実体、いちめんの硝子を裂き、だからこそ小指を繫ぎ。
剝き出しの宇宙 梁に掛かつてゐる
鈴生りの星は耀く汀を憶えている。笑いあう髪を揺らす六弦の交響曲
空風が鳴り船が鳴り、ぶらんこが鳴り、半身の花火殻が、天の川が鳴る
誓うべき響きを費やす街の丈夫な屋根にも、降り積む息のしろさは同じ
そのひとがいたこと。そこにあったこと。追い縋る光もやがて翳るなら
素足でゆけ春兆す地へあの海へ