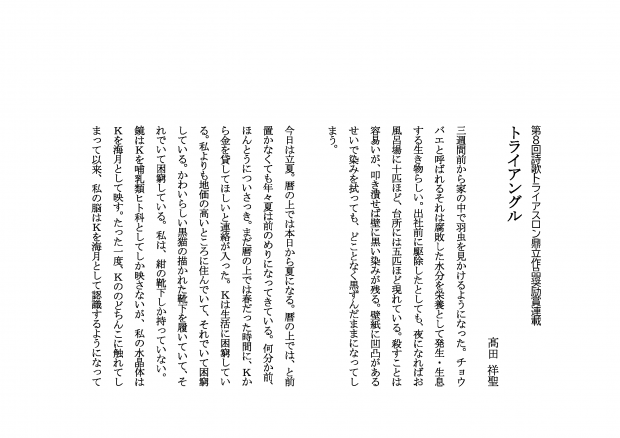
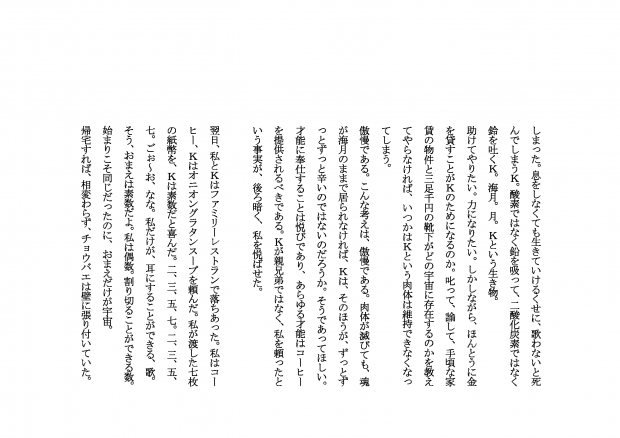
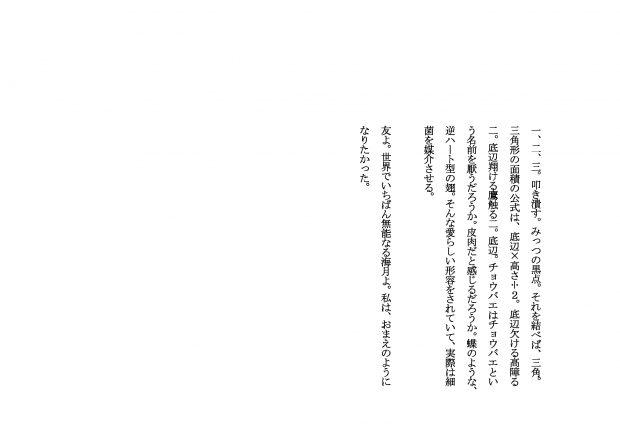
第8回詩歌トライアスロン鼎立作品奨励賞連載
トライアングル 髙田 祥聖
三週間前から家の中で羽虫を見かけるようになった。チョウバエと呼ばれるそれは腐敗した水分を栄養として発生・生息する生き物らしい。出社前に駆除したとしても、夜になればお風呂場に十匹ほど、台所には五匹ほど現れている。殺すことは容易いが、叩き潰せば壁に黒い染みが残る。壁紙に凹凸があるせいで染みを拭っても、どことなく黒ずんだままになってしまう。
今日は立夏。暦の上では本日から夏になる。暦の上では、と前置かなくても年々夏は前のめりになってきている。何分か前、ほんとうについさっき。まだ暦の上では春だった時間に、Kから金を貸してほしいと連絡が入った。Kは生活に困窮している。私よりも地価の高いところに住んでいて、それでいて困窮している。かわいらしい黒猫の描かれた靴下を履いていて、それでいて困窮している。私は、紺の靴下しか持っていない。
鏡はKを哺乳類ヒト科としてしか映さないが、私の水晶体はKを海月として映す。たった一度、Kののどちんこに触れてしまって以来、私の脳はKを海月として認識するようになってしまった。息をしなくても生きていけるくせに、歌わないと死んでしまうK。酸素ではなく鉛を吸って、二酸化炭素ではなく鈴を吐くK。海月。月。Kという生き物。
助けてやりたい。力になりたい。しかしながら、ほんとうに金を貸すことがKのためになるのか。叱って、諭して、手頃な家賃の物件と三足千円の靴下がどの宇宙に存在するのかを教えてやらなければ、いつかはKという肉体は維持できなくなってしまう。
傲慢である。こんな考えは、傲慢である。肉体が滅びても、魂が海月のままで居られなければ、Kは、そのほうが、ずっとずっとずっと辛いのではないのだろうか。そうであってほしい。才能に奉仕することは悦びであり、あらゆる才能はコーヒーを提供されるべきである。Kが親兄弟ではなく、私を頼ったという事実が、後ろ暗く、私を悦ばせた。
翌日、私とKはファミリーレストランで落ちあった。私はコーヒー、Kはオニオングラタンスープを頼んだ。私が渡した七枚の紙幣を、Kは素数だと喜んだ。二、三、五、七。二、三、五、七。ごぉ~お、なな。私だけが、耳にすることができる、歌。そう、おまえは素数だよ。私は偶数。割り切ることができる数。始まりこそ同じだったのに、おまえだけが宇宙。
帰宅すれば、相変わらず、チョウバエは壁に張り付いていた。一、二、三。叩き潰す。みっつの黒点。それを結べば、三角。三角形の面積の公式は、底辺×高さ÷2。底辺欠ける高障る二。底辺翔ける鷹触る二。底辺。チョウバエはチョウバエという名前を厭うだろうか。皮肉だと感じるだろうか。蝶のような、逆ハート型の翅。そんな愛らしい形容をされていて、実際は細菌を媒介させる。
友よ。世界でいちばん無能なる海月よ。私は、おまえのようになりたかった。






