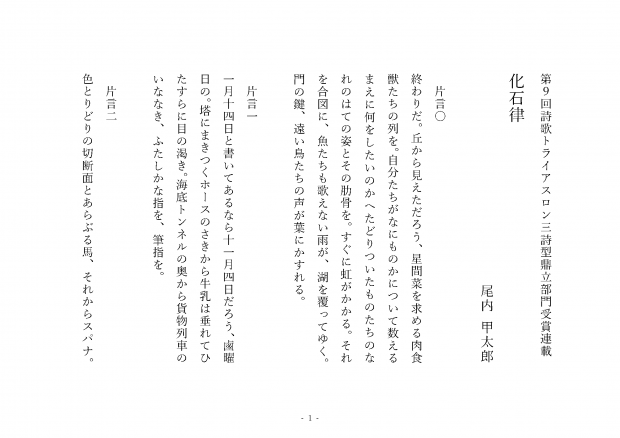
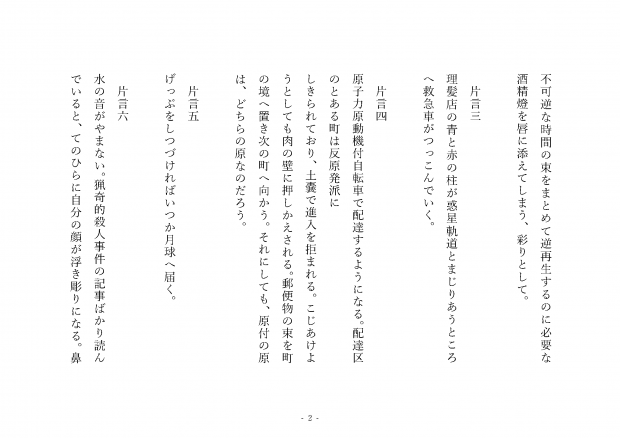
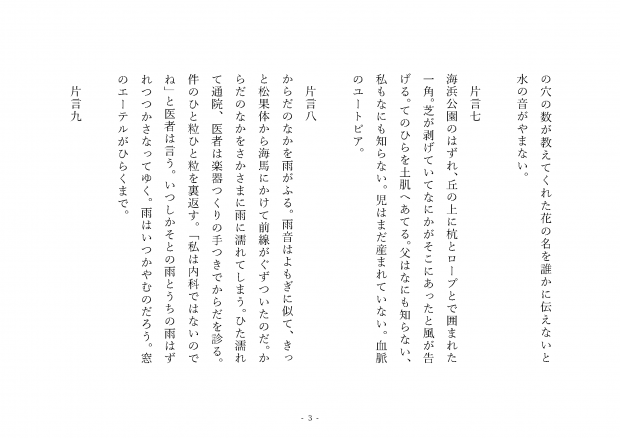
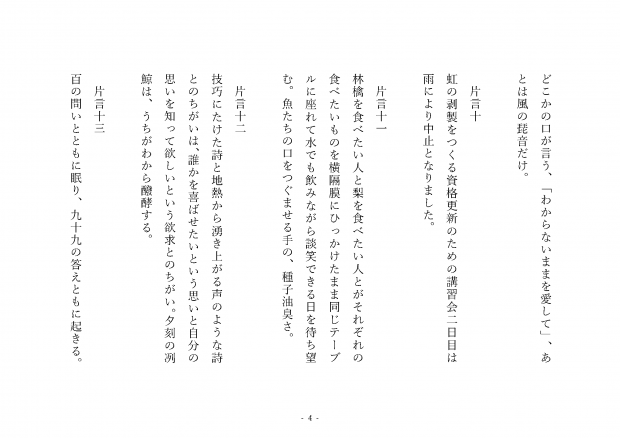
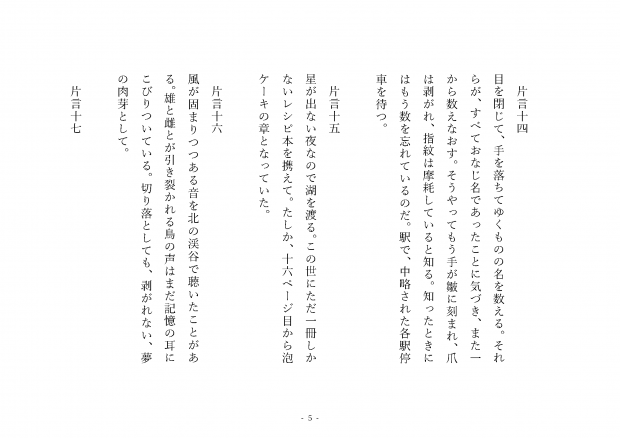
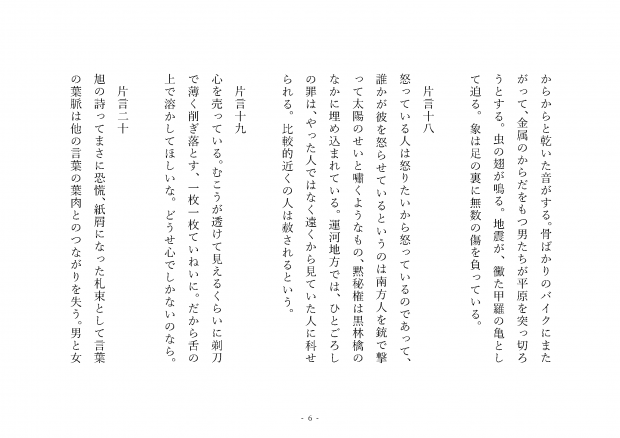
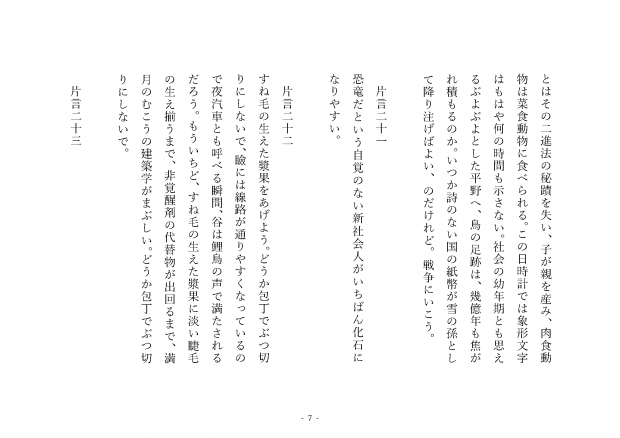
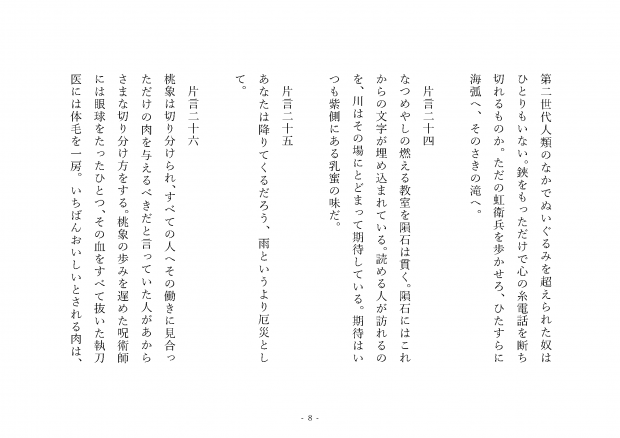
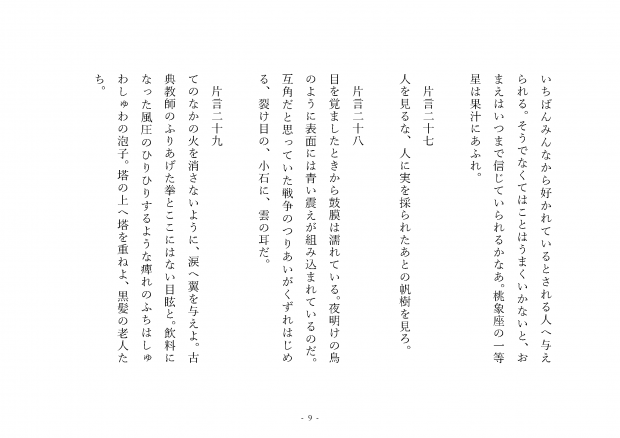
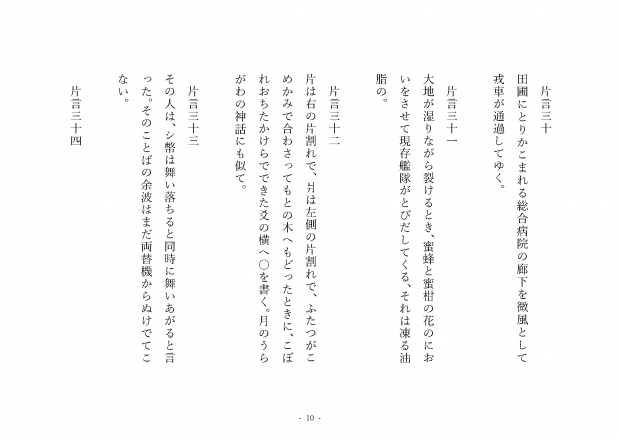
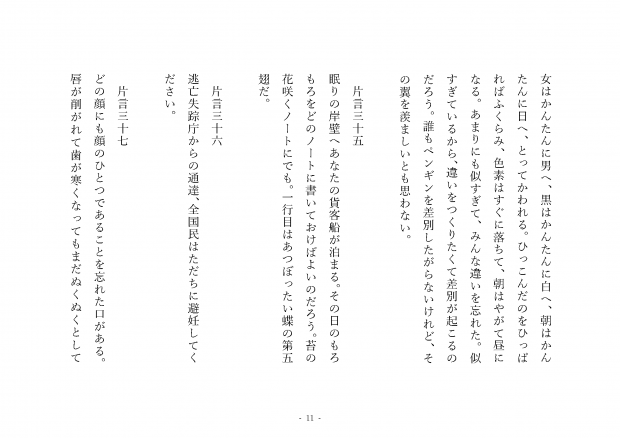
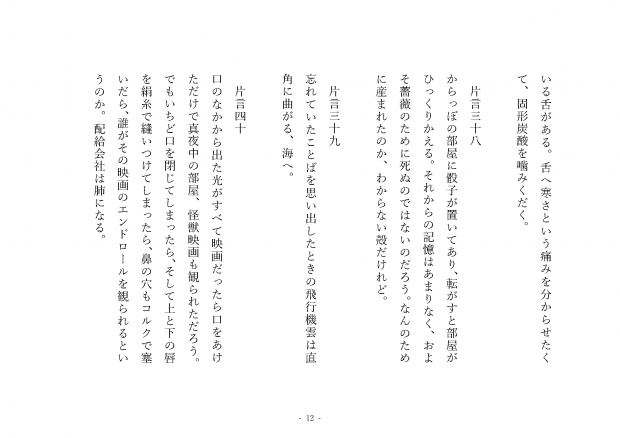
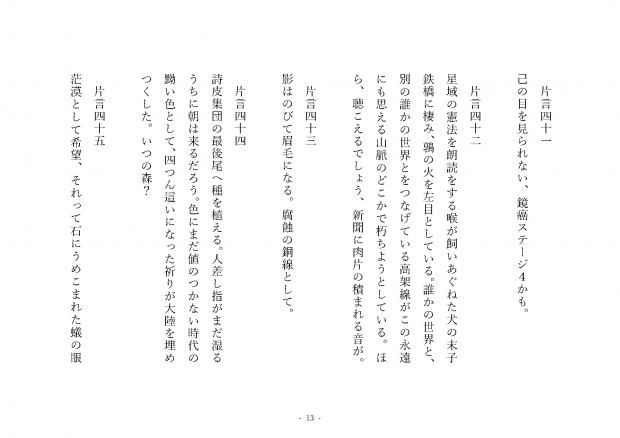
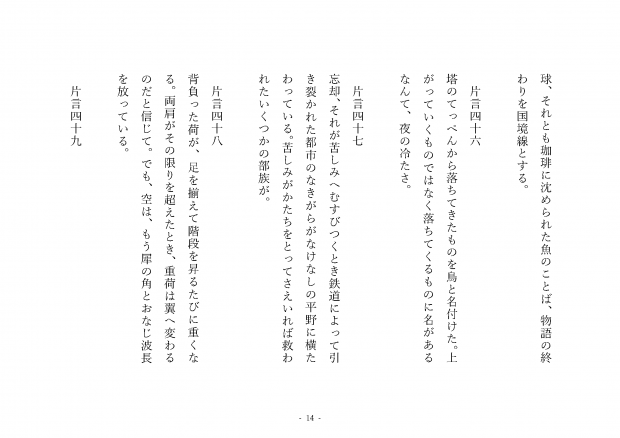
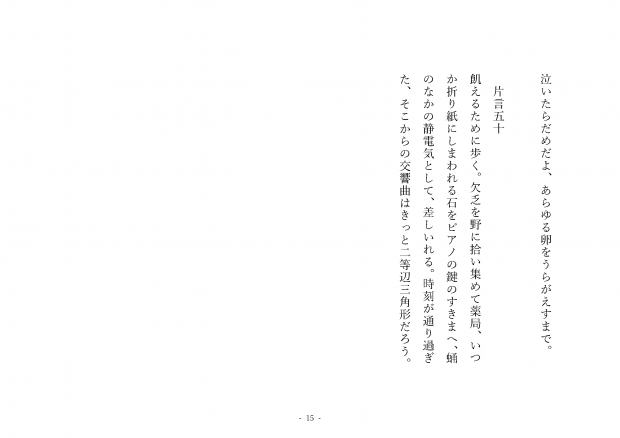
第9回詩歌トライアスロン三詩型鼎立部門受賞連載
化石律
尾内 甲太郎
片言〇
終わりだ。丘から見えただろう、星間菜を求める肉食獣たちの列を。自分たちがなにものかについて数えるまえに何をしたいのかへたどりついたものたちのなれのはての姿とその肋骨を。すぐに虹がかかる。それを合図に、魚たちも歌えない雨が、湖を覆ってゆく。門の鍵、遠い鳥たちの声が葉にかすれる。
片言一
一月十四日と書いてあるなら十一月四日だろう、鹵曜日の。塔にまきつくホースのさきから牛乳は垂れてひたすらに目の渇き。海底トンネルの奥から貨物列車のいななき、ふたしかな指を、筆指を。
片言二
色とりどりの切断面とあらぶる馬、それからスパナ。不可逆な時間の束をまとめて逆再生するのに必要な酒精燈を唇に添えてしまう、彩りとして。
片言三
理髪店の青と赤の柱が惑星軌道とまじりあうところへ救急車がつっこんでいく。
片言四
原子力原動機付自転車で配達するようになる。配達区のとある町は反原発派に
しきられており、土嚢で進入を拒まれる。こじあけようとしても肉の壁に押しかえされる。郵便物の束を町の境へ置き次の町へ向かう。それにしても、原付の原は、どちらの原なのだろう。
片言五
げっぷをしつづければいつか月球へ届く。
片言六
水の音がやまない。猟奇的殺人事件の記事ばかり読んでいると、てのひらに自分の顔が浮き彫りになる。鼻の穴の数が教えてくれた花の名を誰かに伝えないと水の音がやまない。
片言七
海浜公園のはずれ、丘の上に杭とロープとで囲まれた一角。芝が剥げていてなにかがそこにあったと風が告げる。てのひらを土肌へあてる。父はなにも知らない、私もなにも知らない。児はまだ産まれていない。血脈のユートピア。
片言八
からだのなかを雨がふる。雨音はよもぎに似て、きっと松果体から海馬にかけて前線がぐずついたのだ。からだのなかをさかさまに雨に濡れてしまう。ひた濡れて通院、医者は楽器つくりの手つきでからだを診る。件のひと粒ひと粒を裏返す。「私は内科ではないのでね」と医者は言う。いつしかそとの雨とうちの雨はずれつつかさなってゆく。雨はいつかやむのだろう。窓のエーテルがひらくまで。
片言九
どこかの口が言う、「わからないままを愛して」、あとは風の琵音だけ。
片言十
虹の剥製をつくる資格更新のための講習会二日目は雨により中止となりました。
片言十一
林檎を食べたい人と梨を食べたい人とがそれぞれの食べたいものを横隔膜にひっかけたまま同じテーブルに座れて水でも飲みながら談笑できる日を待ち望む。魚たちの口をつぐませる手の、種子油臭さ。
片言十二
技巧にたけた詩と地熱から湧き上がる声のような詩とのちがいは、誰かを喜ばせたいという思いと自分の思いを知って欲しいという欲求とのちがい。夕刻の冽鯨は、うちがわから醱酵する。
片言十三
百の問いとともに眠り、九十九の答えともに起きる。
片言十四
目を閉じて、手を落ちてゆくものの名を数える。それらが、すべておなじ名であったことに気づき、また一から数えなおす。そうやってもう手が皺に刻まれ、爪は剥がれ、指紋は摩耗していると知る。知ったときにはもう数を忘れているのだ。駅で、中略された各駅停車を待つ。
片言十五
星が出ない夜なので湖を渡る。この世にただ一冊しかないレシピ本を携えて。たしか、十六ページ目から泡ケーキの章となっていた。
片言十六
風が固まりつつある音を北の渓谷で聴いたことがある。雄と雌とが引き裂かれる鳥の声はまだ記憶の耳にこびりついている。切り落としても、剥がれない、夢の肉芽として。
片言十七
からからと乾いた音がする。骨ばかりのバイクにまたがって、金属のからだをもつ男たちが平原を突っ切ろうとする。虫の翅が鳴る。地震が、黴た甲羅の亀として迫る。象は足の裏に無数の傷を負っている。
片言十八
怒っている人は怒りたいから怒っているのであって、誰かが彼を怒らせているというのは南方人を銃で撃って太陽のせいと嘯くようなもの、黙秘権は黒林檎のなかに埋め込まれている。運河地方では、ひとごろしの罪は、やった人ではなく遠くから見ていた人に科せられる。比較的近くの人は赦されるという。
片言十九
心を売っている。むこうが透けて見えるくらいに剃刀で薄く削ぎ落とす、一枚一枚ていねいに。だから舌の上で溶かしてほしいな。どうせ心でしかないのなら。
片言二十
旭の詩ってまさに恐慌、紙屑になった札束として言葉の葉脈は他の言葉の葉肉とのつながりを失う。男と女とはその二進法の秘蹟を失い、子が親を産み、肉食動物は菜食動物に食べられる。この日時計では象形文字はもはや何の時間も示さない。社会の幼年期とも思えるぶよぶよとした平野へ、鳥の足跡は、幾億年も焦がれ積もるのか。いつか詩のない国の紙幣が雪の孫として降り注げばよい、のだけれど。戦争にいこう。
片言二十一
恐竜だという自覚のない新社会人がいちばん化石になりやすい。
片言二十二
すね毛の生えた漿果をあげよう。どうか包丁でぶつ切りにしないで、瞼には線路が通りやすくなっているので夜汽車とも呼べる瞬間、谷は鯉鳥の声で満たされるだろう。もういちど、すね毛の生えた漿果に淡い睫毛の生え揃うまで、非覚醒剤の代替物が出回るまで、満月のむこうの建築学がまぶしい。どうか包丁でぶつ切りにしないで。
片言二十三
第二世代人類のなかでぬいぐるみを超えられた奴はひとりもいない。鋏をもっただけで心の糸電話を断ち切れるものか。ただの虹衛兵を歩かせろ、ひたすらに海弧へ、そのさきの滝へ。
片言二十四
なつめやしの燃える教室を隕石は貫く。隕石にはこれからの文字が埋め込まれている。読める人が訪れるのを、川はその場にとどまって期待している。期待はいつも紫側にある乳蜜の味だ。
片言二十五
あなたは降りてくるだろう、雨というより厄災として。
片言二十六
桃象は切り分けられ、すべての人へその働きに見合っただけの肉を与えるべきだと言っていた人があからさまな切り分け方をする。桃象の歩みを遅めた呪術師には眼球をたったひとつ、その血をすべて抜いた執刀医には体毛を一房。いちばんおいしいとされる肉は、いちばんみんなから好かれているとされる人へ与えられる。そうでなくてはことはうまくいかないと、おまえはいつまで信じていられるかなあ。桃象座の一等星は果汁にあふれ。
片言二十七
人を見るな、人に実を採られたあとの帆樹を見ろ。
片言二十八
目を覚ましたときから鼓膜は濡れている。夜明けの鳥のように表面には青い震えが組み込まれているのだ。互角だと思っていた戦争のつりあいがくずれはじめる、裂け目の、小石に、雲の耳だ。
片言二十九
てのなかの火を消さないように、涙へ翼を与えよ。古典教師のふりあげた拳とここにはない目眩と。飲料になった風圧のひりひりするような痺れのふちはしゅわしゅわの泡子。塔の上へ塔を重ねよ、黒髪の老人たち。
片言三十
田圃にとりかこまれる総合病院の廊下を微風として戎車が通過してゆく。
片言三十一
大地が湿りながら裂けるとき、蜜蜂と蜜柑の花のにおいをさせて現存艦隊がとびだしてくる、それは凍る油脂の。
片言三十二
片は右の片割れで、爿は左側の片割れで、ふたつがこめかみで合わさってもとの木へもどったときに、こぼれおちたかけらでできた爻の横へ○を書く。月のうらがわの神話にも似て。
片言三十三
その人は、シ幣は舞い落ちると同時に舞いあがると言った。そのことばの余波はまだ両替機からぬけでてこない。
片言三十四
女はかんたんに男へ、黒はかんたんに白へ、朝はかんたんに日へ、とってかわれる。ひっこんだのをひっぱればふくらみ、色素はすぐに落ちて、朝はやがて昼になる。あまりにも似すぎて、みんな違いを忘れた。似すぎているから、違いをつくりたくて差別が起こるのだろう。誰もペンギンを差別したがらないけれど、その翼を羨ましいとも思わない。
片言三十五
眠りの岸壁へあなたの貨客船が泊まる。その日のもろもろをどのノートに書いておけばよいのだろう。苔の花咲くノートにでも。一行目はあつぼったい蝶の第五翅だ。
片言三十六
逃亡失踪庁からの通達、全国民はただちに避妊してください。
片言三十七
どの顔にも顔のひとつであることを忘れた口がある。唇が削がれて歯が寒くなってもまだぬくぬくとしている舌がある。舌へ寒さという痛みを分からせたくて、固形炭酸を噛みくだく。
片言三十八
からっぽの部屋に骰子が置いてあり、転がすと部屋がひっくりかえる。それからの記憶はあまりなく、およそ薔薇のために死ぬのではないのだろう。なんのために産まれたのか、わからない殻だけれど。
片言三十九
忘れていたことばを思い出したときの飛行機雲は直角に曲がる、海へ。
片言四十
口のなかから出た光がすべて映画だったら口をあけただけで真夜中の部屋、怪獣映画も観られただろう。でもいちど口を閉じてしまったら、そして上と下の唇を絹糸で縫いつけてしまったら、鼻の穴もコルクで塞いだら、誰がその映画のエンドロールを観られるというのか。配給会社は肺になる。
片言四十一
己の目を見られない、鏡癌ステージ4かも。
片言四十二
星域の憲法を朗読をする喉が飼いあぐねた犬の末子鉄橋に棲み、鶉の火を左目としている。誰かの世界と、別の誰かの世界とをつなげている高架線がこの永遠にも思える山脈のどこかで朽ちようとしている。ほら、聴こえるでしょう、新聞に肉片の積まれる音が。
片言四十三
影はのびて眉毛になる。腐蝕の銅線として。
片言四十四
詩皮集団の最後尾へ種を植える。人差し指がまだ湿るうちに朝は来るだろう。色にまだ値のつかない時代の黝い色として、四つん這いになった祈りが大陸を埋めつくした。いつの森?
片言四十五
茫漠として希望、それって石にうめこまれた蟻の眼球、それとも珈琲に沈められた魚のことば、物語の終わりを国境線とする。
片言四十六
塔のてっぺんから落ちてきたものを鳥と名付けた。上がっていくものではなく落ちてくるものに名があるなんて、夜の冷たさ。
片言四十七
忘却、それが苦しみへむすびつくとき鉄道によって引き裂かれた都市のなきがらがなけなしの平野に横たわっている。苦しみがかたちをとってさえいれば救われたいくつかの部族が。
片言四十八
背負った荷が、足を揃えて階段を昇るたびに重くなる。両肩がその限りを超えたとき、重荷は翼へ変わるのだと信じて。でも、空は、もう犀の角とおなじ波長を放っている。
片言四十九
泣いたらだめだよ、あらゆる卵をうらがえすまで。
片言五十
飢えるために歩く。欠乏を野に拾い集めて薬局、いつか折り紙にしまわれる石をピアノの鍵のすきまへ、蛹のなかの静電気として、差しいれる。時刻が通り過ぎた、そこからの交響曲はきっと二等辺三角形だろう。





