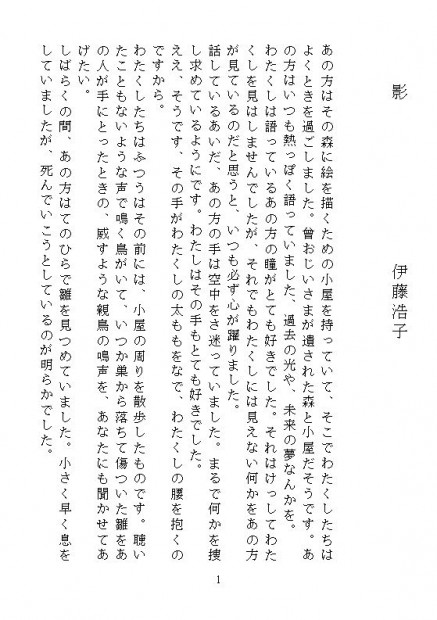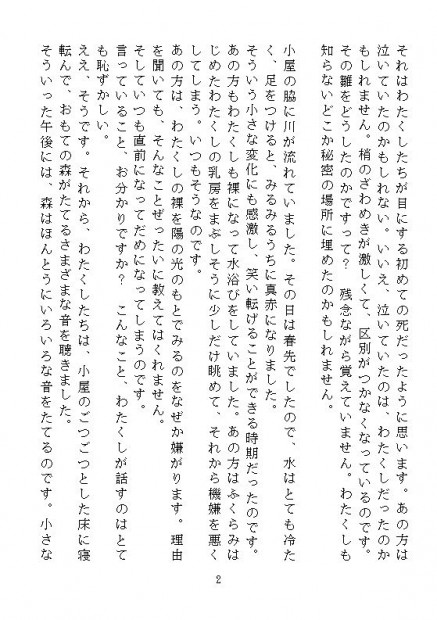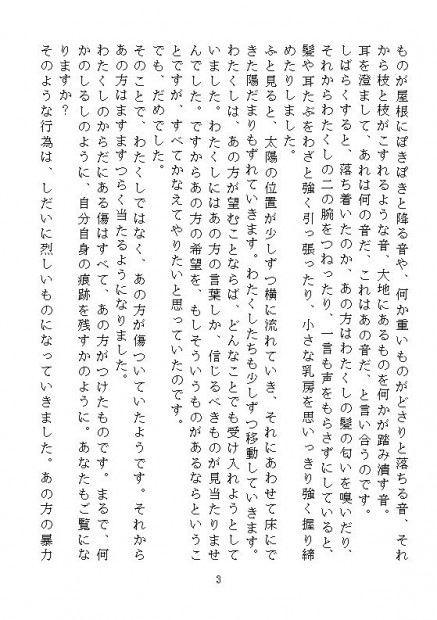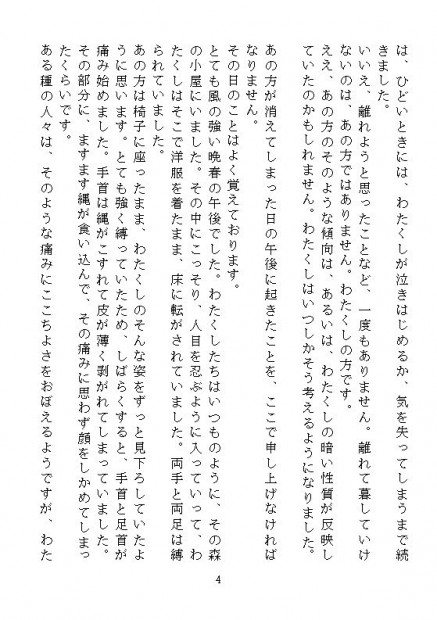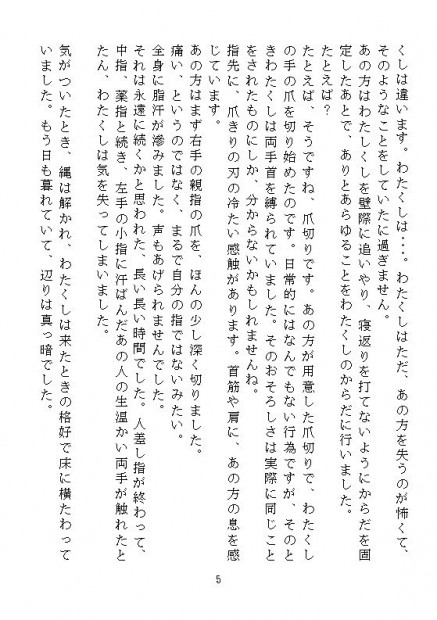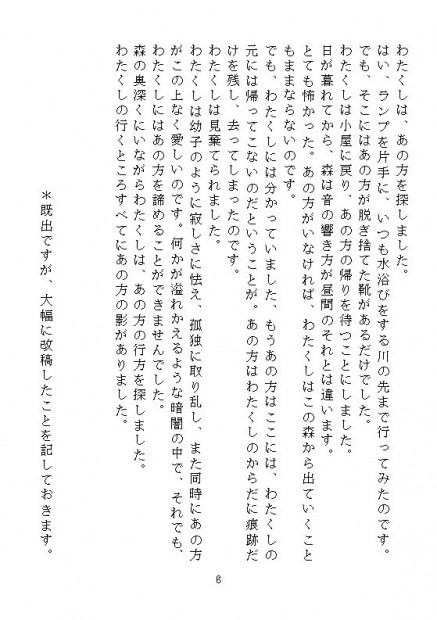影 伊藤浩子
あの方はその森に絵を描くための小屋を持っていて、そこでわたくしたちはよくときを過ごしました。曾おじいさまが遺された森と小屋だそうです。あの方はいつも熱っぽく語っていました、過去の光や、未来の夢なんかを。
わたくしは語っているあの方の瞳がとても好きでした。それはけっしてわたくしを見はしませんでしたが、それでもわたくしには見えない何かをあの方が見ているのだと思うと、いつも必ず心が躍りました。
話しているあいだ、あの方の手は空中をさ迷っていました。まるで何かを捜し求めているようにです。わたしはその手もとても好きでした。
ええ、そうです、その手がわたくしの太ももをなで、わたくしの腰を抱くのですから。
わたくしたちはふつうはその前には、小屋の周りを散歩したものです。聴いたこともないような声で鳴く鳥がいて、いつか巣から落ちて傷ついた雛をあの人が手にとったときの、威すような親鳥の鳴声を、あなたにも聞かせてあげたい。
しばらくの間、あの方はてのひらで雛を見つめていました。小さく早く息をしていましたが、死んでいこうとしているのが明らかでした。
それはわたくしたちが目にする初めての死だったように思います。あの方は泣いていたのかもしれない。いいえ、泣いていたのは、わたくしだったのかもしれません。梢のざわめきが激しくて、区別がつかなくなっているのです。
その雛をどうしたのかですって? 残念ながら覚えていません。わたくしも知らないどこか秘密の場所に埋めたのかもしれません。
小屋の脇に川が流れていました。その日は春先でしたので、水はとても冷たく、足をつけると、みるみるうちに真赤になりました。
そういう小さな変化にも感激し、笑い転げることができる時期だったのです。
あの方もわたくしも裸になって水浴びをしていました。あの方はふくらみはじめたわたくしの乳房をまぶしそうに少しだけ眺めて、それから機嫌を悪くしてしまう。いつもそうなのです。
あの方は、わたくしの裸を陽の光のもとでみるのをなぜか嫌がります。理由を聞いても、そんなことぜったいに教えてはくれません。
そしていつも直前になってだめになってしまうのです。
言っていること、お分かりですか? こんなこと、わたくしが話すのはとても恥ずかしい。
ええ、そうです。それから、わたくしたちは、小屋のごつごつとした床に寝転んで、おもての森がたてるさまざまな音を聴きました。
そういった午後には、森はほんとうにいろいろな音をたてるのです。小さなものが屋根にぽきぽきと降る音や、何か重いものがどさりと落ちる音、それから枝と枝がこすれるような音、大地にあるものを何かが踏み潰す音。
耳を澄まして、あれは何の音だ、これはあの音だ、と言い合うのです。
しばらくすると、落ち着いたのか、あの方はわたくしの髪の匂いを嗅いだり、それからわたくしの二の腕をつねったり、一言も声をもらさずにしていると、髪や耳たぶをわざと強く引っ張ったり、小さな乳房を思いっきり強く握り締めたりしました。
ふと見ると、太陽の位置が少しずつ横に流れていき、それにあわせて床にできた陽だまりもずれていきます。わたくしたちも少しずつ移動していきます。
わたくしは、あの方が望むことならば、どんなことでも受け入れようとしていました。わたくしにはあの方の言葉しか、信じるべきものが見当たりませんでした。ですからあの方の希望を、もしそういうものがあるならということですが、すべてかなえてやりたいと思っていたのです。
でも、だめでした。
そのことで、わたくしではなく、あの方が傷ついていたようです。それからあの方はますますつらく当たるようになりました。
わたくしのからだにある傷はすべて、あの方がつけたものです。まるで、何かのしるしのように、自分自身の痕跡を残すかのように。あなたもご覧になりますか?
そのような行為は、しだいに烈しいものになっていきました。あの方の暴力は、ひどいときには、わたくしが泣きはじめるか、気を失ってしまうまで続きました。
いいえ、離れようと思ったことなど、一度もありません。離れて暮していけないのは、あの方ではありません。わたくしの方です。
ええ、あの方のそのような傾向は、あるいは、わたくしの暗い性質が反映していたのかもしれません。わたくしはいつしかそう考えるようになりました。
あの方が消えてしまった日の午後に起きたことを、ここで申し上げなければなりません。
その日のことはよく覚えております。
とても風の強い晩春の午後でした。わたくしたちはいつものように、その森の小屋にいました。その中にこっそり、人目を忍ぶように入っていって、わたくしはそこで洋服を着たまま、床に転がされていました。両手と両足は縛られていました。
あの方は椅子に座ったまま、わたくしのそんな姿をずっと見下ろしていたように思います。とても強く縛っていたため、しばらくすると、手首と足首が痛み始めました。手首は縄がこすれて皮が薄く剥がれてしまっていました。その部分に、ますます縄が食い込んで、その痛みに思わず顔をしかめてしまったくらいです。
ある種の人々は、そのような痛みにここちよさをおぼえるようですが、わたくしは違います。わたくしは・・・。わたくしはただ、あの方を失うのが怖くて、そのようなことをしていたに過ぎません。
あの方はわたしくしを壁際に追いやり、寝返りを打てないようにからだを固定したあとで、ありとあらゆることをわたくしのからだに行いました。
たとえば?
たとえば、そうですね、爪切りです。あの方が用意した爪切りで、わたくしの手の爪を切り始めたのです。日常的にはなんでもない行為ですが、そのときわたくしは両手首を縛られていました。そのおそろしさは実際に同じことをされたものにしか、分からないかもしれませんね。
指先に、爪きりの刃の冷たい感触があります。首筋や肩に、あの方の息を感じています。
あの方はまず右手の親指の爪を、ほんの少し深く切りました。
痛い、というのではなく、まるで自分の指ではないみたい。
全身に脂汗が滲みました。声もあげられませんでした。
それは永遠に続くかと思われた、長い長い時間でした。人差し指が終わって、中指、薬指と続き、左手の小指に汗ばんだあの人の生温かい両手が触れたとたん、わたくしは気を失ってしまいました。
気がついたとき、縄は解かれ、わたくしは来たときの格好で床に横たわっていました。もう日も暮れていて、辺りは真っ暗でした。
わたくしは、あの方を探しました。
はい、ランプを片手に、いつも水浴びをする川の先まで行ってみたのです。でも、そこにはあの方が脱ぎ捨てた靴があるだけでした。
わたくしは小屋に戻り、あの方の帰りを待つことにしました。
日が暮れてから、森は音の響き方が昼間のそれとは違います。
とても怖かった。あの方がいなければ、わたくしはこの森から出ていくこともままならないのです。
でも、わたくしには分かっていました、もうあの方はここには、わたくしの元には帰ってこないのだということが。あの方はわたくしのからだに痕跡だけを残し、去ってしまったのです。
わたくしは見棄てられました。
わたくしは幼子のように寂しさに怯え、孤独に取り乱し、また同時にあの方がこの上なく愛しいのです。何かが溢れかえるような暗闇の中で、それでも、わたくしにはあの方を諦めることができませんでした。
森の奥深くにいながらわたくしは、あの方の行方を探しました。
わたくしの行くところすべてにあの方の影がありました。
*既出ですが、大幅に改稿したことを記しておきます。