というわけで「超新撰21」(邑書林)。この一冊に、果たしてどのように斬り込んでい
こうか‥‥と考え、そしてそれは「この一冊は、僕にどのように斬り込んでくるのか」と
同義であることに気づかされた。つまり、参加者だけでなく読者もまた、俳句作家として
の姿勢を質される、試される一冊であるということだ。
その思いを些かなりの基調として、この一冊あらためてじっくりと読ませていただいた。
種田スガル「ザ・ヘイブン」
賛否両論。様々な話題を呼んだ100句であるが、僕的には多くの作品において「言葉
が鎧になってしまっている。閉じてしまっている」印象を受けた。こんなに饒舌なのに、
もうひとつ種田氏の生身が伝わってこないもどかしさがある。
ただ、「脆いから熟れうる あなたが触れて萎える」の「熟れうる」であるとか、「寝こ
ろび星のみ摘み取る」「どこまでいけば美味」「心地よい右斜め後ろ」など、 斬新なフレー
ズも散見される。
「ハイエナのジレンマに 現地の女連れ込む」の「現地の女連れ込む」という展開 はすこ
ぶる痛快、パワフル。意味を超えたところで十分楽しめた。「結合の相性で決まるペンギン
の飛距離」これはセックス関連の句として読んだが(そんなのひょっとして僕だけか?)、
ペンギンというメタファーの違和感が逆に面白かった。
小川楓子「芹の部屋」
作句信条に「私たち生者と古よりの死者たちがときに寄り添い、解け合ってはまた離れ
てゆく港を思って」とある。「清明に生れてみどりの踵持つ」「清明に死してわたしと隣り
合ふ」確かに小川氏の誕生日は清明の頃、4月3日。自らの生と、太古からの数限りなき
生と死、その繋がりを形にしていこうという作句者としての真摯な思い。末尾の一句「そ
してみな芹の部屋にてまどろみぬ」の「みな」には、きっと数多の死者も含まれているのだろう。
また、「あふれさうな臓器抱へてみどりの日」「青霧は灼ける手足のなかにある」「まんじ
ゆしやげひらくあしのゆびひらく」「わが産みし鯨と思ふまで青む」「耳たぶの穴白藤のひ
とねむり」「笛吹いて十一月の白いくち」(「くち」という平仮名表記が効果的)など、独特
の肉体感覚、森羅万象との独特の遊び方に惹かれる。
大谷弘至「極楽」
大谷氏は現在32歳。昨年より俳句雑誌「古志」の新主宰となった。一句目「波寄 せて
詩歌の国や大旦」は俳句作家としてのひとつの「選手宣誓」であろう。俳句への 意気が垣
間見えて爽やか。「大旦」が佳い。
「蝉の穴まばゆき朝の来てゐたり」は斬新なアングル。蝉穴を穴の内側から表現した句
は珍しいのでは?
その他「菜の花や生まれかはりてこの星に」の壮大なロマン。「血をわけし一匹の蚊と冬
ごもり」の諧謔に共鳴。「水揺れてすなはちそこに初蛙」「烏瓜烏にもつてゆかれけり」「大
文字のなごりの風やけさの風」「われら住む家を映して水澄めり」などの素朴さもまた。
篠崎央子「鴨の横顔」
「愛深し水になりたるソーダ水」惹かれた一句。愛し合っている時間の経過か、それと
も水になってもソーダ水を愛し続けるということか。鑑賞がふくらむ。
また、「枯芝に身を擦る猫や失業す」「白藤の花ざわめきて無職なり」「麦笛に犬の振り向
く職探し」「瓜の種ていねいに削ぎ天職なし」など、「職」というモチーフ の捉え方に滋味あり。
「ビアガーデン飛ばされさうなピザの来る」「月赤し都会は捨てるもの多き」「銀蠅や早
送りするラブシーン」の現代性、「ペンギンの腹から進む立夏かな」「残暑か な黄身の染み
出す割れ卵」「洗ひ髪一升酒を抱へ来る」「もんじや焼の土手を崩しぬ 花粉症」の映像セン
スにも注目。
田島健一「記録しんじつ」
「記録しんじつ」というタイトル。現実をどうリアルに捉えるか。一歩先の俳句を 模索
している。作句信条の「私の制御できない〈痙攣〉。それでも、確かに私であるところの」
という一節に感じ入った。
「餅肌や見えない滝で充ちている」見た感じであるとか、触感であるとか(まあね)、「餅肌
」というものの瑞々しさを斬新な表現で描く中七下五。「忠実な嫁の嫁菜の 読めない愛」
「蟻が蟻越え銀行が痩せてゆく」「神山君の家葱を売る靴も売る」「梟や息のおわりのきれ
いな詩」など、言葉が自由自在で巧み。
「接吻のまま導かれ蝌蚪の国」「新緑や全国犀の角協会」「白鳥定食いつまでも聲かがや
くよ」奇抜にして詩情溢れる句群。共鳴句が多かった。
明隅礼子「みづのほとり」
「しやぼん玉はじめ遠くへ行くつもり」しゃぼん玉というもの、瑞々しさと儚さの飽和
点という印象を持っていたが、まさにそのあたりを見事におさえている。
他にも、「春の野になかなか着かぬピエロかな」「文字のなき絵本をひらく日永かな」「草
笛の音をかさねて深き空」の世界の柔らかな捉え方、「子のことばあふれて春の川となり」
「吾子抱きて遠くがまぶし桐の花」「子を追つて蟻の国まで来てしまふ」の母としての佇ま
い、立ち止まり方に惹かれた。
D.J.リンズィー「涅槃の浪」
豪州生まれ。深海生物を研究。「事実よりも真実を捉えていきたい」との作句信条。「異
人我れ陽炎を摑みつつある掌」は俳句作家としての自分自身を詠んだ句ではないだろうか。
「カブトガニ上陸の夜を火星燃ゆ」「鮟鱇の貌へ銀河のひとすぢ来る」「貸してよとすぐ
に手が出るオワンクラゲ」「リュックサックに寝袋詰めてウリクラゲ」「海蛇の長き一息梅
雨に入る」など、海洋学者としてのスキル、センスがいかんなく発揮された句群。中でも
「肛門が口山頭火忌のイソギンチャク」、イソギンチャクの性質を、山頭火の生きざま、キ
ャラと配合。面白い!
牛田修嗣「千夜一夜」
作句信条に「俳句に出会うまでは挫折ばかりの人生でした。俳句に出会ったことで命を
救われたといっても過言ではありません。(中略)俳句を通して幸せを得たい、そして幸せ
を贈りたい、ただそれのみです」とある。お写真の朗らかさと共に印象に残った。
素朴なストレートな作風の句が並ぶ。「渦となる潮の力年立ちぬ」「まだ色を明か さぬ莟
チューリップ」「水辺の恋人たちのため日永」「その翼呉れよ五月を飛ばぬ鳩」「目ひらけば
星目つむれば秋の声」など、生きている喜び、煌めきに満ちている句群。 「噴水にガリバ
ーのとき小人のとき」は特に惹かれた一句。噴水の楽しさ、ファンタジー性を見事に演出。
榮猿丸「バック・シート」
非凡なエンターテイメント性を感じた。言葉選びの鋭さ、そして安定感。
「さへづりや電球の尻太き螺子」「愛されずしてTシャツは寝間着になる」「写真部部室
映画部寄生さるすべり」「欄干摑めば指輪ひびきぬ夏の河」「冬麗や二十世紀の千の椅子」
「スターリンも靴屋の息子花八つ手」「ゴッホ鬱ゴーギャン躁や枯木に月」など、フレーズ
の切れ味と季語の妙で、ぐいぐいと読ませる。
また、「蜜厚く大学芋や胡麻うごく」「若芝に引く白線の起伏かな」「かたつむり 肉出で
て貌あらはるる」「指の肉照る箱庭に灯を入れて」など、鮮やかに立ち上がってくる質感。
映像作家的資質も十分に感じられる。
小野裕三「龍の仕組み」
「俳句に向き合う時、いつも〈日本〉ということを考える。この国が受け継ぐ文化や社
会のいい面も悪い面も、きちんと見つめていきたい」という作句信条の一節。
「この海の黙約われら被爆国」「月光のやがて聖徳太子かな」「空耳が金閣寺にも ありに
けり」「春の夜のテールランプと民主主義」「侍をたくさん噴いて弥生山」な ど、小野氏の
「日本」をモチーフにした句の感覚の豊かさ、詩情を再認識。中でも「月光の‥‥」は以
前初めて目にした時、こうしたグルーヴ感が五七五で出せるんだ、と驚嘆した思い出がある。
その他、「冬帽よわたくしの好きな体温」「ストローを愛したように私を愛す」「玉葱を切
っても切っても青い鳥」「高きに登る具体的には犬」「燕帰る長き名前の 挑戦者」など、魅力さまざま。
山田耕司「風袋抄」
作句信条の「俳句作家とは、自己の作品の不連続に耐える者」という一文にいたく共感
した。凄いフレーズだ‥‥。
「手をひつぱる鬼は夕焼け色だつた」「戦争や殻のくらさに黄身浮かび」「降る花 を母と
思はばのど仏」「春泥に贔屓の穴を作りけり」「箸を逃げ骨に春昼あかるけれ」「墓をさへぎ
る墓をさへぎる櫻かな」「眠き夢なり月見草まで這ふ夢なり」などの作品、日本語が本来持
つエロスと美、そして死生観が浮き彫りになる。その緊迫感。
また、「友の忌の蚊柱なれば浴びにけり」「茄子に臍彫りて不孝をわびにけり」「狼 に降
る雪と決め舌を出す」「雪の野に雪降り乳房線で描き」といった感情・感傷の出し方の微妙
な捻れに興味をひかれた。
男波弘志「印契集」
「桃咲くやまだ歯の生えぬ母とゐて」の時間の麗しい超越、「チョークで描くなが き棺
や冬の蜂」の複雑な哀感、静けさが印象的。
また、「乳房もて秋の螢を囲みけり」「蟋蟀や女体にて水呑み終る」「膝立てて立ち上ると
き身籠りぬ」「腸の中にも真砂冬銀河」「どの骨の隙間にも海見えてあり」 など、この作者
も独特の肉体感覚あり。魅せられる。
その他、「鰺の群れ色を変へたる涅槃かな」「百遍死にまう一度死ぬ泉かな」「水葬といふ
一冊の本がある」に共鳴。
青山茂根「白きガルーダ」
「ひとつづつ衣服を脱ぎて兎追ふ」兎の存在、兎を追うことによって、自らがだん だん
裸になってゆく感覚。
「ふらここを軛(くびき)の重さとも知らず」「纏足(てんそく)を包むバナナの皮であ
り」「バビロンへ行かう風信子咲いたなら」「夜濯(よすすぎ)に火星のやうな下着かな」
「雛壇の裏の奈落に気づかざる」など、日常の何気ないものから異世界 へのいきなりの飛
躍が興味深い。面白い。
そして、様々な俳句の旅のあと、最後の句「最果ての地にも蒲団の干されけり」であら
ためて「生活」に思いを寄せるところが好ましかった。
杉山久子「光」
「一句の中にかなしみやおかしみがうっすらと光を湛えて横たわっているような、そん
な句を詠めたら」と作句信条。
100句、とても柔らかい。そして実が詰まっている。
「うぐひすに裁かれたくもある日かな」「うぐひすの喉のてざはり死のてざはり」鴬とい
う、ひとつの「シンボル」に自らを託し、また死を感じるという流れ、とても 共感できた。
他にも、「しやぼん玉雀映してこはれけり」「跳箱の内のくらがり桃の花」「ねむりても猫
の尾ゆるる天の川」「立春の水際を歩く鳥と歩く」「ひとつぶの星へ舟虫はしりけり」など。
佐藤成之「光棲む国」
「鉄棒に西日が首を吊っている」「雨上がる薔薇の血抜きも終えしころ」「長き夜 に鋏を
入れて溺愛す」「かあさんはぼくのぬけがらななかまど」「夕焼を煮詰めてみれば夷狄の血」
など、シュールな感覚。生々しいファンタジー性というべきか。
また、「陽炎はいま恋人になるところ」の青春性、「春の虹サンドイッチを飛び出せり」
「紫陽花にまだ未使用の恋がある」「戦力外通知鮑のこりこりと」など、視点と表現の面白
さに注目した。
「悲しみのあるいは背骨天の川」は上五中七の措辞が胸に刺さってくるような‥‥。強
い印象を残す一句。好きな一句。
久野雅樹「バベルの塔」
「俳句という幸せの器」と久野氏。「子に語る脳は紫陽花ほどなると」「花の下の 下象が
ゐて亀がゐて」「絵日記のラムネの泡のおびただし」「花火見るみな正面と思ひゐし」「七夕
の竹に星めく点字かな」など、良き明るさの作品群。
とりわけ「バカボンもカツオも浴衣着て眠る」の幸福感。この句にはまず爆笑させられ
たし(この一冊の中の僕の共鳴句ベスト10に絶対入る)、子供達への讃歌、素 晴らしい
「昭和」讃歌とも思えた。
小沢麻結「花蜜柑」
「結婚も良いかも春の動物園」「夏見舞会ひたくなつてしまひけり」「大寒や母の ビーフ・
シチューが待つ」「チョコレート回つてきたる夜業かな」などの素朴な柔らかな日常詠。そ
んな中に「木の実降る音と信じて振り向かず」「たんぽぽ黄吾を苦しめてゐしは吾」「狐火
の揺るるここから一人行け」といった厳しさ、芯の強さもある。
「葉桜や眩しげに訳聞かれたる」「葉桜やネクタイ緩めても似合ふ」の二句、葉桜な らで
はの煌めきをうまく捉えていると思う。
上田信治「上と下」
「火を焚いて砂浜の名が分らない」「絨緞に文鳥のゐてまだ午前」「水洟の人電球 を買ひ
にけり」「風船はいまスリッパに載つてをる」「家よりも大きな雲や瓜の花」 などの作品、
平明な語り口の中に日常感の佳き味わい。
超新撰21竟宴シンポジウムでの上田氏の発言、『(高野)素十もね、「何にも言ってな
ーい!」って全部どけちゃったあとに、うっすら感情が出るみたいなのがあって、その薄
さが最近気に入っているところなんですけど』を思い出す。
中でも「椎茸や人に心のひとつゞつ」は特に印象に残った句のひとつ。何気ないんだけ
ど、その何気なさがいい感じで響いてくる。椎茸のあのしみじみとした味わいが、こんな
風に活かされるとは。
小川軽舟「ラララ」
「夜へ」の醸す余韻が素晴らしい「水たまり踏んでくちなし匂ふ夜へ」から始まって、
「マフラーに星の匂ひをつけて来し」「春待つや鈴ともならず松ぼくり」「雪女 鉄瓶の湯の
練れてきし」「蘆原にいま見ゆるものすべて音」「泥に降る雪うつくしや泥になる」「死ぬと
きは箸置くやうに草の花」など、格調高く、詩情溢れる句が並ぶ。
「季語の力」の巧みな引き出し方に何度となく唸らされた。
また、「五分後の地球も青しあめんばう」「灯火親し英語話せる火星人」といった 奇抜な
発想も小川氏の持ち味のひとつ。
柴田千晶「モンスター」
「からつぽの子宮明るし水母踏む」「葡萄滲むシーツの裏に千の夜」「まはされて銀漢と
なる軀かな」「内腿に触れし冷たき耳ふたつ」といった赤裸々なエロス表現に インパクト
あり。「円山町に飛雪私はモンスター」の一句、まさに園子温監督『恋の罪』の世界観を先
取り。鬼気迫る。
また、生家、父母を詠んだ句群の切迫感。「首吊りの木に柿実る生家かな」「猫に 餌投げ
つけし母冬満月」「徘徊の父と無月の庭に立つ」「凍晴の廊下来て父失禁す」「冬川のごとし
繋がれ眠る父」「げんげ田に煙の父の立ちにけり」。そして「春風やこの世に紛れ父咳す」
の柔らかさ優しさに辿り着く。
清水かおり「相似形」
清水氏は現代川柳の作家とのこと。フレーズに独特の世界観、訴求力あり。どんどん引
き込まれる。「夏木立いつもひとりの翻訳機」「雨の日の瓶の水位は君を忘れる」 「口づけ
のように首傾げる焼却炉」「たぶんここ風の体を入れ替える」「原形は葡萄 知らない重さ」
「落ちたのは海 一瞥の林檎よ」。
中でも「太陽の人だからめぐりあえない」の微妙な哀感、「箱で売られる薄く唇あけたま
ま」のざわっとした手触りが特に印象的だった。
以上、妄言多謝。鑑賞眼の浅さ荒さ、力不足を自覚しつつ、思うところを書かせていた
だいた。何だか今ぼーっとしている。ぼーっとしていながらも、あらためて、21名の作
家の皆様には「ありがとう!また会いましょう!」と大きな声で言いたい。
作者紹介
- 宮崎斗士(みやざき とし)
1962年東京都生まれ。「海程」所属。「青山俳句工場05」編集・発行人。第5 回海程会賞、第45回海程賞、第27回現代俳句新人賞受賞。句集『翌朝回路』(六花書林)。現代俳句協会会員。
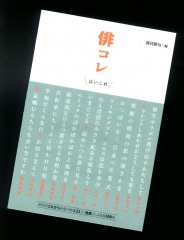 俳コレ 週刊俳句編 web shop 邑書林で買う |

