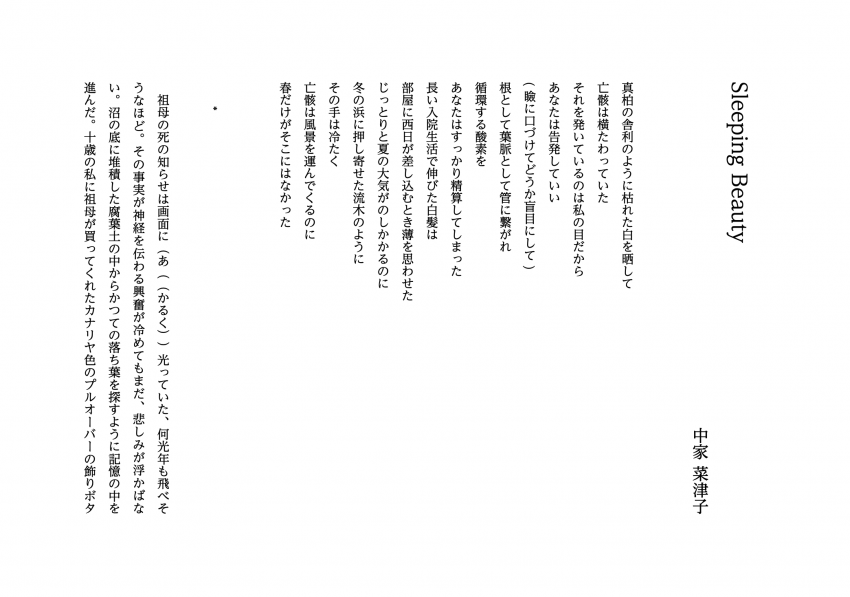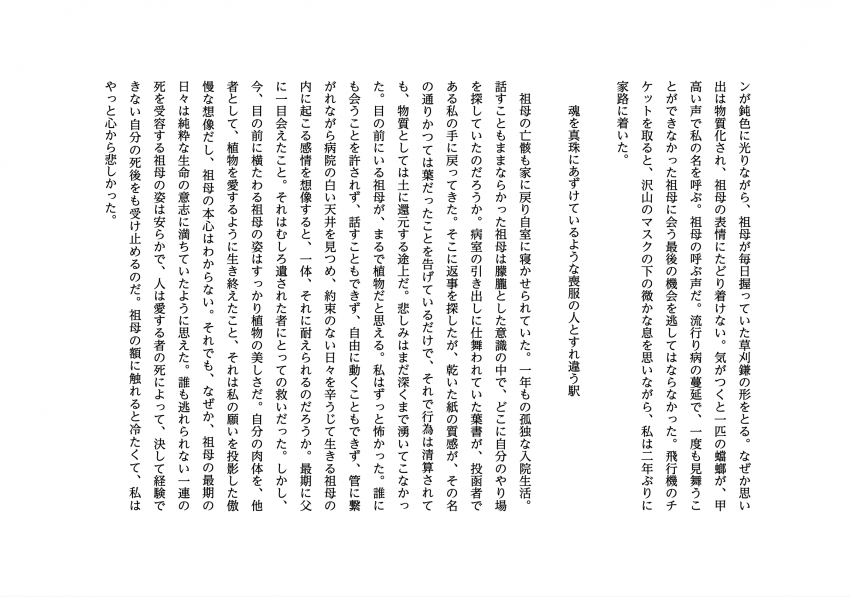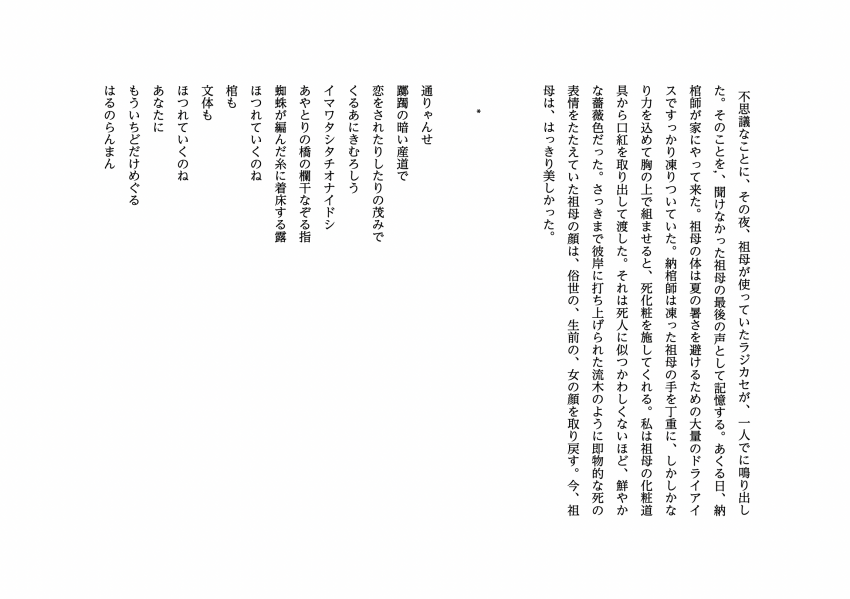Sleeping Beauty 中家菜津子
真柏の舎利のように枯れた白を晒して
亡骸は横たわっていた
それを発いているのは私の目だから
あなたは告発していい
( 瞼に口づけてどうか盲目にして )
根として葉脈として管に繋がれ
循環する酸素を
あなたはすっかり精算してしまった
長い入院生活で伸びた白髪は
部屋に西日が差し込むとき薄を思わせた
じっとりと夏の大気がのしかかるのに
冬の浜に押し寄せた流木のように
その手は冷たく
亡骸は風景を運んでくるのに
春だけがそこにはなかった
*
祖母の死の知らせは画面に(あ((かるく))光っていた、何光年も飛べそ
うなほど。その事実が神経を伝わる興奮が冷めてもまだ、悲しみが浮かばな
い。沼の底に堆積した腐葉土の中からかつての落ち葉を探すように記憶の中
を進んだ。十歳の私に祖母が買ってくれたカナリヤ色のプルオーバーの飾り
ボタンが鈍色に光りながら、祖母が毎日握っていた草刈鎌の形をとる。なぜ
か思い出は物質化され、祖母の表情にたどり着けない。気がつくと一匹の蟷
螂が、甲高い声で私の名を呼ぶ。祖母の呼ぶ声だ。流行り病の蔓延で、一度
も見舞うことができなかった祖母に会う最後の機会を逃してはならなかっ
た。飛行機のチケットを取ると、沢山のマスクの下の微かな息を思いなが
ら、私は二年ぶりに家路に着いた。
魂を真珠にあずけているような喪服の人とすれ違う駅
祖母の亡骸も家に戻り自室に寝かせられていた。一年もの孤独な入院生活。
話すこともままならかった祖母は朦朧とした意識の中で、どこに自分のやり
場を探していたのだろうか。病室の引き出しに仕舞われていた葉書が、投函
者である私の手に戻ってきた。そこに返事を探したが、乾いた紙の質感が、
その名の通りかつては葉だったことを告げているだけで、それで行為は清算
されても、物質としては土に還元する途上だ。悲しみはまだ深くまで湧いて
こなかった。目の前にいる祖母が、まるで植物だと思える。私はずっと怖
かった。誰にも会うことを許されず、話すこともできず、自由に動くことも
できず、管に繋がれながら病院の白い天井を見つめ、約束のない日々を辛う
じて生きる祖母の内に起こる感情を想像すると、一体、それに耐えられるの
だろうか。最期に父に一目会えたこと。それはむしろ遺された者にとっての
救いだった。しかし、今、目の前に横たわる祖母の姿はすっかり植物の美し
さだ。自分の肉体を、他者として、植物を愛するように生き終えたこと、そ
れは私の願いを投影した傲慢な想像だし、祖母の本心はわからない。それで
も、なぜか、祖母の最期の日々は純粋な生命の意志に満ちていたように思え
た。誰も逃れられない一連の死を受容する祖母の姿は安らかで、人は愛する
者の死によって、決して経験できない自分の死後をも受け止めるのだ。祖母
の額に触れると冷たくて、私はやっと心から悲しかった。
不思議なことに、その夜、祖母が使っていたラジカセが、一人でに鳴り出し
た。そのことを,、聞けなかった祖母の最後の声として記憶する。あくる日、
納棺師が家にやって来た。祖母の体は夏の暑さを避けるための大量のドライ
アイスですっかり凍りついていた。納棺師は凍った祖母の手を丁重に、しか
しかなり力を込めて胸の上で組ませると、死化粧を施してくれる。私は祖母
の化粧道具から口紅を取り出して渡した。それは死人に似つかわしくないほ
ど、鮮やかな薔薇色だった。さっきまで彼岸に打ち上げられた流木のように
即物的な死の表情をたたえていた祖母の顔は、俗世の、生前の、女の顔を取
り戻す。今、祖母は、はっきり美しかった。
*
通りゃんせ
躑躅の暗い産道で
恋をされたりしたりの茂みで
くるあにきむろしう
イマワタシタチオナイドシ
あやとりの橋の欄干なぞる指
蜘蛛が編んだ糸に着床する露
ほつれていくのね
棺も
文体も
ほつれていくのね
あなたに
もういちどだけめぐる
はるのらんまん
ほつれていくのね
きがつけば
焼き場に骨の爆ぜる音
あすたりすくの雪がふる
ほら、とおりゃんせ
火葬なら灰があなたの体温と同じになれる瞬間がある