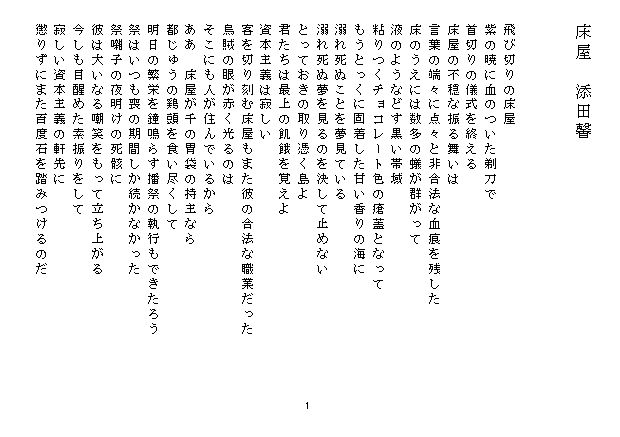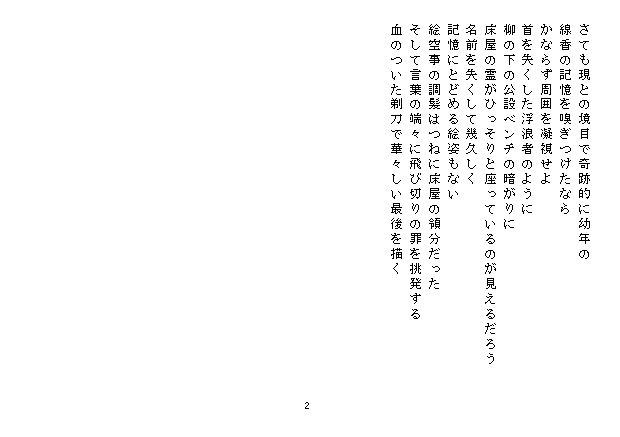床屋 添田馨
飛び切りの床屋
紫の暁に血のついた剃刀で
首切りの儀式を終える
床屋の不穏な振る舞いは
言葉の端々に点々と非合法な血痕を残した
床のうえには数多の蟻が群がって
液のようなどす黒い帯域
粘りつくチョコレート色の瘡蓋となって
もうとっくに固着した甘い香りの海に
溺れ死ぬことを夢見ている
溺れ死ぬ夢を見るのを決して止めない
とっておきの取り憑く島よ
君たちは最上の飢餓を覚えよ
資本主義は寂しい
客を切り刻む床屋もまた彼の合法な職業だった
烏賊の眼が赤く光るのは
そこにも人が住んでいるから
ああ 床屋が千の胃袋の持主なら
都じゅうの鶏頭を食い尽くして
明日の繁栄を鐘鳴らす播祭の執行もできたろう
祭はいつも喪の期間しか続かなかった
祭囃子の夜明けの死骸に
彼は大いなる嘲笑をもって立ち上がる
今しも目醒めた素振りをして
寂しい資本主義の軒先に
懲りずにまた百度石を踏みつけるのだ
さても現との境目で奇跡的に幼年の
線香の記憶を嗅ぎつけたなら
かならず周囲を凝視せよ
首を失くした浮浪者のように
柳の下の公設ベンチの暗がりに
床屋の霊がひっそりと座っているのが見えるだろう
名前を失くして幾久しく
記憶にとどめる絵姿もない
絵空事の調髪はつねに床屋の領分だった
そして言葉の端々に飛び切りの罪を挑発する
血のついた剃刀で華々しい最後を描く