「新撰21」、これほど、私の青春は終わってしまった、と痛感させるアンソロジーはかつてなかった。壊れそうな繊細さ、ナイーブさ、そしてみずみずしい表現力と体力。四十代半になった今の私には、もう作れない。
俳句は本当に不思議だ。年月を重ね歳をとるにつれて亀の甲羅のような老獪さを纏うようになる。そしてある時、それがぽろりと落ちて、そこには洒脱で軽みのある句が生まれる。しかし「新撰21」の俳人達は、そんな変遷の出発点、まだまだ柔らかい殻を纏いはじめたばかりで、独特の魅力がある。
三十代最後の年に、私は第一回芝不器男賞に応募した。その時に編まれた小冊子があるのだが、「新撰21」出版は、その冊子に掲載された俳人達と久しぶりの邂逅でもあった。
私はそんな俳人達に実際に会えるのを楽しみに、出版記念のシンポジウムに参加した。そして、ひとりひとりにサインなど貰いながら話を聞いてみた。するとそこには作品の強さ弱さとは全く別の、誠実でシャイな素顔の人々がいた。まるで中島みゆきの陰影ある歌と妙に明るいDJのギャップをそれぞれの作家が抱えているように。良く考えれば、俳句も創作活動なのだから、作品と作家に隔たりがあっても当たり前なのだが、それぞれの俳句があまりに心を剥き出しにしていたので、勘違いしてしまっていたのだ。
しかし、同時に、皆が誠実過ぎる人々なので却って不安になった。些細な日常を詠むのが俳句であるとはいえ、何だか生活空間が小さくまとまり過ぎて、閉じられているような気がしたのだ。このような私小説的な俳句の傾向が、これからの潮流になってしまうのだろうか。
この流れの中で、バブル期に学生時代を過ごした四十代の俳人、というのはどうも中途半端だ、と思う。五十代以上の人々からは旅をし吟行し写生する「基本的な」俳句を詠む最後の「若手」と見られているが、俳句はそれだけでもないような気がする。しかし、二十代や三十代からは当然完成した俳人と見られており、もう青春のしっぽをひきずる訳にはいかない。また彼らの詠む些細な日常だけでは物足りない、とも思う。不惑を過ぎたはずが、俳句では迷うばかりだ。つくづく私は昭和の人間である。
作者紹介
- 内村恭子(うちむら・きょうこ)
昭和四十年東京生まれ。
平成十四年「天為」入会。
平成二十年「天為」同人。
平成二十二年「天為」新人賞。
美術品オークションハウス勤務。
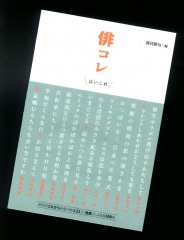
俳コレ
週刊俳句編
web shop 邑書林で買う

