サテ無事にお伊勢参りを成し遂げたとて、弥次郎兵衛・喜多八の二人は京の都でぐうたらぐうたら。ハッと気づけば月日は百代の過客にして、時は2012年5月某日となりにけり。
「おいッ、弥次さん弥次さん」
「んあ?なんでェ朝ッぱらからうるせえ野郎だ」
「朝でも晩でもいゝから起きなッ!おれたちゃ、ちィッとばかし、寝過ぎたやうだぜ」
「さう言や頭がぼんやりすらァ。いま何どきでぃ」
「2012年でぃ」
「ホゥそれはまた豪気に寝過ごしたもんだ」
「オイこの瓦版、仮名遣いがをかしくねェか」
「それだけ月日も経ちゃあ仮名遣いもをかしくなるってもんだ、ドレ」
「読めるのかい、弥次さん」
「いや、さつぱり、ハゝゝゝゝ」
「どうやつて江戸に帰りゃいいんでェ」
「さうだな、とにかくこんなボロ宿は御免だ、見ろてめェの足元腐ってやがる」
「さう言ふおめェの服にゃ菌(きのこ)が生えてら、ひとまづずらかって考えやう」
そういうと二人は京の町をぶらぶら。
「なんだか騒々しいな、これが2012年てぇもんかい」
「見ろッ、女子(をなご)の髪が異人さんみてえだぜ」
「服装も日本じゃねェみてェだな、男の図体のでけえこと」
「売国したのかもしれねェ」
「もの凄い早さで走る乗り物があるな」
「あゝ、こりゃいゝ、チョイトあれに乗って今夜の宿を探そう、オーイ」
「どちらまで?」
「エート、さうだな、このあたりに長屋はねェのかい」
「長屋ですか…山科の方に少しありますね」
「じゃ、そこまでひとつやっつくんな」
「弥次さん、長屋に行ってどうすんで?」
「長屋ってのは昔ッから人情深いんだヨ、だれかひとりぐれえ泊めてくれらあ」
「お客さん、着きましたよ」
「おう、もう着いたかい、かたじけねェ、じゃ」
「ちょっと、お客さん!賃料を払っていただかないと」
「賃料?ああ、そうか…おれの連れ合いが払うから、ちィっと待ってくんな」
そういうと弥次さん、長屋の中へ歩いてゆき、
「ふーむ、長屋といってもずいぶん立派なもんだ…オット、カモを探さなきゃあ。ごめんくださいよ」ガラガラ
「はい、なんでしょう…うわ、すごい格好なにものあなた」
出てきたのは御中虫。
「そいつぁこっちの台詞だ!てめぇ男のくせになんだかなよなよしてやがるな」
「うるせーあたしゃ女だよ!つかだれだてめー!けーさつ呼ぶぞ!」
「お、おなご…!?」
「おう、坊主頭の女がいてわりーか」
「よくわからねェな、2012年の女は…まあいいや、おまいさん、ちょいと頼みがあるんで、実はかくかくしかじかうんたらかんたら」
「へ??あの弥次喜多…?」
「オ、おれたちの名前も売れたもんだな、知ってるなら話が早い、とにかくまづは賃料を」
「冗談!なんであたしがあんたらのタクシー代払う義理がある!」
「一晩あっためてやるからよ」
「やかましい!」
「オウ、女とみて下手に出てりゃいい態度じゃねェか!」
「おまえが最初っからいい態度なんだよ!」
「ちょっと!静かにしてくださいよ虫さん!」
「ア、ご近所の奥さん、すみません…しょうがねーな、賃料貸すから静かにしろよ」
「へッ、最初っから素直に払やいゝんだ」
御中虫、しぶしぶタクシー代を払ふ、その隙に弥次さん喜多さんドヤドヤと虫宅に上がり込み。
「なかなか風変わりな内装じゃねェか、南蛮風だね」
「ちょっとあんたたち!なに勝手にあたしんちに入ってんのよ!」
「マ、これも何かの御縁…なんだ、この本」
「『おくのほそ道』…フム、こりゃおれでも読める仮名遣いだな。あんた、昔の本が好きなのか」
「違うわよ。こう見えてもあたしは俳人で、勉強してんの。この本はね、昔の本ではあるけれど、いまだに俳人の鑑となっているから現在でも手に入んのよ」
「俳人か!そいつぁ御見それ!イヤァ、こんなご時世になっても長屋に住んで俳句をする人がいるんだねえ弥次さん」
「オウ、喜多さん!おれぁ最初っからこの女たゞものぢやねえって踏んでたのヨ」
「嘘吐けよ」
「まま、チョットこの本読ませてもらうぜ…オ、松尾芭蕉と言ふ俳人か。なんと!またえらく長い旅に出たものだな…チョイト喜多さん、丸でおれたちのやうぢやねえか」
「ほんたうだな弥次さん」
「ウム。ヨシ、決まった!」
弥次さんやおら立ち上がると、
「今度の旅は、『おくのほそ道』をなぞり歩く旅にしようじゃねえか!こいつぁ気がきいてるぜ!」
「いいねえ弥次さん!しかし、おあしはどうすんで?この時代のあしなんか、おれたちゃ一文も持ってねえ」
「ナニ、こゝに立派な俳人さんがいらっしゃるじゃねえか」
「ちょ、冗談!あたし、俳句やってるけど俳句でメシ食ってねーし!つか無職だし!」
「ならイッソ尼さんになるがいゝや。その風貌だもの、みんな喜捨するぜ」
「いやです」
「…」
「…」
弥次喜多目配せをすると、突然奇声を発して大騒ぎを始めること、
「ちょっと虫さん!いいかげんにしてくださいっ!」
「ああっ御近所のみなさん!これには深いわけが!」
「いーえ、なんですか男を二人もつれこんで昼間っから!出ていってもらいます!」
御中虫、長屋村の村八分確定。
「もー!わかったわよ!おくのほそ道ツアーでも何でも行ってやるわよ!」
「善は急げだ、出発出発」
~~~~
トコロデ一方。こゝにも奇妙な同行二人がいた。
「ああ~ん、なんかもぉまじ疲れたってかんじぃ~曾良ぁ~抱っこ抱っこ抱っこ~」
「や、やめろよ芭蕉…みんな見てるじゃねえか…」
「ふふっ、赤くなっちゃって、カ・ワ・イ・イ♪」
「…ちっ…しょうがねえなあ…おんぶならしてやらんでもないぜ…そのかわりあとで一句詠めよ、今日はまだ一句もひねってないんだからな」
「ええ~また俳句のはなしぃ~?もお、芭蕉、疲れちゃった。俳句なんか、ぷっぷくぷ~だ」
「おいっ!おまえ、今じゃ俳聖って呼ばれてんだぞ!?わきまえろよ!!」
「わ・か・り・ま・し・たっ。曾良ってほんとキビシイんだからっ」
「だいたいおまえが『旅に病んで夢は枯野を駈けめぐる』なんつー未練がましい句を詠んだせいで、いまだに旅が終わらねーんだぞ」
「まあ、そこが芭蕉のスゴイとこってゆうの?一句ひねったら、夢、実現しちゃう?みたいな?でもさすがに飽きてきたわぁ」
「おまえのせいで俺までいつまでも死ねない体になったんだからな!責任とれよ!つかなんだよその言葉遣い!抵抗なく現代になじんでんじゃねーよ!」
「え…芭蕉のコト…もお、キライになっちゃったんだ…?」
「ばっ…ちがっ…」
「芭蕉のコト、好き…?」
「いやっ…それはそのっ…」
「やっぱり嫌いなんだ!もうイイっ!おろしてっ!わあああああああああ(号泣)!」
「おい!待てよ芭蕉!」
どしん!
「あ…ごめんなさい」
「イヤ、こっちもウッカリしてたんで…立てますかい、ご老体?」
「ご老体ぃ~?まじへこむ、その言い方!あたし、若いですっ」
「ア、コリャどうも失礼…(変なじじいだな)」
「芭蕉!芭蕉!」
「ちょっとぉ曾良ぁ聞いてぇ~?このヒト、あたしのこと、ご老体ってゆーんだよ?ぷーんだ」
「あんたはどーみても老人だよ!ちょっと黙ってて!あっすみませんなんか…あの、お怪我は?」
「イヤ、とくに…」
「ああ、お着物が汚れてしまいましたね…それにしても現代には珍しい風体ですね」
「ああ、おれは弥次郎兵衛ってもんで、かくかくしかじかチョット寝過ごしてこんな時代まで」
「えっ?奇遇ですね!わたしは曾良という者で、ここにいる、連れ合いはその、松尾芭蕉といいまして…」
「なんだって!?オーイ、みんなちょっと来い!」
どやどやどや。
「なんでぇ弥次さん大声出して」
「そうよ、往来で恥ずかしい」
「よっく聞け、ここにおわする方はあの松尾芭蕉大先生だとよ!」
「ええええええええええええええええ」
のけぞる一同。
「やだ。あたしってそんなに有名?まぁそっか、俳聖だもんね、うふん」
「(御中虫小声で)単に頭のイタイじいさんじゃ…」
「(芭蕉、虫をキッと睨み)あんたがあの御中虫ね?わかるわよ、そんな坊主頭の女なんてそうそういないもん。あたし、あんたの俳句だけは、みとめなぁーいっ」
「な、なんですかいきなり」
「あったしさぁ、無駄に長生きしてるわけじゃないわよ?いちおー、現代の俳句についてもひととおりチェックしてんのよ?でもあんた、句集出してても、『アンソロジ』られてないじゃん!きゃっはははは!カワイソー!」
「カワイソーじゃないっ!あたしゃ『俳コレ』なんかに入っても、いっこもうれしくなかったもんっ!」
「そお?そのわりには『このあたしをさしおいた100句』なんて、いかにも嫉妬に狂ったひねくれた連載してるじゃなあい?くすくすくす」
「うるさいうるさいうるさい!」
「その連載だって、もうすぐ終わりよねええ。そしたらあなた、どおすんのぉ?またぼっちになっちゃうのぉ?いやん、イタイタしすぐるぅ~芭蕉見てらんなぁい」
「う、う、…うわーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーん!!」
御中虫ついに泣きだす、それを見かねた弥次さん喜多さん、
「や、や、まあとにかくネ、芭蕉さんも虫さんも同じ俳句をうたう者同士じゃねェですか、そんなにいがみあうこたねえですよ」
「さうだヨ、どだい時代も世代も違ふぢやねえか、比べろってほうが無理な話だ、ナ」
曾良ぽんと手を叩き、
「そういや俺、いま『俳コレ』持ってますよ。最新の句集だというんで、さっきジュンク堂で買ったんです。虫さんの書評連載終了の前祝いを兼ねて、ひとつどこかの宿屋で『俳コレ』を肴に宴会でもしようじゃありませんか。ね、いいでしょう、みなさん」
「そいつぁいい」
「愉快なことになってきたね」
まだ睨みあう芭蕉と虫をなだめつゝ、一行は適当な宿屋に腰を落ち着けり。
「さあ、宴会だ。いいねえ、俳句を肴に一杯。ソレソレ、曾良さん、あんたいける口だね」
「いえ、俺は…とにかく虫さん、これあなたの連載ですから、あなたがまず句を選んでくださいよ」
「えー。別にもういいんじゃないのー。あたしタバコ吸ってるからさー、芭蕉大先生に、見てもらえばぁ?」
「そんな、拗ねるなヨ、虫の旦那」
「旦那じゃないっ」
「オット失敬、お嬢さん」
「きゃははははは」
「笑うな芭蕉!」
「なによぉー俳聖にさからう気?」
「まま、お二方、じゃこういう趣向はどうで?虫さん5句、芭蕉さん5句、計10句選んで皆で鑑賞」
「オ、さすが弥次さん、いい趣向だ」
といふわけで選び出された10句。
「ええ、ではまず芭蕉さん選から。一句め」
天の川音のするまで右に廻し 岡野泰輔
「じゃ、芭蕉が解説するね♪この句のステキなところわぁ…」
「アイ、チョイト失礼しますヨ」
「ちょっとぉ~アンタ誰?」
「わっちぁ季語太夫でありんすぅ。俳句の宴ときいちゃあ、出て来ずにはをれませんわいな」
「誰が呼んだのよ、こんなの」
「へへ、おれが」
「隅に置けねえなぁ喜多さんも」
「んもう、邪魔が入ったわね。続けるわよ。この句のステキなところわぁ…、」
「この句は季語が動きィしィせん。そこがよいのでありんす。まるで天の川がオルゴオルのやうに、きらきらとかゞやいていんすわな」
「うっさいわねこの季語太夫とかゆう女!芭蕉の鑑賞も聞きなさいよ!いい?天の川というものには音がないのね。そこにあえて【音のするまで】と、いよいよありえないことを言っている、この浪漫よ!」
「で、なんで【右に】廻すわけ?【左】じゃダメなのー?字余りだからぁ?」
「虫は黙ってて!」
「あたしの連載なんだよ!だいたいさぁ、天の川って季語、ちょっと甘くない?そこにさらにオルゴオルだかなんだかわかんないけど、ロマンチックな語句をだらだらだらだら、恥ずかしくないの?クールに行けよ、もっと!右に廻そうが左に廻そうが音なんかしねーよ!その【音がしない】って事実にもっと目を向けてこーぜ!こんな現実逃避句、ちっともよくねーよ!」
「まー!憎たらしい虫だことっ!芭蕉、まじむかつく!」
「おう、やるか?」
「イヤイヤ、おふたりさん、まま、一献。先は長い、次の句に行きましょうや」
放たれし鷹漂うてみせにけり 望月周
「これは虫が選んだ句ね。じゃあ解説するわね。えっと」
「おこんばんわぁ」
「誰、あんた」
「無季奴ともうしますぅ」
「また話をややこしくするのがきた!誰が呼んだのよ!」
「へへ、俺が」
「また喜多さんか、しょうがねえなあ」
「だいたいこの句は無季じゃないじゃない!いい、この句はね、鷹のもつ雄大さをきわめてシンプルに言い表した句なの。しかも【放たれ】たというのに、大空に消えてしまわないで【漂うてみせにけり】よ。わかる?放たれてなおそこに漂うてみせる鷹揚さ、まさしく王者の風格、余裕を感じる一句だわ」
「でも姐さん」
「なに?無季奴」
「うち、思うんやけどぉ、この【鷹】って、本当の鷹と違うんやないやろか?なんか、こお、作者の精神性を表すシンボルとしての【鷹】にすぎへんのやないやろか?せやとしたら、この句、無季にも読める…」
「ふたりともなにめちゃめちゃなことゆーてんのぉ?芭蕉、こんなつまんない句きらぁい。だからなにぃ?ってかんじ?なんてゆうかぁ、俳句を勘違いしてるかんじぃ?【それっぽい】けどぉ、核心をついてないよね。たましいのさけびがぁ、欠けてる?みたいなぁ」
「革新的でもねえなあ」
「弥次さん、『核心』と『革新』を掛けたね、ウマイッ」
「イヤァ、確信犯だよ喜多さん、ハゝゝゝゝ」
「ハゝゝゝゝ」
「あの~、俳句と関係のない話題は…」
「オット曾良さん、いたのかい。静かだから気付かなかったヨ、マアいいじゃねえか飲みねえ飲みねえ」
「恐れ入ります」
「次は芭蕉の選よぉ」
金魚掬ひて枯野へと放ちけり 山下つばさ
「見てこの句!この句の」
「御免」
「は?あんたナニ」
「拙者、切れの守と申す」
「ああんもお、また変なのが増えたぁ」
「イヤ、にぎやかな方がいいかなッてんで」
「また喜多さんの仕業かい、参ったねハゝ」
「拙者思いまするにこの句、さいごの【けり】が効いてをりますな。潔い、いさぎよい、切れとはいさぎよく使うもの」
「誰もアンタなんかの意見聞いてないわよー!」
「季重なりでありんす」
「季語太夫!まだいたの!」
「姐さんうちゃこの【金魚】にも【枯野】にもリアルを感じィしィせん、この句は無季」
「無季奴もおだまりっ!芭蕉まじむかついてきた!あのねえ芭蕉はねぇ、枯野に浪漫を託した第一人者なのよっ!この山下つばさって子は、その浪漫を受け継いでいると思う~!金魚の泳ぐ枯野を想像してごらんな」
「できるかバーロー!」
「出たな、虫!」
「おう、出たわい!なんでもかんでも枯野に放り込んだら浪漫かよ!金魚も枯野もなあ、俳句世間で一山百円で売られてんだよこのご時世!芭蕉!俳聖だかなんだかしらんが、金魚はともかく枯野がインフレおこしたんは半分以上てめーのせいだぞ!どないして責任とってくれんや?お?」
「芭蕉、疲れちゃったぁ~お酒飲んでこよっと」
「逃げる気かっ」
「ささ、一献」
「うふん、あ・り・が・と♪」
「芭蕉、ちょっとペースダウンしてくれ」
「やだぁ、曾良だって、結構呑んでるじゃなあい、つんっ♪」
「イヤァ、救いがたい様相を呈してきたね、弥次さん」
「オット、【掬ふ】と【救う】を掛けたね喜多さん」
「見破られたか、ハゝゝゝゝ」
「ハゝゝゝゝ」
宵闇やはぐれし人を探さずに 望月周
「これは虫選ね。さて」
「われは音韻・ド・句頭院なり」
「またややこしいのが…弥次喜多っ!」
「なんせ連載最終回前の前夜祭ですから、へへ」
「yoiyamiya のy音の羅列、はぐれし人 のh音の重ね方、探さずに のs音の重ね方…美しい」
「虫が鑑賞するんだから部外者は黙ってて!そうね、これは音韻も面白いけど」
「【や】で切れて、最後の【に】でさらに切る。上級者でござる」
「切れの守…あのな」
「うちゃ無季やと思うんどす」
「無季奴ちゃん、いい子だからあっちいってて、はぁ…ちょっと一杯もらえる?」
「あ、どぞどぞ」
「ふぅ。あのね、虫が思うに【はぐれし人】は恋人かなにかなんだよ、きっと。お別れをはっきり言うのは名残惜しい、だからせめて宵闇にまぎれてさよならしませうという、ちょっとものがなしい句」
「ちゃんちゃらおかし~い!芭蕉笑える!なあに、この陳腐なヒロイズム~。さがしてやんなさいよ、男なら!探さずに黙って去る俺~って、く・らーいっ。芭蕉そーゆーの、不健康だと思う!どぉせこいつ、家に帰って酒浸りになるんだよぉ。あ、酒もうないの?」
「ありますあります」
「かんぱーいっ☆」
「イヤァ芭蕉さんの飲みっぷり、いいねェ」
「うふん、ありがとん」
「ちょっと、あたしの連載なんですけど!」
「アア、わかってまさァ、虫の旦那」
「旦那じゃないっ!」
「アレ、虫さんの奢りじゃなかったんで?」
「あたしゃ無一文だってば!!おいこら曾良テメー払えよ!こんなわけわかんなくした責任おまえにあるんだからな!」
「エ、エエエエエ!?だって虫さんのお連れさんが…」
「あんなやつら連れじゃねえ!!」
「盛り上がってきたねえ弥次さん」
「そうだねえ喜多さん」
閉ざされて月の扉となりにけり 津川絵理子
「これわぁ、芭蕉が選んだ句でぇ」
「【閉ざされて】と【けり】がうまく呼応しているでござるな」
「あのさあ」
「季語が凛としているでありんす」
「だからあ」
「t音がリズムよく入っているのう」
「でもこれはポエジイだからうちゃ無季やと」
「いえわたくしは、この句の魅力は定型にこそあると思いまする」
「むむ?また新たなキャラが乱入したわね?あんた誰」
「定型観世音菩薩でございまする」
「なんだい、また呼んだのかい喜多さん」
「イヤァ、ここまで来たらどんちゃん騒ぎしねえともったいねえよ弥次さん」
「うるさいなああもおぅ!芭蕉の観賞する隙がなくなっちゃうじゃないのっ!この句はねえ、ミステリアスな魅力があるのよねえ~。何が閉ざされたのか?月の扉ってなあに?乙女心をくすぐ」
「らないね、全然!」
「やろう、また虫かっ」
「こーゆー思わせぶりな句は、えてして実はなーんにも考えていないことが、多いんだよ!言葉のイメージに溺れているだけだね!自分が翻弄されているだけだね!ちっとも魅力的じゃない!酒もってこい!」
「虫さんもイケる口だねえ」
「あたしゃ下戸だよ!けどこんな展開になったらもー酒呑んでごまかすしかねーよ!連載どーしてくれるんだよ!ここまで結構順調に来たのによ!!」
「順調だったあ?あれでぇ?くすっ、くすくすくすっ」
「曾良!芭蕉黙らせろ!」
「仲良くしてくださいよ、ふたりとも…」
「やだ」
「やだ」
「案外息が合ってるように見えるがな、弥次さん」
「そうだな、喜多さん」
「マア、おれたちほどじゃねえが…ふふっ」
「やめろよ、弥次さん…読者が、見てるぜ…ふふふっ」
初日出でたり万歳す合掌す 望月周
「これ、虫ね。ふーむ」
「破調じゃ破調じゃ、でんつくでん」
「もう誰が来ても驚かねえ。酔いも回ったし。ま、一応聞くけど、誰?」
「破調達磨じゃ、でんつくでん」
「先に聞いとくけど、あなたのご意見は?」
「これは十七音におさまりはしているものの、【初日出でたり】【万歳す】【合掌す】と変調で切れるのじゃ、でんつくでん。ゆえに破調の一種とみなす、でんつくでん」
「ちがうざます、これは自由律の一種なんざます」
「もう一人来たか。自己紹介をどうぞ」
「自由律公爵夫人ざあます。世間では自由律をただやみくもに十七音を破壊したものと誤解する向きがあるざますが、自由律は【律】に重きをおくもの。この句は独自の律をもって表現することに、成功しているざあます」
「季語をお忘れでないかえ。【初日】がなけりゃあこの句は成立いたしィせんよゥ」
「うーん頭痛くなってきた。虫はさあ、この『もろ手を挙げて寿ぐ』感に魅かれたのよね。『俳コレ』にはたくさんの句があったけど、ここまで愚直にめでたい句はなかったのね。それと、リズム感かな。踊りだしたくなるかんじ…あっ弥次喜多っ裸踊りはやめなさいっ」
「ふんどしは締めてますぜ、旦那」
「なんなら外してもいいですぜ」
「やめろっつーに」
「あーやだ、あんたの連れまじ下品、芭蕉萎える~。あ、一応批評しとくわあ。この句、やりすぎ?ってかんじぃ。本来『俳』とは、もっと節度を持ってストイックにうたうべきなのよね~。なのに、なに?このうかれとんちきな句は~。芭蕉の時代には、こおんな無節操な句、なかったわあ~。ほい、曾良ちゃん酒注いで」
「てめーの現状の方がよっぽど無節操だろ」
「え?なに?なになに?曾良と芭蕉の関係に嫉妬してんのぉ?ヤダ、さもしい~キャハハハハハハハ」
「ちげーよ!つか弥次喜多!静かになったと思ったらなに裸で抱き合ってんだよ!」
「そうよねえ~ぼっちなのは、虫ちゃんだけだもんねえ~カワイソー」
「虫殿、拙者がいるでござる、でんつくでん」
「わっちもいるでありんすよゥ」
「うちもぉ」
「ざます」
「やっかましいっ!!」
御中虫、ついに席を立ってどこかへ、
「あらん。虫ったら、拗ねちゃったみたあい。ちょうどいいわ、あたしもちょっとお手洗い」
芭蕉は雪隠へ。
「弥次さん、なにやら静かになったと思ったら、あのふたりどこかへ行っちまいましたぜ」
「ちょうどいいや喜多さん、向こうに蒲団が敷いてある、…ふふふっ」
「ち、ちょっとちょっとお二方何考えてんですか…これ俳句の観賞文ですよっ」
「曾良さん、あんたも来るかい?なかなかイイ体してると思ってたんだヨ…」
「そ、そんな…僕には芭蕉というヒトが…ああっ」
襖、音もなく閉まる。
「…やれやれ、残されたわっちらは、どうすりゃいいのサ」
「仕方がありませぬ、我らで残りの句を鑑賞いたしませぬか」
「うちも混ぜてえな」
「あたくしも」
「でんつくでん」
と、云う訳で。残された句ずらずらと並べられ。
レモンティー雨の向うに雨の海 太田うさぎ
だまし絵のやうに猫ゐる年の暮 太田うさぎ
耳うすく一月一日はどこへ 岡村知昭
「では、まず…季語太夫いかがか」
「わっちゃあこの太田うさぎとやらいふ娘の季語の扱いには我慢なりんせん!【レモン】も【年の暮】も、たゞ当て嵌めただけではありんせんか!付け足しのやうに季語を用いる最近の風潮にはうんざりでありんすゥ」
「いやだわ姐さん、もうそんな重苦しい季語の時代は終わったとうちゃ考えております。太田さんの句には詩情がありんす」
「いやいや、彼女のレモンティーの句、a音が句頭韻になっておるところに注目せんといかんですな」
「【レモンティー】で何気なく切れているところに品のよさを感じるでござる」
「定型を守る、美しさでございまする」
「いや、破調という冒険心に欠ける、でんつくでん」
「こんな句はいっそ自由律にする方が内容が活きるざますのに」
「次の句もわっちゃあ意味がわかりんせん、なぜ【耳うすく】と【一月一日】が絡むんでありんしょう」
「いやだわ姐さん、そこがポエムなのよぅ」
「mimiとitiでリズムをとっているのじゃよ」
「とにかく破調でないことには、でんでん」
「定型だからこそこの内容が活きるのでございますよ」
「いえ、自由律にすべきざます!」
「季語を舐めてゐるでありんす!」
「だから現代俳句にもはや季語は不要なのよっ!」
「冒険心が!」
「句格が!」
「でんつくでん!」
大暴れに暴れてついに襖を破りたれば、
「お客さん!いい加減にしてくださいっ!出てってくれっ!」
宿屋の主に全員つまみだされけり。
全員散り散りに解散したあと残りしは、
芭蕉と曾良、弥次喜多と虫。
「あ~あ、なんだかわけのわかんないうちに追い出されちゃった…あんたの連載、こんなんでいいわけ?」
「いいわけねーだろ!」
そこへひらひらと一枚の短冊、
給油所をひとつ置きたる枯野かな 山田露結
「あら、もう一句あったんだっけ。これ、どっちが選んだ句?」
「さあ…」
「【枯野】って入ってるからには、芭蕉じゃね?」
「えー芭蕉【山田露結】きらぁい。虫じゃね?」
「では、こうしたら…最後だし、おふたりで鑑賞ということで」
「曾良、たまにはいいこと言う~。虫、最後ぐらい一緒にやんね?」
「ああ…(どーでも)いいよ」
「じゃあ芭蕉の観賞。露結!てめ神聖な枯野にナニ給油所設置してんだよ!どけろよ!枯野にはなあ、浪漫しか持ち込んじゃいけねーって決まってんだよ!つか芭蕉が決めたんだよ!面白くねーよこんな汚らわしい句!定型?句頭韻?それがどーしたんだ!ひとのサンクチュアリ灯油臭くすんな!出てけーーーーー!!!」
「じゃあ虫の観賞。露結!てめーも一山百円の枯野にひっかかった口か!枯野はもうインフレおこしてるっつってんだろー!そこに給油所置いたぐらいでドヤ顔すんなまじうぜえ!枯野が神聖なものたりえた時代にはそれが二物衝突でよかったんだよでも今は違う!どちらも俗だ!まだ枯野になにがしかの浪漫を感じているおまえ芭蕉か!」
「ちょっと…いまなにげに露結を罵倒したと見せかけて芭蕉のこと罵倒したわね…?」
「気のせいじゃね?ふんふんふ~ん」
「なによあんたなんかあらゆる意味で枯野女のくせに!」
「ちょっとそれどーゆー意味っ!」
「イヤハヤ弥次さん、俳句鑑賞ってこんなにとげとげしいものだったとはナア」
「そうだな喜多さん、おれたちゃ俳人じゃなくてほんとうに良かったナア…ふふっ」
「ふふふ…っ」
「あっお二方、どこへ行くんです!」
「あんな喧嘩に付き合ってもしょうがネエヨ、おれたちゃおれたちでやることがあんのサ…」
「曾良さんも来なヨ、宿屋の続きを…サ…ふふっ」
「ふふふっ」
「ああっ…」
そしてふたりの俳人を枯野に残して三人の男は闇夜に消えたのだった。
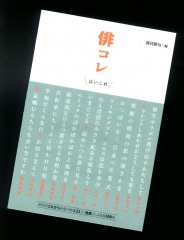 俳コレ 週刊俳句編 web shop 邑書林で買う |
執筆者紹介
- 御中虫(おなか・むし)
1979年8月13日大阪生。京都市立芸術大学美術学部中退。
第3回芝不器男俳句新人賞受賞。平成万葉千人一首グランプリ受賞。
第14回毎日新聞俳句大賞小川軽舟選入選。第2回北斗賞佳作入選。第19回西東
三鬼賞秀逸入選。文学の森俳句界賞受賞。第14回尾崎放哉賞入選。







2012年5月29日 : spica - 俳句ウェブマガジン -
on 5月 30th, 2012
@ :
[…] た怪物に違いない。ということで、残念ながら俳句については失念。 http://shiika.sakura.ne.jp/haiku/hai-colle/2012-05-04-8466.html 同時に散々苦労した第10回の画像「~~虫コレ」到着。これはま […]