まず、三つのお断りから始めておきたい。一つは、評者の連載は最大で5回の予定であるが、毎週の掲載ではない。隔週か三週間置きになる。一つは、評者は三詩型のうちの短歌側の人間として執筆している事である。三詩型それぞれの分野から『俳コレ』ないし『超新撰』の評者を募っているが、俳句側ではなく短歌側として引き受けた。歌人の執筆者が一人少ないように見えても、評者が含まれているので実際の数は合うはずだ。最後の一つは、前回の松本てふこ論のところで同氏が所属している結社の事を「伝統俳句の牙城とも云える結社」と書いたのだが、「伝統俳句の牙城となりつつある結社」と書いた方が正確だったのかもしれない事である。現在は日本伝統俳句協会系の結社であるが、いわゆるホトトギス系の伝統俳句結社とは来歴が違う。ちなみに、評者が所属している「澤」も伝統俳句の牙城と巷では言われているらしい……絶対に違う、と思う。
【矢口晃】
金魚飢う部屋のどこにも鏡なし
嘘つきし口もわが口あたたかし
立春や石をめくれば虫の国
夏果や押して鉄扉の地を擦れる
わたむしの浮力だんだん吾の浮力
あと二回転職をして蝌蚪になる
犬と犬すれ違ひたる銀河かな
鷹鳩と化すや嫌はれてもいいや
グッピーに藻を足し無断欠勤す
へうたんの中に鋭利なものがある
境涯詠が多いという点で、石田波郷と通じるものがある(作者は、波郷に兄事した藤田湘子に師事していたが、その影響ではないと思う)。しかし、波郷の境涯詠は病中吟に集中しているが、作者のものは失業者やワーキングプアの社会的境涯に集中している。その点、小林一茶や村上鬼城の動物に自己投影した境涯象徴詠に近い。しかし、一茶や鬼城の句は動物に自己投影しているものの、動物の描写が主であり、作者の句には作中主体が動物とは別に前面に押し出ている。この点、非常に短歌的であり、池田澄子の「この人の詠みたいもの、持っているものは、本当はあまり俳句と相性のいいものではないですよね」という指摘は正しい気がする。それをきちんと句にしているのは作者の実力ゆえであろう。また、句の境涯性をどこまで追求するかという問題もある。現代の二三十代の不安やその世代を取り巻く社会的状況を優れた手法で代弁しているのか、敢えて自己劇化して世代の代弁者の役割を芸術の為に演じているのか、上の世代を喜ばせるためにこの世代にしか詠めそうにもない素材を持ち込んでいるのか、世代論ではなくあくまでも自分自身にしか興味がなく一茶や鬼城以上の自己憐憫に陥っているのか、読者には判然としない部分もあるが、今後は解消されていくに違いない。特に、失業や貧困に関する句は世間的に急増して来ているので、作者にしか詠めないような切り口に期待したい。作者の句には、二物衝撃の多用(湘子の影響か)や素材の厳選(水・雲・虫など)といった特徴もあったが、近年新たな師に付いたことにより、大いに変貌しつつあるようだ。
一句目、水槽か金魚鉢(閉鎖空間)の中で金魚が飢えているが、鏡の無い部屋(つまり閉鎖空間)の中で金魚を飼っている作中主体も飢えているのかもしれない。ただ、この句における飢えや閉塞感はあくまでも現代人の精神に巣食っている、抽象的なものとして読みたい。失業者やワーキングプアの貧困という具体的な読みを重ねると句の価値が下がる。発展途上国の難民とでは飢餓や絶望のレベルが違うからだ。二句目、「も」「わが口」という確信犯的な呆け具合、「あたたかし」というナルシズムが面白い。三句目、この句型の見本例。「国」という表現で句になっている。ただし、立春は石の下だけど、啓蟄になったら石の下から出てくるはず、と理詰めで鑑賞すると味わいが薄くなりそうだ。四句目、境涯詠としても読めるが、それでは「夏」「果」「押」「鉄扉」「地」「擦」が付き過ぎでつまらない。あくまでも鉄扉と地面の接触を写生した句として解釈したい。五句目、わたむしに同化していくような意識が句の見どころ。綿虫という儚く哀れな存在に作中主体を重ね合わせるところに、作者の強い自己憐憫を感じる。芸術のために自己劇化しているのか素朴な本音なのか不明。前者であると推察する。六句目、作者のリクルート俳句の中では、「あと二回」という具体性、「転職をして蝌蚪になる」というイメージの飛躍があって出色。現状報告でなく、未来を語っているところも好いし、「転生」を「転職」にもじった機智や成体の蛙でなく幼生の蝌蚪になる機智も効いている。ここでも、儚く哀れな存在に作中主体を重ね合わせる手法が使われているが、前出の綿虫よりも蝌蚪の方がグロテスクなインパクトがある分、句として現実感がある。七句目、瑣末な日常風景と広大な銀河を取合わせる手法は「銀河系のとある酒場のヒヤシンス」(橋間石)に通じる。八句目、季語は七十二候の一つだが、本来の季感ではなく、鷹から鳩への「社会的には格下げと見られる身分の異動」に注目したようだ。作中主体は「嫌はれてもいいや」と言いつつも、鳩になった自分を嫌われたくないのだ。つまり、「鷹鳩と化す」と「嫌はれてもいい」は一見二物衝撃であるが、一物仕立。九句目、評者にも同様の体験があり、共感できた。「グッピーに藻を足」すという行為、「無断欠勤」という欠勤の種類、いずれも具体性があるからこそ句にリアリティーが感じられる。十句目、百句の中で最も良いと思った。句意が明快でありながらも、色々な読みや解釈を誘う。作者の新し方向性を感じる。
【南十二国】
鏡みな現在映す日の盛
人類を地球はゆるし鰯雲
甦るごとく暁けゆく障子かな
ロボットも博士を愛し春の草
遺跡ふと未来に似たり南風
枯園に散らばつてゐる小さき音
たんぽぽに小さき虻ゐる頑張らう
集まつてだんだん蟻の力濃し
雪達磨星座のけもの聳えけり
落葉踏みわれは言葉の国にゐる
SF的発想を採りいれつつも、句はどこまでも端正かつ清新。屈折、陰惨、悲哀といったものから程遠い。抒情に満ちた青春俳句と云ってもよいかもしれない。三十代を迎えた今、最初の変革期を迎えるであろうが、どういう方向を目指すのであろうか。作者は箴言的な句、哲学的な認識を詠んだ句が多いが、そういった思索は深まってくるに違いし、そう言った思索を詠む技法や表現手段も深まって来るであろう。十二国は韻律処理における押韻の仕方や季語の斡旋が巧みな作者であり、同じ内容でも凡百の俳句愛好者では考えつかない表現に至る場合が多い。楽しみである。なお、作者と同門の小川軽舟や高柳克弘と同様、『20週俳句入門』(藤田湘子)の型に基づく句が多いが(同書に学んだ評者の句も例外ではない)、作者にとって型はプラスに作用しているようである。
一句目、「鏡みな現在映す」の箴言的な認識は可も不可もなく及第点といったところだが、「日の盛」で佳句になっている。池田澄子と同意見。二句目、こちらの認識はありそうでなかったので、一番最初に詠んだ作者の手柄。「鰯雲」の斡旋も好い。ちなみに、地球が人類を「ゆるし」てしまうところが作者の個性だと思う(評者なら別の季語を使って地球に人類を駆除させる)。三句目、「甦る」が出てきそうでなかなか出てこない。四句目、ハとクの韻が効いていて、「春の草」は韻律的にも内容的にも動かない。なんて素敵な光景。五句目、作者のこの系統の句の中では弱い方だが(過去に未来の原型を視る、という認識は有りがち)、季語の斡旋がやはり良い。ミの頭韻だけで選んだのではなかろう。過去の遺跡と南風の取合わせで、未来都市の廃墟が目に浮かんでくる。六句目、素直で繊細。「散らばつてゐる」が悪くない。七句目、下五の勝利。八句目、不気味な凄みのある句。数は力という陳腐な箴言とは一線を画している。九句目、こういう抒情はありそうでなかなかない。昭和、子供時代、田舎の三拍子が揃っている雰囲気。十句目、「葉」の連想でできたような句だが、こういう「われ」の実感は悪くない。落葉を踏む音が無言の空間に響いているようだ。
【林雅樹】
干潟にてパンツな見せそお婆さん
梅雨深し王の真似する家来たち
人死ねば肛門開く大暑かな
ぱらぱらと人逃げて行く枯野かな
管弦楽団塔の土台に埋めて冬
凍死者の人差指の何か指す
ぶらんこに背広の人や漕ぎはじむ
草いきれ河童釣れたらまづ皿割る
一筋の黒髪浮ける泉かな
南風(みなみ)吹きわたる日本の沈みし海
評者と同門の先輩である。同じ師系でも句風は違うが、好きな句が多い。そもそも、結社の句会では評者は毎回のように彼の句をとってしまう(他の誰も彼の句をとらない時でさえ)。顰蹙系の俳句も真面目な俳句も好きなものが多い。なぜ好きかと言えば、他の誰にも詠めない、他の誰も詠もうと思わなかった発想や素材があるからだ。そもそも一定水準以上の技術を持っている作者なのでいくらでも無難な句は作れるのだが、そのような事で点を稼いでも面白くない、と思っているようで、その技術力を珍妙な発想(物語性の濃い内容が多い)を表現するためにひたすら奉仕させている。つまり、顰蹙系の俳句とはいえ、悪巫山戯ではなく、大真面目な取組みの結果である。もしかしたら将来何らかの変貌は訪れるかもしれない(顰蹙系俳句をやめるとか)が、作者の姿勢は変わらないだろう、きっと。
一句目、よくある情景だが、句として詠まれたのはたぶん本邦初。卑俗な内容にわざわざ王朝的な「な……そ」を使うあたり、技あり。二句目、季語の斡旋と句意の寓話性が素晴らしい。他国でもよくある話だが、日本の企業や役所では日常茶飯事。三句目、死を美化しないところが好い。特に暑い日は腐敗現象が進行しやすく、肛門から脱糞する死体も多い(それゆえ、死後処置の折には肛門にも綿花を詰めるそう)。四句目、「遠山に日の当りたる枯野かな」(虚子)から百年ほど経ち、枯野のイメージも多様化してきた。枯野を俯瞰している視点が面白い。五句目、類を見ない妄想、否、幻想。三崎亜記の短篇「鼓笛隊の襲来」に出てくる鼓笛隊の末路かもしれない。六句目、凍死者が何かを指していた、という摩訶不思議な光景を描いている。一般的な凍死は時間がかかるため、普通は何かを指しながら死ぬ事はない。ただ、低温による幻覚症状は報告例があり、一般的な凍死の場合はこの解釈を採りたい。自身の家族や友人の幻像、もしくは天使や死神を指していたのかもしれない。なお、一般的でない、瞬間冷凍による凍死の可能性もある。その場合は多分殺人事件であるので、犯人を指しながら死んだのかもしれない。被殺者の人差指が何かを指しているミステリ小説は多いが、凍死者版も書けそうだ。脱線してしまった。七句目、幼少期を懐かしんでいるビジネスマンだろうか、それともリストラされて出勤しているフリをしている元ビジネスマンが昼間の公園に来ているのだろうか。六句目同様、物語性のある句。八句目、残酷性が俳句に合っている事を示す証左。草いきれの見られるような暑い日、河童は即干上がるだろう。その頭の皿を割る事で水分補給を不可能にするのだ。日本各地にある河童のミイラのうち、何体かはこのような残酷な方法で製造されたに違いない……嘘。九句目、「一筋」とあるので鬘(ヅラ)ではなく、エクステであろう。付けていた当人は入水してしまったのか。写生句のようでありながら、光景の珍妙さが物語的な読みを誘う。十句目、「南国に死して御恩のみなみかぜ」(攝津幸彦)どころか、日本そのものが沈んでしまった。
【太田うさぎ】
遠泳のこのまま都まで行くか
きつねのかみそり迷子になつてゐないふり
レモンティー雨の向うに雨の海
着膨れて大きな声になつてゐる
だまし絵のやうに猫ゐる年の暮
寿司桶に降り込む雪の速さかな
なまはげのふぐりの揺れてゐるならむ
エリックのばかばかばかと桜降る
時速百キロつぎつぎと山笑ふ
四隅より辞書は滅びぬ花ミモザ
作者の特長は、おおらかな笑い、どぎつくない俳味、省略の巧さ、天衣無縫の表現、そして明るさにあるのではないだろうか。『俳コレ』掲載百句には撰者の趣味が出ているとはいえ、ここまでマイナス思考の句がないという事はやはり作者の資質なのであろう(評者が挙げた十句目の辞書の滅びにしても暗さが付き纏わない)。負や影に惹かれる傾向の多い俳人が多い中、珍しい。同様に、事物の細部を詠む事が少ない。写生詠はあっても写実詠は少なく、それに反比例するかのように、大胆な状況把握に基づく句が多い。大胆な状況把握は一般論でいえば危険なのだが、省略の効かせ方がうまいため、むしろ浮世絵的な構図の句を生みだす事に役立っているようだ。
一句目、都からの距離感が読者にわかる仕組みになっている。二句目、「ゐないふり」という幼心が平仮名を多用した表記と合っている。三句目、省略がうまい。レモンティーを飲んでいる作中主体の居場所、窓の外の雨が降っている土地、更にその奥の海。四句目、これも省略の見本例。五句目、だまし絵の比喩が年の暮と合っている。日本における犬猫飼育率の割合は約3対2、犬猫飼育意向率の割合は約8対5で犬派の方が多いはずだが、俳句は猫の句の方が圧倒的に多い。六句目、出前の寿司を食べ終わったのち、外に寿司桶を出しておいたのであろうか、雪が意外な速さで桶の中にまで降り込んでくる、という句意であろうか。速さに着目したのが好い。七句目、韻律の調子が良い。内容は……想像したくないが、こういう着想を句にできた作者は立派。八句目、外国人と思われる固有名詞、会話の一部と思われる具体的な台詞、ニッポン的なイメージを醸し出す季語の三点がアンバランスなようでバランスしている。九句目、車か特急列車に乗りながら窓外の景色に山が連なっている、という事実をうまく省略している。十句目、そう言われてみればそうだ。しかも、辞書だけではなく、世界の諸々に対象を拡張しても成立する真理かもしれない。
【山田露結】
難解を伴ふ春のショールかな
殺虫剤浴びてかがやく春の蝿
コピーして赤はグレーに昭和の日
うかつにも人の部分を蚊に刺され
えんぴつ削り回しくらげの話など
かたまつてゐて鶏頭のごとくなり
映りたる顔剥いてゆく林檎かな
紙の音して寒禽の飛び出づる
給油所をひとつ置きたる枯野かな
煮凝や音なく荒るる日本海
作者は、機智、滑稽、抒情、言葉、詩心といった相反しそうな要素を融合させようとしている。良い意味で「銀化」的である。露結句の笑いは決して下品ではないし、機智もシュールなほどに練られているものが多い。読み解く楽しみがある。一部の機智句(鬼畜ではない)には滑稽を越えて、哀しみや衝撃に達しているものもある。師・中原道夫の句と似た句も多いが、違いを指摘するとすれば、師の句が美意識や言葉への偏愛といった傾向が強いのに対し、露結句は敢えて美意識を捨て、どこか寂しく、懐かしく、暗く、哀しく、逆説的にいのちの讃歌となっている。機智や言葉で作る句は純粋な嘱目句とは別の意味で、それなりに類想も多いが、作者の句には比較的類想句は少ないものの、師の域を目指すとすれば、更に斬新な発想と精進が求められる。作者にはその素質があると思う。その可能性に大いに賭けたい。
一句目、複雑な形に結んだり解いたりするのに作中主体が苦労している様が浮かぶ。春ショールのデザイン性が難しいという句意ではないだろう。二句目、死ぬ前にこそ命は輝くと、いうフレーズのパロディー。殺虫剤に実際に濡れて光っているのだ。三句目、「昭和の日」という詠みにくい季語に挑戦し、成功を収めている。昭和時代にもカラーコピーは存在していたが、もはや二十年前に終わってしまった時代、当時の記憶もモノクロと化している。四句目、衣服等の人でない部分を刺される事はないはずだが、言い回しが面白い。人でも無機物でもない、獣の部分もあるという句意ではないはず。五句目、えんぴつ削りもノスタルジーを醸し出すアイテムを化してしまった現代だからこそ、この句が魅力的に思える。肝心の季語「くらげ」が会話の話題なので季感が多少弱いが、動きそうで動かない気もする。六句目、「鶏頭の十四五本もありぬべし」(正岡子規)の本歌取りか。本当の鶏頭ではなく、どこかでかたまっている別の何かを鶏頭に喩えているところが滑稽。七句目、不気味さが妙味。顔の映りたる皮を「映りたる顔」と省略しているところが俳句的な技。ただ、ワックスだらけでもない限り、林檎に顔が映る事はまずない。八句目、本当は寒禽が飛び出る際に紙と擦りあって音をさせたのであろうが、「紙の音し」という表現で寒禽と因果関係を断ちきり、「て」で作中主体の認識上の時間的小休止を持たせているのが技か。九句目は、只事報告句と捉える読者もいようが、「ひとつ置きたる」で「給油所」さえもミクロ的に扱い、「枯野」のマクロ的大きさを出す事に成功している。十句目、日本海の荒れているときの音は凄まじいので、「音なく荒るる日本海」は煮凝りを食べながら作中主体の脳裏に閃いたイメージ。音がなくても激しく荒れ狂っている。
<つづく>
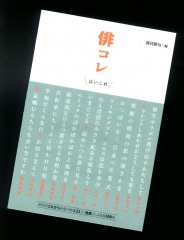 俳コレ 週刊俳句編 web shop 邑書林で買う |
執筆者紹介
- 堀田季何(ほった・きか)
「澤」・「吟遊」・「中部短歌」所属、「朱馬」代表。第三回芝不器男俳句新人賞斎藤慎爾奨励賞、第二回石川啄木賞(短歌部門)。






