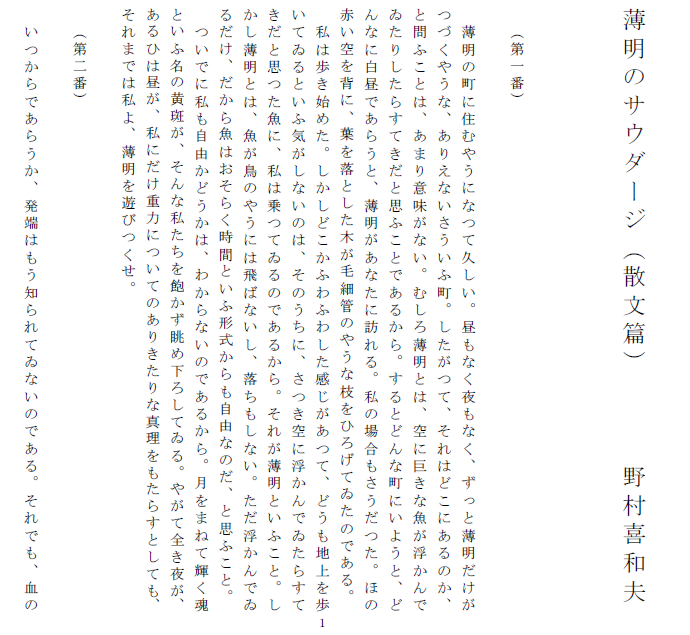薄明のサウダージ(散文篇) 野村喜和夫
(第一番)
薄明の町に住むやうになつて久しい。昼もなく夜もなく、ずっと薄明だけがつづくやうな、ありえないさういふ町。したがつて、それはどこにあるのか、と問ふことは、あまり意味がない。むしろ薄明とは、空に巨きな魚が浮かんでゐたりしたらすてきだと思ふことであるから。するとどんな町にいようと、どんなに白昼であらうと、薄明があなたに訪れる。私の場合もさうだつた。ほの赤い空を背に、葉を落とした木が毛細管のやうな枝をひろげてゐたのである。
私は歩き始めた。しかしどこかふわふわした感じがあつて、どうも地上を歩いてゐるといふ気がしないのは、そのうちに、さつき空に浮かんでゐたらすてきだと思つた魚に、私は乗つてゐるのであるから。それが薄明といふこと。しかし薄明とは、魚が鳥のやうには飛ばないし、落ちもしない。ただ浮かんでゐるだけ、だから魚はおそらく時間といふ形式からも自由なのだ、と思ふこと。
ついでに私も自由かどうかは、わからないのであるから。月をまねて輝く魂といふ名の黄斑が、そんな私たちを飽かず眺め下ろしてゐる。やがて全き夜が、あるひは昼が、私にだけ重力についてのありきたりな真理をもたらすとしても、それまでは私よ、薄明を遊びつくせ。
(第二番)
いつからであらうか、発端はもう知られてゐないのである。それでも、血の色をしたゼリー寄せのやうな薄明の町を、私はさまよひ歩いてゐた。友人が出る芝居に招待されたのだが、劇場の場所がわからない。するとふたりの役者のやうな通行人がやつて来て、ほらここが劇場です、と言つて青い小さな扉を指し示すのであるから、中を覗き込む。間違ひであつた。私は言ふ、同じ血の色をしたゼリー寄せのやうな町がひろがつてゐるだけ、劇場なんかないではないか。いやありますよ、通行人はなおも言ひ、どこに、と私ものめり込み、勢いあまつて、扉の中のその町に入り込んでしまふ。さうしてまたさまよふことになつたのである。
劇場はどこですか。するとふたりの役者のやうな通行人がやつて来て、ほらここが劇場です、と言つて青い小さな扉を指し示すのであるから、中を覗き込む。埒もないことであつた。またも血の色をしたゼリー寄せのやうな町がひろがつてゐて、なんだよこれ、と思ふほどに、消えろ消えろ、となにやら台詞のやうなものがきこえてきた。ほんの自分の出番のときだけ舞台のうへで見得を切つたり、わめいたり、そしてとどのつまりは消えてなくなる。え? 誰? シェークスピアみたいないまの台詞、と思ふほどに、私もまた役者の出で立ちで、月が出た月が出て地には卵黄ラヴソング、などとわめき始めてゐたのであるから。