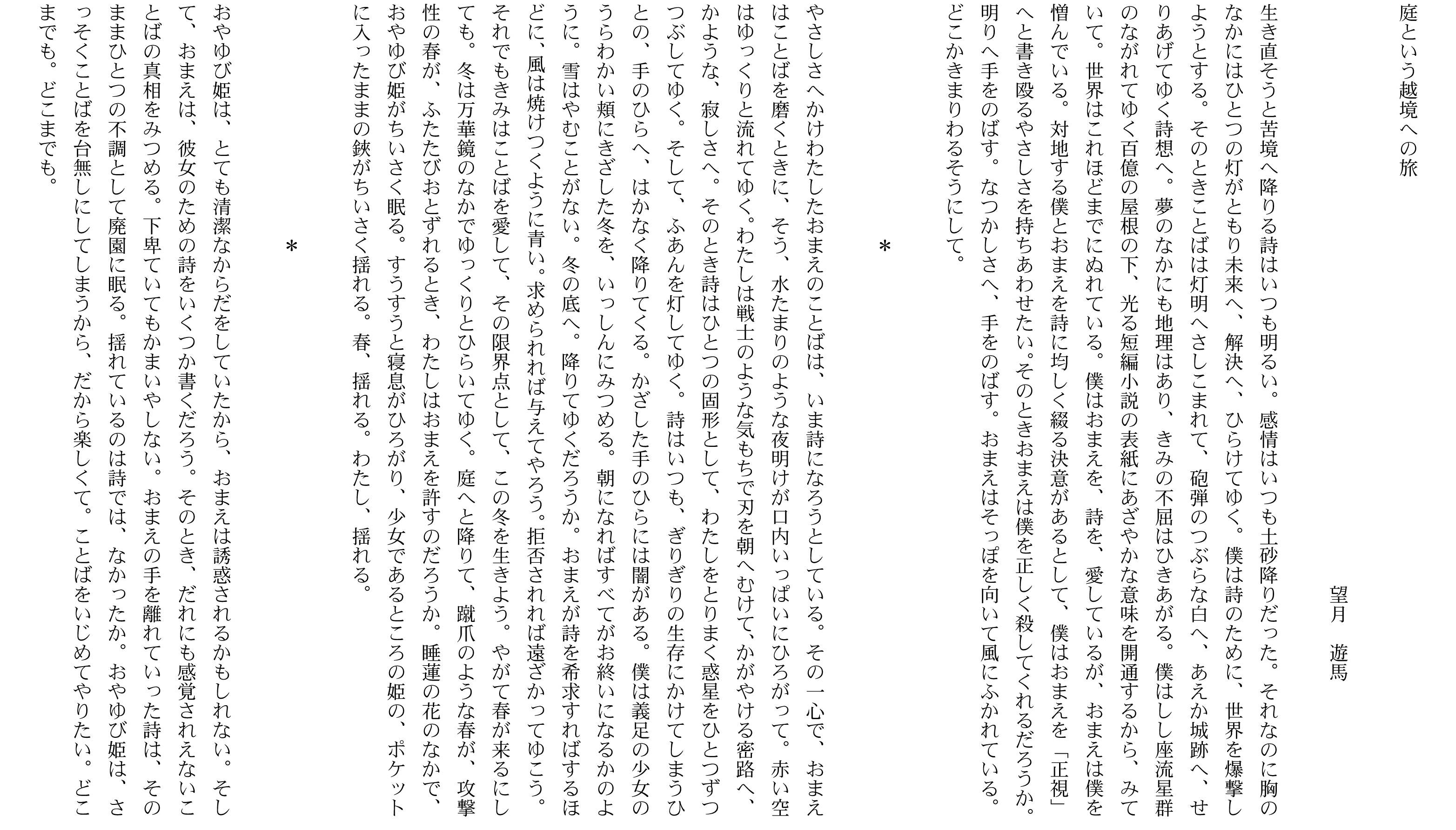庭という越境への旅 望月 遊馬
生き直そうと苦境へ降りる詩はいつも明るい。感情はいつも土砂降りだった。それなのに胸の
なかにはひとつの灯がともり未来へ、解決へ、ひらけてゆく。僕は詩のために、世界を爆撃し
ようとする。そのときことばは灯明へさしこまれて、砲弾のつぶらな白へ、あえか城跡へ、せ
りあげてゆく詩想へ。夢のなかにも地理はあり、きみの不屈はひきあがる。僕はしし座流星群
のながれてゆく百億の屋根の下、光る短編小説の表紙にあざやかな意味を開通するから、みて
いて。世界はこれほどまでにぬれている。僕はおまえを、詩を、愛しているが、おまえは僕を
憎んでいる。対地する僕とおまえを詩に均しく綴る決意があるとして、僕はおまえを「正視」
へと書き殴るやさしさを持ちあわせたい。そのときおまえは僕を正しく殺してくれるだろうか。
明りへ手をのばす。なつかしさへ、手をのばす。おまえはそっぽを向いて風にふかれている。
どこかきまりわるそうにして。
*
やさしさへかけわたしたおまえのことばは、いま詩になろうとしている。その一心で、おまえ
はことばを磨くときに、そう、水たまりのような夜明けが口内いっぱいにひろがって。赤い空
はゆっくりと流れてゆく。わたしは戦士のような気もちで刃を朝へむけて、かがやける密路へ、
かような、寂しさへ。そのとき詩はひとつの固形として、わたしをとりまく惑星をひとつずつ
つぶしてゆく。そして、ふあんを灯してゆく。詩はいつも、ぎりぎりの生存にかけてしまうひ
との、手のひらへ、はかなく降りてくる。かざした手のひらには闇がある。僕は義足の少女の
うらわかい頬にきざした冬を、いっしんにみつめる。朝になればすべてがお終いになるかのよ
うに。雪はやむことがない。冬の底へ。降りてゆくだろうか。おまえが詩を希求すればするほ
どに、風は焼けつくように青い。求められれば与えてやろう。拒否されれば遠ざかってゆこう。
それでもきみはことばを愛して、その限界点として、この冬を生きよう。やがて春が来るにし
ても。冬は万華鏡のなかでゆっくりとひらいてゆく。庭へと降りて、蹴爪のような春が、攻撃
性の春が、ふたたびおとずれるとき、わたしはおまえを許すのだろうか。睡蓮の花のなかで、
おやゆび姫がちいさく眠る。すうすうと寝息がひろがり、少女であるところの姫の、ポケット
に入ったままの鋏がちいさく揺れる。春、揺れる。わたし、揺れる。
*
おやゆび姫は、とても清潔なからだをしていたから、おまえは誘惑されるかもしれない。そし
て、おまえは、彼女のための詩をいくつか書くだろう。そのとき、だれにも感覚されえないこ
とばの真相をみつめる。下卑ていてもかまいやしない。おまえの手を離れていった詩は、その
ままひとつの不調として廃園に眠る。揺れているのは詩では、なかったか。おやゆび姫は、さ
っそくことばを台無しにしてしまうから、だから楽しくて。ことばをいじめてやりたい。どこ
までも。どこまでも。