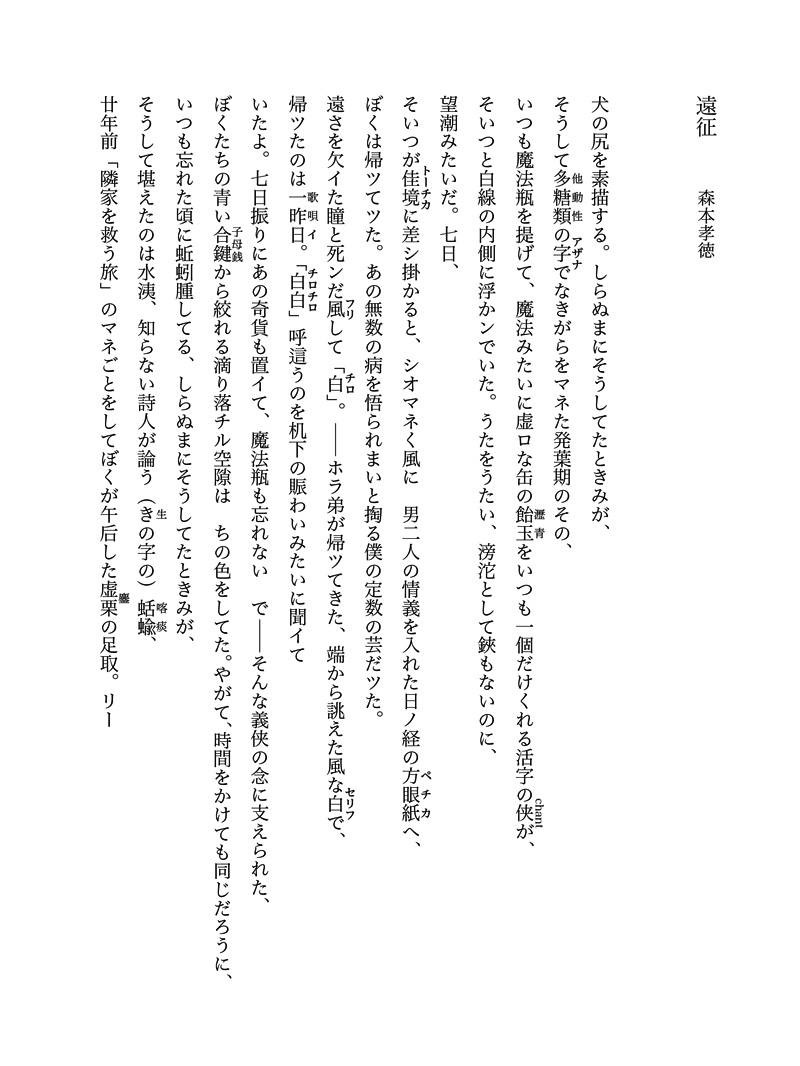遠征 森本孝徳
犬の尻を素描する。しらぬまにそうしてたときみが、
そうして
いつも魔法瓶を提げて、魔法みたいに虚ロな缶の
そいつと白線の内側に浮かンでいた。うたをうたい、滂沱として鋏もないのに、
望潮みたいだ。七日、
そいつが
ぼくは帰ツてツた。あの無数の病を悟られまいと掏る僕の定数の芸だツた。
遠さを欠イた瞳と死ンだ
帰ツたのは
いたよ。七日振りにあの奇貨も置イて、魔法瓶も忘れない で――そんな義侠の念に支えられた、
ぼくたちの青い
いつも忘れた頃に蚯蚓腫してる、しらぬまにそうしてたときみが、
そうして堪えたのは水洟、知らない詩人が論う(
廿年前「隣家を救う旅」のマネごとをしてぼくが午后した