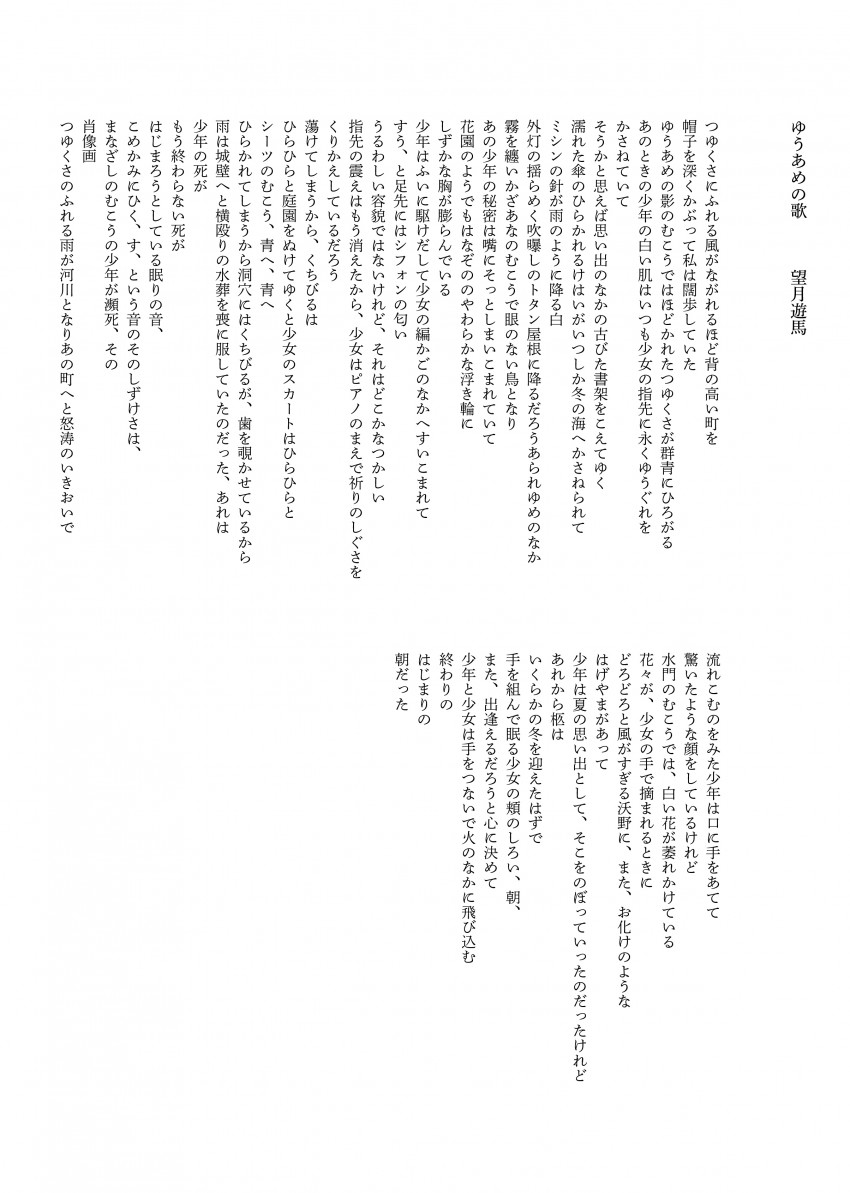ゆうあめの歌 望月遊馬
つゆくさにふれる風がながれるほど背の高い町を
帽子を深くかぶって私は闊歩していた
ゆうあめの影のむこうではほどかれたつゆくさが群青にひろがる
あのときの少年の白い肌はいつも少女の指先に永くゆうぐれを
かさねていて
そうかと思えば思い出のなかの古びた書架をこえてゆく
濡れた傘のひらかれるけはいがいつしか冬の海へかさねられて
ミシンの針が雨のように降る白
外灯の揺らめく吹曝しのトタン屋根に降るだろうあられゆめのなか
霧を纏いかざあなのむこうで眼のない鳥となり
あの少年の秘密は嘴にそっとしまいこまれていて
花園のようでもはなぞののやわらかな浮き輪に
しずかな胸が膨らんでいる
少年はふいに駆けだして少女の編かごのなかへすいこまれて
すう、と足先にはシフォンの匂い
うるわしい容貌ではないけれど、それはどこかなつかしい
指先の震えはもう消えたから、少女はピアノのまえで祈りのしぐさを
くりかえしているだろう
蕩けてしまうから、くちびるは
ひらひらと庭園をぬけてゆくと少女のスカートはひらひらと
シーツのむこう、青へ、青へ
ひらかれてしまうから洞穴にはくちびるが、歯を覗かせているから
雨は城壁へと横殴りの水葬を喪に服していたのだった、あれは
少年の死が
もう終わらない死が
はじまろうとしている眠りの音、
こめかみにひく、す、という音のそのしずけさは、
まなざしのむこうの少年が瀕死、その
肖像画
つゆくさのふれる雨が河川となりあの町へと怒涛のいきおいで
流れこむのをみた少年は口に手をあてて
驚いたような顔をしているけれど
水門のむこうでは、白い花が萎れかけている
花々が、少女の手で摘まれるときに
どろどろと風がすぎる沃野に、また、お化けのような
はげやまがあって
少年は夏の思い出として、そこをのぼっていったのだったけれど
あれから柩は
いくらかの冬を迎えたはずで
手を組んで眠る少女の頬のしろい、朝、
また、出逢えるだろうと心に決めて
少年と少女は手をつないで火のなかに飛び込む
終わりの
はじまりの
朝だった