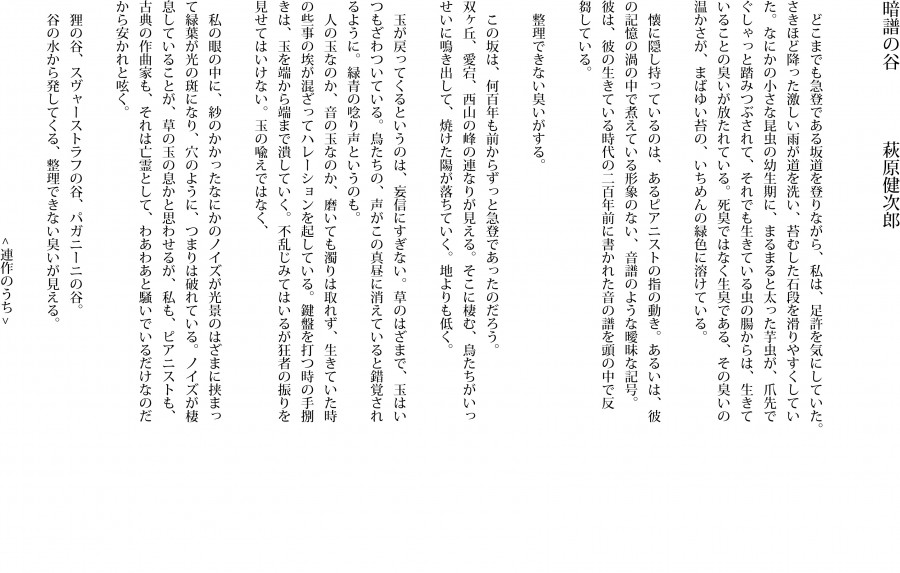暗譜の谷 萩原健次郎
どこまでも急登である坂道を登りながら、私は、足許を気にしていた。
さきほど降った激しい雨が道を洗い、苔むした石段を滑りやすくしてい
た。なにかの小さな昆虫の幼生期に、まるまると太った芋虫が、爪先で
ぐしゃっと踏みつぶされて、それでも生きている虫の腸からは、生きて
いることの臭いが放たれている。死臭ではなく生臭である、その臭いの
温かさが、まばゆい苔の、いちめんの緑色に溶けている。
懐に隠し持っているのは、あるピアニストの指の動き。あるいは、彼
の記憶の渦の中で煮えている形象のない、音譜のような曖昧な記号。
彼は、彼の生きている時代の二百年前に書かれた音の譜を頭の中で反
芻している。
整理できない臭いがする。
この坂は、何百年も前からずっと急登であったのだろう。
双ヶ丘、愛宕、西山の峰の連なりが見える。そこに棲む、鳥たちがいっ
せいに鳴き出して、焼けた陽が落ちていく。地よりも低く。
玉が戻ってくるというのは、妄信にすぎない。草のはざまで、玉はい
つもざわついている。鳥たちの、声がこの真昼に消えていると錯覚され
るように。緑青の唸り声というのも。
人の玉なのか、音の玉なのか、磨いても濁りは取れず、生きていた時
の些事の埃が混ざってハレーションを起している。鍵盤を打つ時の手捌
きは、玉を端から端まで潰していく。不乱じみてはいるが狂者の振りを
見せてはいけない。玉の喩えではなく、
私の眼の中に、紗のかかったなにかのノイズが光景のはざまに挟まっ
て緑葉が光の斑になり、穴のように、つまりは破れている。ノイズが棲
息していることが、草の玉の息かと思わせるが、私も、ピアニストも、
古典の作曲家も、それは亡霊として、わあわあと騒いでいるだけなのだ
から安かれと呟く。
狸の谷、スヴャーストラフの谷、パガニーニの谷。
谷の水から発してくる、整理できない臭いが見える。
<連作のうち>