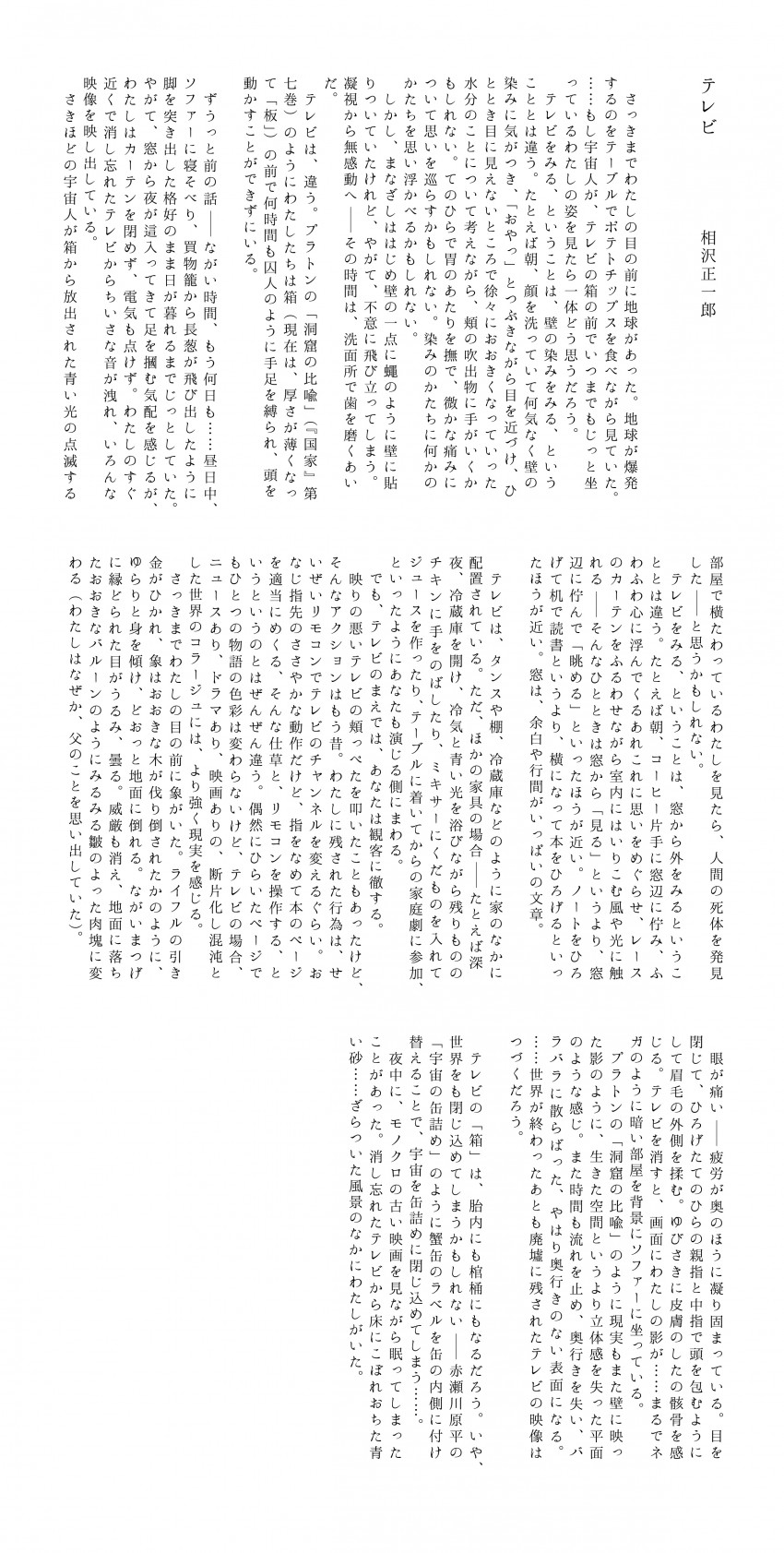テレビ 相沢正一郎
さっきまでわたしの目の前に地球があった。地球が爆発
するのをテーブルでポテトチップスを食べながら見ていた。
……もし宇宙人が、テレビの箱の前でいつまでもじっと坐
っているわたしの姿を見たら一体どう思うだろう。
テレビをみる、ということは、壁の染みをみる、という
こととは違う。たとえば朝、顔を洗っていて何気なく壁の
染みに気がつき、「おやっ」とつぶきながら目を近づけ、ひ
ととき目に見えないところで徐々におおきくなっていった
水分のことについて考えながら、頬の吹出物に手がいくか
もしれない。てのひらで胃のあたりを撫で、微かな痛みに
ついて思いを巡らすかもしれない。染みのかたちに何かの
かたちを思い浮かべるかもしれない。
しかし、まなざしははじめ壁の一点に蠅のように壁に貼
りついていたけれど、やがて、不意に飛び立ってしまう。
凝視から無感動へ――その時間は、洗面所で歯を磨くあい
だ。
テレビは、違う。プラトンの「洞窟の比喩」(『国家』第
七巻)のようにわたしたちは箱(現在は、厚さが薄くな
って「板」)の前で何時間も囚人のように手足を縛られ、
頭を動かすことができずにいる。
ずうっと前の話――ながい時間、もう何日も……昼日中、
ソファーに寝そべり、買物籠から長葱が飛び出したよう
に脚を突き出した格好のまま日が暮れるまでじっとして
いた。やがて、窓から夜が這入ってきて足を摑む気配を
感じるが、わたしはカーテンを閉めず、電気も点けず。
わたしのすぐ近くで消し忘れたテレビからちいさな音が
洩れ、いろんな映像を映し出している。
さきほどの宇宙人が箱から放出された青い光の点滅する
部屋で横たわっているわたしを見たら、人間の死体を発
見した――と思うかもしれない。
テレビをみる、ということは、窓から外をみるというこ
ととは違う。たとえば朝、コーヒー片手に窓辺に佇み、ふ
わふわ心に浮んでくるあれこれに思いをめぐらせ、レース
のカーテンをふるわせながら室内にはいりこむ風や光に触
れる――そんなひとときは窓から「見る」というより、窓
辺に佇んで「眺める」といったほうが近い。ノートをひろ
げて机で読書というより、横になって本をひろげるといっ
たほうが近い。窓は、余白や行間がいっぱいの文章。
テレビは、タンスや棚、冷蔵庫などのように家のなかに
配置されている。ただ、ほかの家具の場合――たとえば深
夜、冷蔵庫を開け、冷気と青い光を浴びながら残りものの
チキンに手をのばしたり、ミキサーにくだものを入れてジ
ュースを作ったり、テーブルに着いてからの家庭劇に参加、
といったようにあなたも演じる側にまわる。
でも、テレビのまえでは、あなたは観客に徹する。
映りの悪いテレビの頬っぺたを叩いたこともあったけど、
そんなアクションはもう昔。わたしに残された行為は、
せいぜいリモコンでテレビのチャンネルを変えるぐらい。
おなじ指先のささやかな動作だけど、指をなめて本のペ
ージを適当にめくる、そんな仕草と、リモコンを操作す
る、というというのとはぜんぜん違う。偶然にひらいた
ページでもひとつの物語の色彩は変わらないけど、テレ
ビの場合、ニュースあり、ドラマあり、映画ありの、断
片化し混沌とした世界のコラージュには、より強く現実
を感じる。
さっきまでわたしの目の前に象がいた。ライフルの引き
金がひかれ、象はおおきな木が伐り倒されたかのように、
ゆらりと身を傾け、どおっと地面に倒れる。ながいまつ
げに縁どられた目がうるみ、曇る。威厳も消え、地面に
落ちたおおきなバルーンのようにみるみる皺のよった肉
塊に変わる(わたしはなぜか、父のことを思い出してい
た)。
眼が痛い――疲労が奥のほうに凝り固まっている。目を
閉じて、ひろげたてのひらの親指と中指で頭を包むよう
にして眉毛の外側を揉む。ゆびさきに皮膚のしたの骸骨
を感じる。テレビを消すと、画面にわたしの影が……ま
るでネガのように暗い部屋を背景にソファーに坐ってい
る。
プラトンの「洞窟の比喩」のように現実もまた壁に映っ
た影のように、生きた空間というより立体感を失った平面
のような感じ。また時間も流れを止め、奥行きを失い、バ
ラバラに散らばった、やはり奥行きのない表面になる。
……世界が終わったあとも廃墟に残されたテレビの映像は
つづくだろう。
テレビの「箱」は、胎内にも棺桶にもなるだろう。いや、
世界をも閉じ込めてしまうかもしれない――赤瀬川原平
の「宇宙の缶詰め」のように蟹缶のラベルを缶の内側に
付け替えることで、宇宙を缶詰めに閉じ込めてしまう……。
夜中に、モノクロの古い映画を見ながら眠ってしまった
ことがあった。消し忘れたテレビから床にこぼれおちた
青い砂……ざらついた風景のなかにわたしがいた。