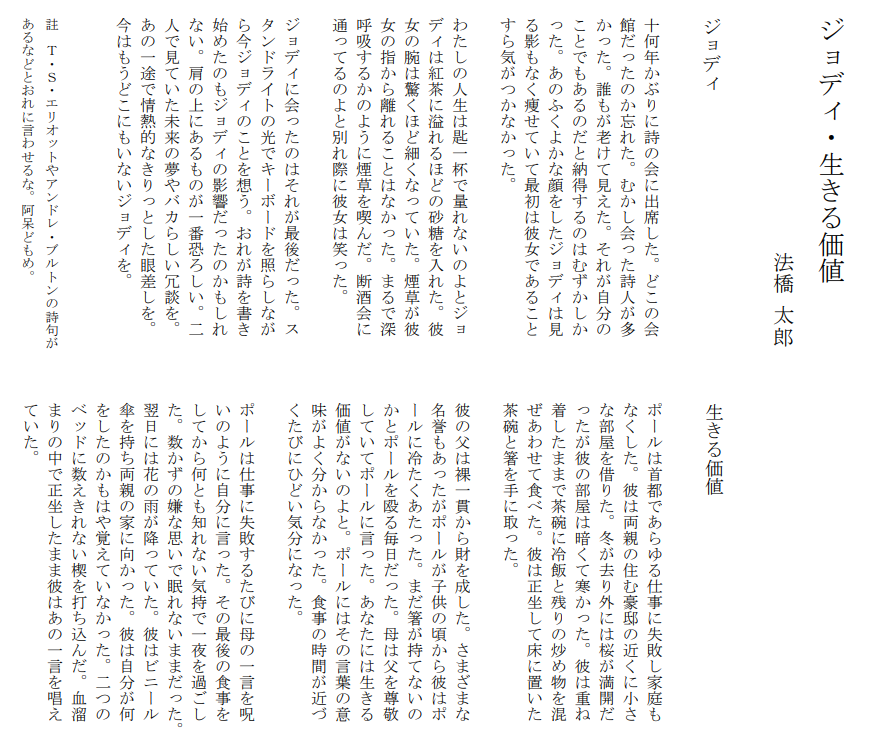ジョディ・生きる価値 法橋 太郎
ジョディ
十何年かぶりに詩の会に出席した。どこの会
館だったのか忘れた。むかし会った詩人が多
かった。誰もが老けて見えた。それが自分の
ことでもあるのだと納得するのはむずかしか
った。あのふくよかな顔をしたジョディは見
る影もなく痩せていて最初は彼女であること
すら気がつかなかった。
わたしの人生は匙一杯で量れないのよとジョ
ディは紅茶に溢れるほどの砂糖を入れた。彼
女の腕は驚くほど細くなっていた。煙草が彼
女の指から離れることはなかった。まるで深
呼吸するかのように煙草を喫んだ。断酒会に
通ってるのよと別れ際に彼女は笑った。
ジョディに会ったのはそれが最後だった。ス
タンドライトの光でキーボードを照らしなが
ら今ジョディのことを想う。おれが詩を書き
始めたのもジョディの影響だったのかもしれ
ない。肩の上にあるものが一番恐ろしい。二
人で見ていた未来の夢やバカらしい冗談を。
あの一途で情熱的なきりっとした眼差しを。
今はもうどこにもいないジョディを。
註 T・S・エリオットやアンドレ・ブルトンの詩句が
あるなどとおれに言わせるな。阿呆どもめ。
生きる価値
ポールは首都であらゆる仕事に失敗し家庭も
なくした。彼は両親の住む豪邸の近くに小さ
な部屋を借りた。冬が去り外には桜が満開だ
ったが彼の部屋は暗くて寒かった。彼は重ね
着したままで茶碗に冷飯と残りの炒め物を混
ぜあわせて食べた。彼は正坐して床に置いた
茶碗と箸を手に取った。
彼の父は裸一貫から財を成した。さまざまな
名誉もあったがポールが子供の頃から彼はポ
ールに冷たくあたった。まだ箸が持てないの
かとポールを殴る毎日だった。母は父を尊敬
していてポールに言った。あなたには生きる
価値がないのよと。ポールにはその言葉の意
味がよく分からなかった。食事の時間が近づ
くたびにひどい気分になった。
ポールは仕事に失敗するたびに母の一言を呪
いのように自分に言った。その最後の食事を
してから何とも知れない気持で一夜を過ごし
た。数かずの嫌な思いで眠れないままだった。
翌日には花の雨が降っていた。彼はビニール
傘を持ち両親の家に向かった。彼は自分が何
をしたのかもはや覚えていなかった。二つの
ベッドに数えきれない楔を打ち込んだ。血溜
まりの中で正坐したまま彼はあの一言を唱え
ていた。