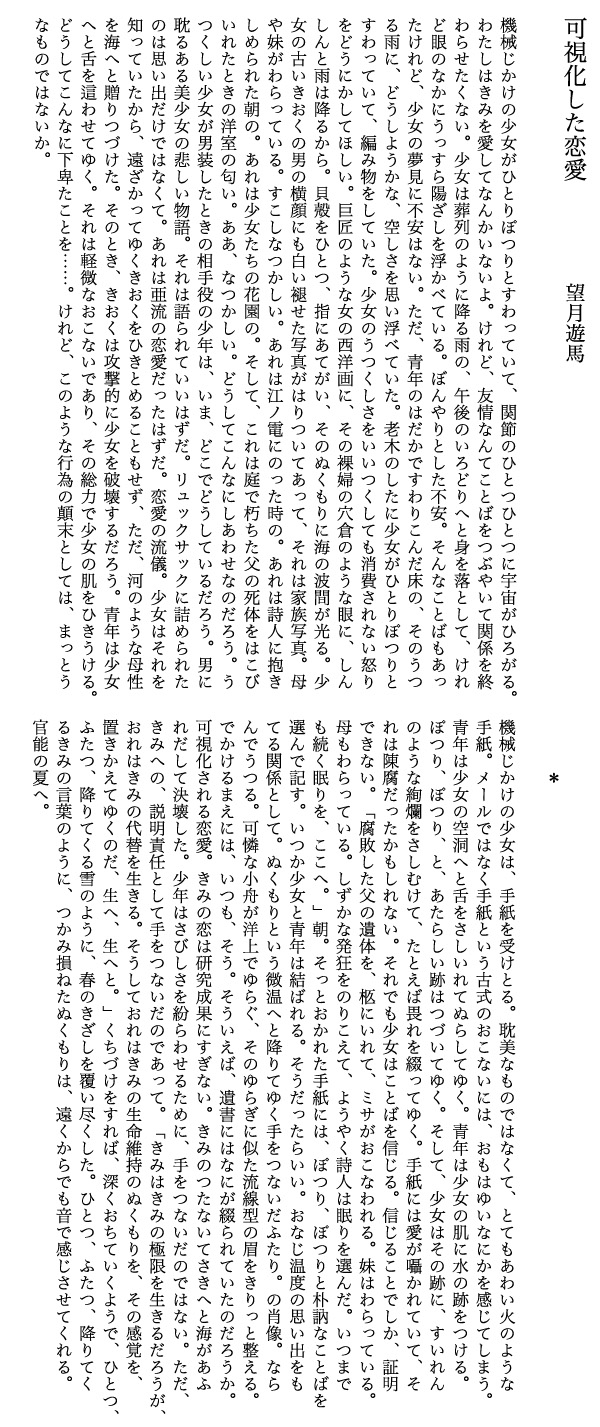可視化した恋愛 望月遊馬
機械じかけの少女がひとりぽつりとすわっていて、関節のひとつひとつに宇宙がひろがる。
わたしはきみを愛してなんかいないよ。けれど、友情なんてことばをつぶやいて関係を終
わらせたくない。少女は葬列のように降る雨の、午後のいろどりへと身を落として、けれ
ど眼のなかにうっすら陽ざしを浮かべている。ぼんやりとした不安。そんなことばもあっ
たけれど、少女の夢見に不安はない。ただ、青年のはだかですわりこんだ床の、そのうつ
る雨に、どうしようかな、空しさを思い浮べていた。老木のしたに少女がひとりぽつりと
すわっていて、編み物をしていた。少女のうつくしさをいいつくしても消費されない怒り
をどうにかしてほしい。巨匠のような女の西洋画に、その裸婦の穴倉のような眼に、しん
しんと雨は降るから。貝殻をひとつ、指にあてがい、そのぬくもりに海の波間が光る。少
女の古いきおくの男の横顔にも白い褪せた写真がはりついてあって、それは家族写真。母
や妹がわらっている。すこしなつかしい。あれは江ノ電にのった時の。あれは詩人に抱き
しめられた朝の。あれは少女たちの花園の。そして、これは庭で朽ちた父の死体をはこび
いれたときの洋室の匂い。ああ、なつかしい。どうしてこんなにしあわせなのだろう。う
つくしい少女が男装したときの相手役の少年は、いま、どこでどうしているだろう。男に
耽るある美少女の悲しい物語。それは語られていいはずだ。リュックサックに詰められた
のは思い出だけではなくて。あれは亜流の恋愛だったはずだ。恋愛の流儀。少女はそれを
知っていたから、遠ざかってゆくきおくをひきとめることもせず、ただ、河のような母性
を海へと贈りつづけた。そのとき、きおくは攻撃的に少女を破壊するだろう。青年は少女
へと舌を這わせてゆく。それは軽微なおこないであり、その総力で少女の肌をひきうける。
どうしてこんなに下卑たことを……。けれど、このような行為の顛末としては、まっとう
なものではないか。
*
機械じかけの少女は、手紙を受けとる。耽美なものではなくて、とてもあわい火のような
手紙。メールではなく手紙という古式のおこないには、おもはゆいなにかを感じてしまう。
青年は少女の空洞へと舌をさしいれてぬらしてゆく。青年は少女の肌に水の跡をつける。
ぽつり、ぽつり、と、あたらしい跡はつづいてゆく。そして、少女はその跡に、すいれん
のような絢爛をさしむけて、たとえば畏れを綴ってゆく。手紙には愛が囁かれていて、そ
れは陳腐だったかもしれない。それでも少女はことばを信じる。信じることでしか、証明
できない。「腐敗した父の遺体を、柩にいれて、ミサがおこなわれる。妹はわらっている。
母もわらっている。しずかな発狂をのりこえて、ようやく詩人は眠りを選んだ。いつまで
も続く眠りを、ここへ。」朝。そっとおかれた手紙には、ぽつり、ぽつりと朴訥なことばを
選んで記す。いつか少女と青年は結ばれる。そうだったらいい。おなじ温度の思い出をも
てる関係として。ぬくもりという微温へと降りてゆく手をつないだふたり。の肖像。なら
んでうつる。可憐な小舟が洋上でゆらぐ、そのゆらぎに似た流線型の眉をきりっと整える。
でかけるまえには、いつも、そう。そういえば、遺書にはなにが綴られていたのだろうか。
可視化される恋愛。きみの恋は研究成果にすぎない。きみのつたないてさきへと海があふ
れだして決壊した。少年はさびしさを紛らわせるために、手をつないだのではない。ただ、
きみへの、説明責任として手をつないだのであって。「きみはきみの極限を生きるだろうが、
おれはきみの代替を生きる。そうしておれはきみの生命維持のぬくもりを、その感覚を、
置きかえてゆくのだ、生へ、生へと。」くちづけをすれば、深くおちていくようで、ひとつ、
ふたつ、降りてくる雪のように、春のきざしを覆い尽くした。ひとつ、ふたつ、降りてく
るきみの言葉のように、つかみ損ねたぬくもりは、遠くからでも音で感じさせてくれる。
官能の夏へ。